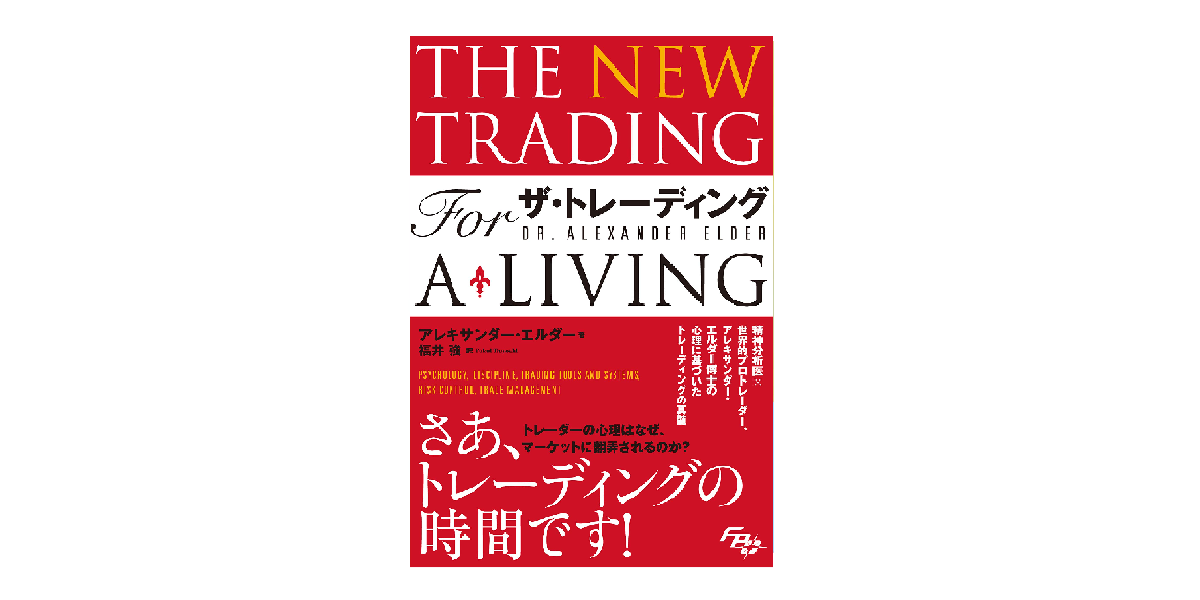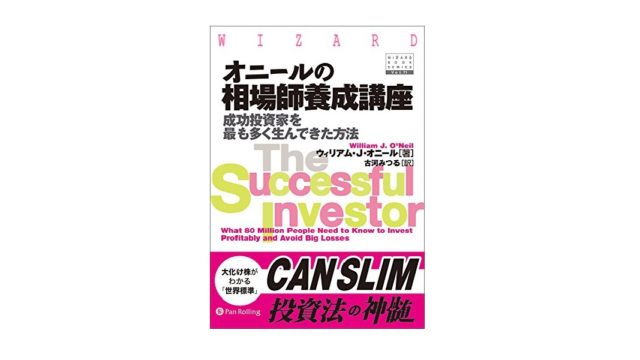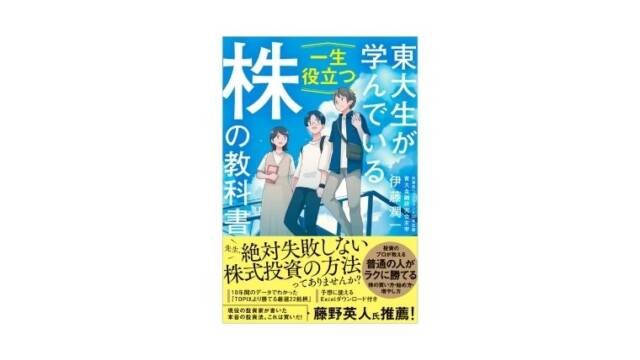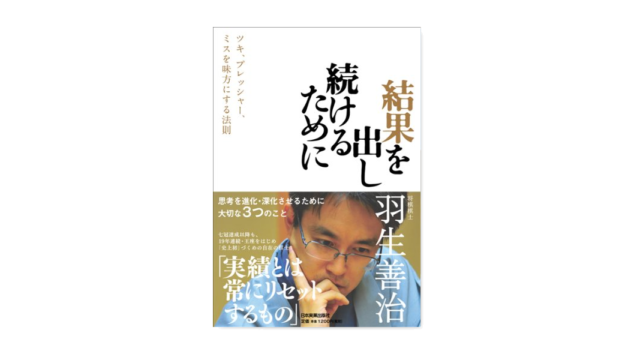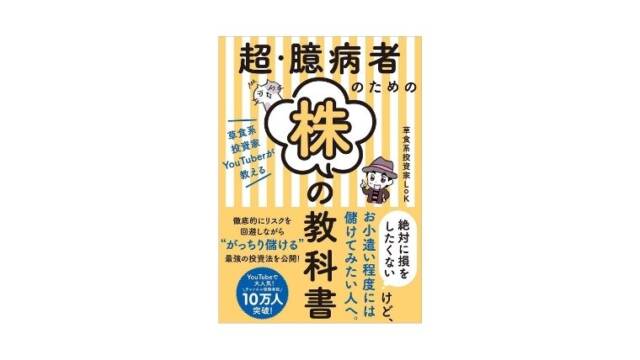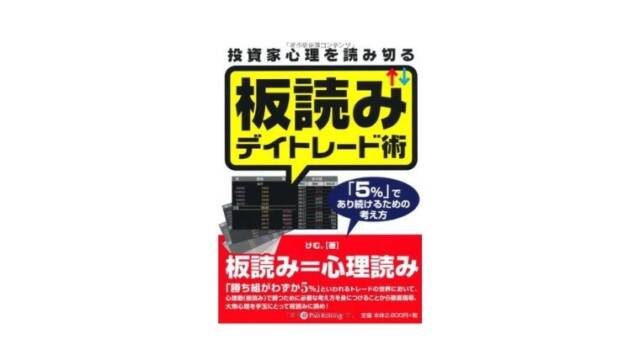投資の勉強をするために、たくさんの本を読んで勉強しています。
『ザ・トレーディング』を読んでいるだけでは記憶になかなか残りにくいため、インプットした知識を整理して、
- 「読んで勉強になったこと」
- 「理解が及ばず、さらに勉強をしなくてはいけないこと」
を感じたままに書き留めています。
とても勉強になりましたので、書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんがご紹介いたします。
目次
『ザ・トレーディング』とは?
| 読みやすさ | |
|---|---|
| 専門性 | |
| 役立ち度 |
- 著者:
- 出版社:FPO
- 発売日:2019/3/1
- ページ数:509ページ
【目次】
- イントロダクション
- 第1章 個人の心理
- 第2章 集団の心理
- 第3章 古典チャート分析
- 第4章 コンピューターを使ったテクニカル分析
- 第5章 出来高と時間
- 第6章 マーケット全般の指標
- 第7章 トレーディングシステム
- 第8章 トレーディング対象商品
- 第9章 リスク管理
- 第10章 実践的なトレーディングの詳細
- 第11章 トレードの適正な記録管理
- 結論 終わりなき旅 学び続ける方法
『ザ・トレーディング』は、パンローリングから刊行された『投資苑』を大幅に加筆・改定し、新たな章を設けた内容で、初版から21年経ってから完全新訳されたものです。
『投資苑』は、全世界で500万部超の大ベストセラー! 17カ国語に翻訳され、有名な古典です。
図表もフルカラーになり、トレーディング業界の最高権威米国アナリスト協会MTA(Market Technicians Association)のテクニカルアナリスト資格CMT指定図書になっています。
『ザ・トレーディング』を完全マスターするための手引き書『ザ・トレーディング ワークブック』も出されており、トレーディングにおける基本的なルールとスキルが確実に身についたかを確認することができます。
『ザ・トレーディング』を読んで勉強になったこと

トレーディングで成功するために必要不可欠な4つのMが基本指針です。
- MIND─欲と恐怖、衝動を排除する心理分析
- METHOD─厳選されたチャートパターンとトレード戦略
- MONEY─数値に裏打ちされた客観的なリスク管理
- MANAGEMENT─「3つのM」を強固に結びつける記録管理
「心理分析・トレード戦略・リスク管理・記録管理」に主眼を置いて、理性的なアプローチを教示するこの規範的なガイド・明確なルールが具体的に示されています。
これらの重要なことが記載されているので、章ごとに重要な箇所をまとめさせていただきます。
イントロダクション
【イントロダクションの小見出し】
- 1. トレーディング ── 最後のフロンティア
- 2. 心理が成功の鍵を握る
- 3. あなたに不利な勝ち目
トレーディングは、自由に世界中のどこにでも生活・働くことができる手段です。
成功するには心理的問題を乗り越えなければならず、そのために本書がまとめられていることが分かります。
第1章 個人の心理
【第1章の小見出し】
- 4. なぜトレーディングをするのか
- 5. 現実と幻想
- 6. 自己破壊性向
- 7. トレーディングの心理
- 8. アルコール依存症患者の会から学んだトレーディングの教訓
- 9. 損失依存症患者の会
- 10. 勝者と敗者
優れたトレーダーは、「トレーディングを上手にすること」を目標にしており、自己の最善を尽くすために常に技術の研鑽を怠りません。
トレード結果に一喜一憂せず、自分の力量と限界を知っています。
負けているトレーダーは、適切なトレードサイズを確保せず、リスク管理を実施できません。
少しばかりの知識を身につけてトレードに勝てるものの、感情を持ち込んで自滅していきます。
マーケットで勝つためには、「健全な心理状態」「理にかなったトレーディングシステム」「実効性のある計画的なリスク管理」を習得する必要があります。
失敗の原因は、トレード手法にあったのではなく、自らの考え方にあると考えることができます。
感情的なトレードは必ず損失を招くため、恐怖心・欲・高揚感が生じた場合、ポジションを手仕舞い、トレーディングを制御できなくなったことを認めるべきです。
精神的に規律として、7つのルールが記載されています。
- マーケットに長時間留まる位置を固めること。
- できる限り学ぶこと。
- 欲をかいて性急にトレードしないこと。
- 相場を分析する手法を開発すること。
- 資金管理の計画を立てること。
- どのようなトレーディングシステムを使っても、トレーダー自身が最も脆弱であると認識すること。
- 自分の心の中にある幻想を追い払い、これまでの生き方や考え方、行動様式を変えること。
第2章 集団の心理
【第2章の小見出し】
- 11. 価格とは何か
- 12. マーケットとは何か
- 13. トレーディングの舞台に登場する人々
- 14. マーケットの群衆とあなた
- 15. トレンドの心理
- 16. ポジション管理対予想
マーケットは人間の巨大な集合体で、市場価格は全ての市場参加者の総意です。
価格が上下するのは、買い手・売りの数が異なるのではなく、買い手と売り手の恐怖の度合いが変化するからです。
人間は群衆に参加して同じように行動したいという強い欲求を感じ、群衆に加わると原始的・衝動的な思考になる傾向があり、価格の動きに飛び乗ったり、咄嗟に意思決定してしまいます。
そのため、抜け目のないトレーダーは、相場が静かな時を狙ってポジションを取り、相場が大きく動いたときに利食いします。
トレードの目標は、「頻繁にトレードすること」ではなく、「上手にトレードすること」です。
機関投資家は常にトレードしなければならないが、個人トレーダーには参加するかの自由裁量があるので、トレードをしすぎず優位性を発揮できます。
バイアスを見つけるために、買いたいと思ったチャートを反転させて売りたいと思うかどうか判断する方法が記載されています。
第3章 古典的チャート分析
【第3章の小見出し】
- 17. チャートを描く
- 18. サポートとレジスタンス
- 19. トレンドと保ち合いレンジ
- 20. カンガルーテイル
古典的チャート分析は、主観的で希望的思考・自己欺瞞を招き易いという難点があります。
水平線で描くサポート・レジスタンスには意味がありますが、斜めに引いたトレンドラインは主観的で危険です。
バーチャート
バーチャートから、アマチュアが1日の始まり・週の始まりに活発にトレードすること、日足・週足の終値がプロトレーダーの行動を表す傾向があることがわかっています
弱気相場では月曜日・火曜日に高値をつけて週末にかけて安値をつける傾向があり、強気相場ではその逆です。
バーが短い時に仕掛け、バーが長い時に利確するのが良いとも記載されています。
サポート・レジスタンス
サポート・レジスタンスは、大多数のトレーダーがその価格水準で苦痛・後悔を感じているために存在するものです。
保ち合いレンジの強度は「期間・値幅・出来高」の3つの要素で決まります。
サポート・レジスタンスは、短い時間枠のチャートより長い時間枠のチャートの方がより重要になります。
マーケットはトレンド相場よりもレンジ相場に長い時間を費やし、保ち合いからのブレイクアウトはほとんどダマシです。
そのためプロトレーダーはレンジ継続に賭ける傾向があり、著者はブレイクアウトした方向とは逆にポジションを取って少し離れたところに損切り注文をおく「ダマシのブレイクアウト」でのトレードを勧めています。
ダマシのブレイクアウトは、薄商いなのが特徴です。
逆に保ち合いからのブレイクアウトを狙うのであれば、「ブレイクアウトを見越して買うか」「ブレイクアウトの最中に買うか」「ブレイクアウトが起きた後の押し目で買うか」の3つ選択肢があり、3回に分けて買うのも1つの手として紹介されています。
第4章 コンピューター・テクニカル分析
【第4章の小見出し】
- 21. トレーディングにおけるコンピューター
- 22. 移動平均
- 23. MACDーラインとヒストグラム
- 24. DMI
- 25. オシレーター系指標
- 26. ストキャスティック
- 31. RSI
テクニカル指標は、トレンドとその反転を見つけるのに役立ち以下のものが紹介されています。
- トレンド系指標:移動平均・MACD・DMI等)
- オシレーター系指標(MACDヒストグラム・ストキャスティクス・RSI等)
- 多種多様なその他の指標(新高値・新安値指数等)
トレンド指標はトレンドを見つけるのに活用し、オシレーター指標はトレンドの転換点を掴むのに活用します。
これらを組み合わせて相場判断をし、たった1つの指標に基づいて意思決定をしないことを強く指示しています。
移動平均
単純移動平均は、たった1つの古い価格が計算期間から外れるだけで急激に変化してしまいます。
そのため、単純移動平均では指数移動平均を使うことを推奨しています。
移動平均が発する重要なメッセージは、方向と角度です。
移動平均が上向きで買い下向きで売り、移動平均線に近いところで仕掛けます。
MACD
MACDラインとシグナルラインがクロスすると、買いて・売り手の力関係が変化したことを表します。
週足でMACDヒストグラムの傾きの変化で、相場が急反発する「乖離」という現象について着目するように推奨しています。
強気の乖離は、価格の安値を更新するがMACDは前回の下落時に形成した谷より浅い水準で止まる状態で、弱気の乖離はその逆です。
ストキャスティクス・RSI
ストキャスティクスは、0〜100%の間で動くように設計されており、80%以上であれば買われすぎ、20%未満なら売られすぎを表します。
RSIは、70%以上であれば買われすぎ、30%未満なら売られすぎを表します。
第5章 出来高と時間
【第5章の小見出し】
- 28. 出来高
- 29. 出来高に基づくテクニカル指標
- 30. 勢力指数
- 31. 取組高
- 32. 時間
- 33. トレードするときの時間枠
出来高は、どれくらい市場参加者がいるのか、どれくらい活発に取引しているか、トレーダーや投資家の行動を移す鏡です。
当日の出来高が直近2週間の平均より25%以上多ければ「出来高が高い」と定義しています。
トレーダーは茹でガエルのような反応を示し、急な価格変動に襲われるとポジションを手仕舞いますが、損が徐々に大きくなっていくと非常に我慢強く耐えます。
恐怖は短時間しか続かない衝動的なもので、欲はゆっくり熟成され高揚感をもたらします。
そのため、徐々に出来高ができている場合にはトレンドが継続しますが、出来高が急増した場合にそこでトレンドが終了する可能性があります。
出来高が減少している場合には、敗者の数も減っているためトレンドが反転する準備が整いつつあります。
OBV(オンボリューム・バランス)、A/D(アキュミュレーション/ディストリビューション)、勢力指数など出来高を用いた指標も紹介されています。
時間については、群衆は気に留めず、値動きばかりに気が向き、ベテラントレーダーが遅いと感じるほど群衆は遅く動きます。
第6章 マーケット全般の指標
【第6章の小見出し】
- 34. 新高値・新安値指数
- 35. 50日移動平均より上にある株
- 36. その他の株式市場の指標
- 37. コンセンサス指標とコミットメント指標
相場に対する見解が高いレベルで一致した場合、反転する前触れになります。
群衆が非常に強気になったら、空売りする準備をするのを勧めています。
一流ビジネス誌の表紙が逆張りの指標として役立つのはそのためで、主要な新聞・雑誌が「絶好の投資チャンス」という広告が3つ以上掲載されたときは、相場の天井が間近に迫っています。
第7章 トレーディングシステム
【第7章の小見出し】
- 38. システムトレード、ペーパトレード、すべてのトレードに必須な3つの事項
- 39. トリプルスクリーン・トレーディングシステム
- 40. インパルスシステム
- 41. チャネル・トレーディングシステム
トレーディングシステムに多くの種類があり、大きく分けると「メカニカルトレーダー・裁量トレーダー」に分かれます。
メカニカルトレーダーは、開発したトレードルールを過去のフェーたを使ってバックテストし、システムを自動操縦にして実際に運用します。
裁量トレーダーは、毎日相場に足して新たにアプローチをし、多くの要因を分析し、異なる方法で重点の置き方を変え、現場の相場の動きに調子を合わせます。
著者が考えたメカニカルトレードのトリプルスクリーン・トレーディングシステム、裁量トレードのインパルスシステムが紹介されています。
トリプルスクリーン・トレーディングシステム
トリプルスクリーン・トレーディングシステムは、3つのスクリーンによるテストをパスしたものをトレードを行います。
第1のスクリーンは長期のチャートを分析することを目的にし、週足のトレンド系指標でトレンド把握します。
第2のスクリーンでは、トレンド内の押し目を探すために、日足のオシレーター指標で週足との逆行を見つけます。
第3のスクリーンでは、仕掛けのタイミングを探すため、日足以下のブレイクアウトポイントを見つけます
利食い・損切りは、長期チャートで利食いを行い、中期チャートで損切りを行います。
インパルスシステム
インパルスシステムは、トレードの可否を判断する検閲システムです。
週足か日足のEMAの傾きとMACDヒストグラムの傾きが一致している場合は、傾きの方向へのトレードが許可され、傾き方向と逆行するトレードが禁止されます。
逆にEMAの傾きとMACDヒストグラムの傾きが一致しない場合は、何も制限はありません。
第8章 トレーディング対象商品
【第8章の小見出し】
- 42. 株式
- 43. 上場投資信託(ETF)
- 44. オプション
- 45. 差金決済取引(CFD)
- 46. 先物
- 47. 外国為替証拠金取引(FX)
どんなトレーディング対象商品を選んでも、流動性・ボラティリティ・時間帯が大事です。
流動性が高ければ高いほど、トレードが容易になり、劣悪なスリッページも回避できます。
ボラティリティが高ければ高いほど、トレードチャンスが多くなります。
自国の時間帯から遠く離れたトレード商品は自身を不利な立場に置くことになるので、自分と同じ時間帯のトレードが良いです。
株式・上場投資信託(ETF)・オプション・差金決済取引(CFD)・先物・外国為替証拠金取引(FX)の特徴や戦略についても簡単に記載されていました。
第9章 リスク管理
【第9章の小見出し】
- 48. 感情と確立
- 49. リスク管理の二大ルール
- 50. 2%ルール
- 51. 6%ルール
- 51. ドローダウンからの回復
- プロトレーダーは、トレードを管理することに集中し、感情をコントロールしています。
- 感情的なトレーダーは、確実な利益にし不確実性を伴ってもより儲ける可能性のある賭けを好み、損を実現することを遅らせる危険なギャンブルに挑みます。
- 個別のトレードの勝ち負けについて感情的にならないように努めなければなりません。
- リスク管理の二大ルールとして
「2%ルール」「6%ルール」
- を定めています。
「2%ルール」は、1回のトレードで資金の2%以上をリスクにさらすことを禁止します。
「6%ルール」は、今月の実現損失とトレード中のポジションのリスク額の合計が資金の6%に達したら、新規のトレードを月末まで禁止します。
最大のリスクを示しているため、これよりも小さいリスクで運用する方が良いかもしれません。
これらのルールに従っていても大きなドローダウンに見舞われることはあります。
大きなドローダウンから回復するために、トレードサイズを100株に落として、2週連続で儲けられたら、次の週から100株多くトレードをできるようにし、1週でも負けるとそれ以前のサイズに戻るルールを適応します。
第10章 リスク・マネジメント
【第10章の小見出し】
- 53. 利食い目標の設定方法ー「もう充分」が強い効力を発揮する
- 54. 損切り注文の置き方ー希望的観測は禁物
- 55. これはグレードAのトレードか
- 56. 可能性のあるトレードをスキャンする
プロトレーダーは自分が望む方向に相場が走り始めるまでに何度か挑戦し、小額の損を必要経費と見なして受け入れます。
潜在的報酬は、リスクの最低2倍かそれ以上であるべきで、リスクリワードを1:3で設定します。
損切り注文は、平均より狭くするか、より幅広い水準に置くことで、群衆から離れて平均的トレーダーに加わらないようにします。
リスクマネージメントをしっかりし、何が自分にとって「グレードAのトレード」なのかが分かってなければなりません。
第11章 トレードの適切な記録管理
【第11章の小見出し】
- 57. あなたに課せられた毎日の宿題
- 58. トレード計画の作成と評点
- 59. トレード日誌ートレードの成果を測る
トレードの記録をきちんと整理することは、規律を導入・維持するための最高のツールです。
朝の決まった手順を用意しておくことが得策で、毎朝トレードするため準備ができているかどうかを客観的に評価する自己診断テストを実施することを進めています。
トレード後には、トレード日誌をつけることを勧めており3つのメリットを挙げています。
- トレードを頭の中できちんと整理すること
- トレードを終了してから1〜2ヶ月に、終了したトレードの復習を通じて学べること
- 数十回にわたり蓄積したトレードをマーケット・トレード戦略・手仕舞いの戦術などで分類し、それに対応する個別の累積損益曲線の推移から学べること
『ザ・トレーディング』を読んで今後勉強すべきこと

取引におけるメンタル面の強化について、もっと勉強するべきだと『ザ・トレーディング』を読んで思いました。
メンタル面の強化には、投資の本以外を活用できるのではないかと思い、相場心理学についても深く学ばなければなりません。
これに関する名著として、『ゾーン「勝つ」相場心理学入門』がありますので、読んでみます。
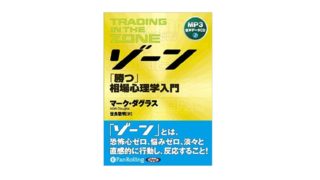
また、投資家にもおすすめであると紹介されていた『賭けの考え方』という本を読んでみようと思いました。

まとめ
『ザ・トレーディング』を書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんがご紹介させていただきました。
投資をしていくためには、まだまだトレーニングが必要ではありますが、少しずつ実践していこうと思います。
より優れた投資家になるために、色々な本を読んでみたいと思います。