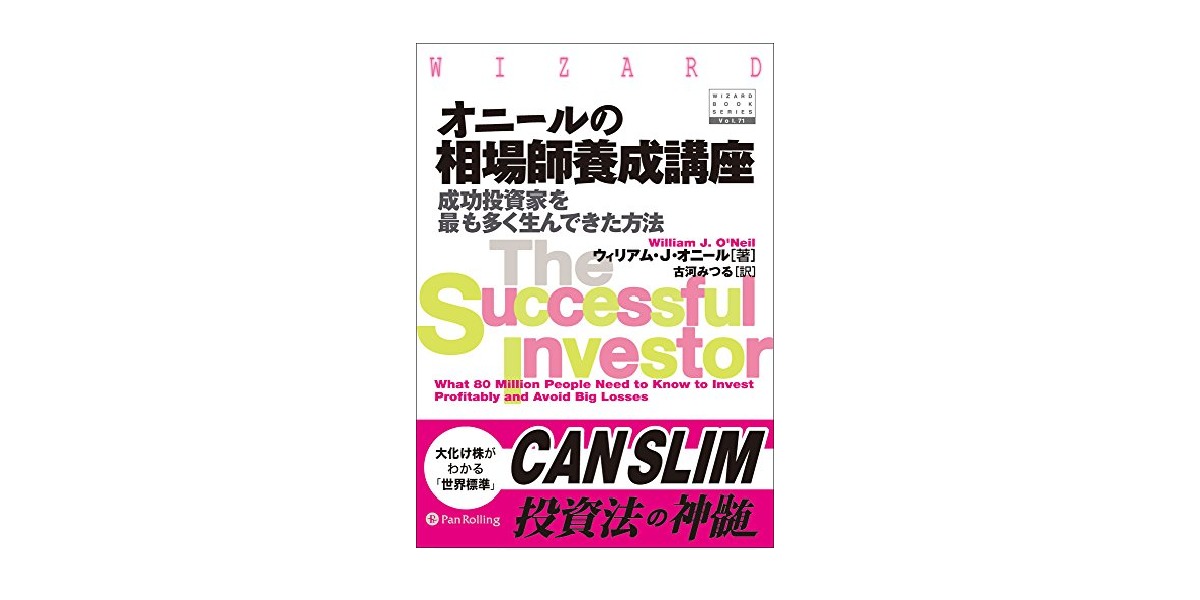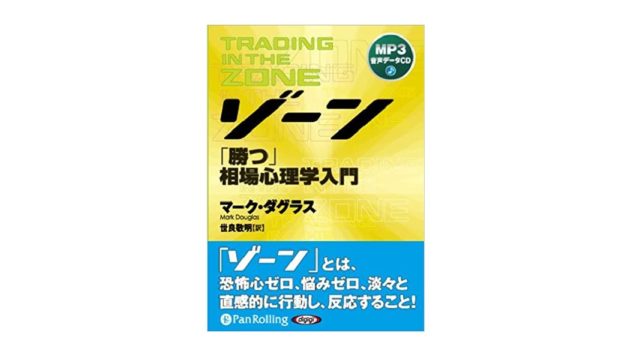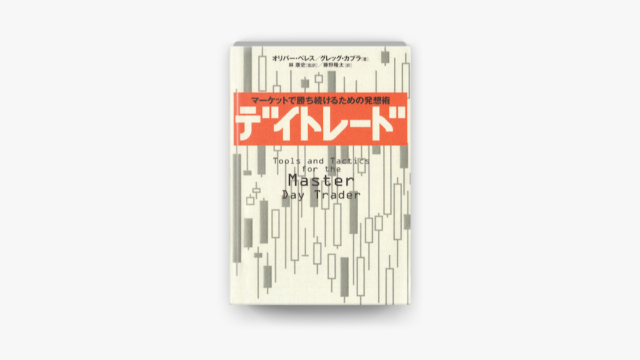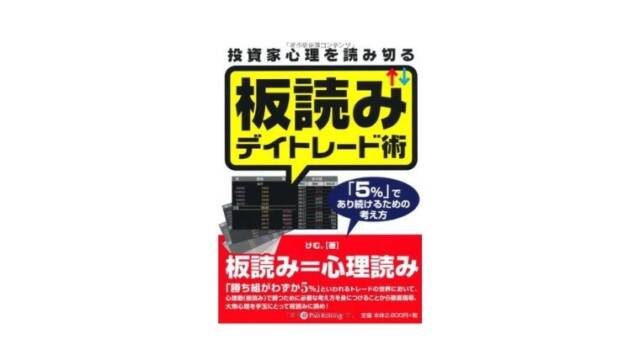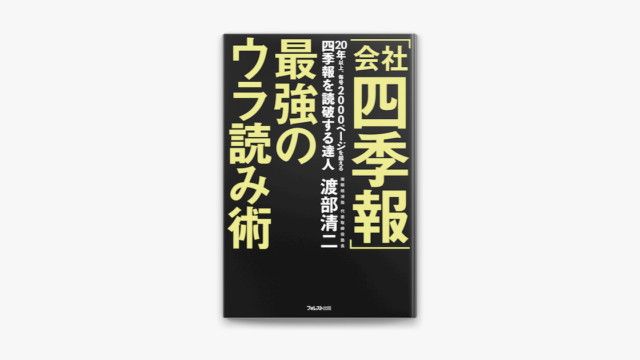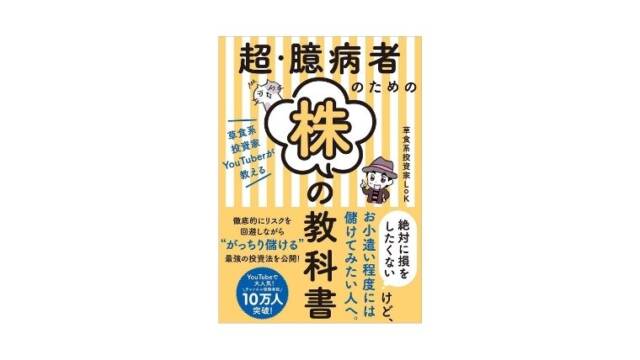投資の勉強をするために、たくさんの本を読んで勉強しています。
『オニールの相場師養成講座』を読んでいるだけでは記憶になかなか残りにくいため、インプットした知識を整理して、
- 「読んで勉強になったこと」
- 「理解が及ばず、さらに勉強をしなくてはいけないこと」
を感じたままに書き留めています。
とても勉強になりましたので、書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんがご紹介いたします。
目次
『オニールの相場師養成講座』とは?
| 読みやすさ | |
|---|---|
| 専門性 | |
| 役立ち度 |
- 著者:ウィリアム・J. オニール (著)・古河みつる(訳)
- 出版社:パンローリング
- 発売日:2004/4/20
- ページ数:240ページ
【目次】
- ステップ1 市場全体の方向性を見きわめる方法
- ステップ2 利益と損失を3対1に想定する方法
- ステップ3 最高の銘柄を最適なタイミングで買う方法
- ステップ4 利益を確定する最適なタイミングで売る方法
- ステップ5 ポートフォリオ管理―損を抑えて利益を伸ばす方法
- 付録A CAN SLIMによる成長株発掘法
- 付録B CAN SLIMのすべて
- 付録C マーケットメモ
- 付録D “ザ・サクセスフル・インベスター” たちの声
- 付録E ベア相場には気をつけろ!
著者のウィルアム・J・オニールは、『オニールの成長株発掘法』でグロース株投資で有名な投資家です。
『オニールの相場師養成講座』の原著は、『The Successful Investor』です。
自立した投資家たちがどうすれば市場に逆らわず、市場に沿って行動し、感情・恐怖・強欲心に従うのではなく、地に足の着いた経験に裏付けられたルールに従って利益を増やすことができるかを説明されています。
グロース株の投資手法として、『オニールの成長株発掘法』でも取り上げられたCANSLIMという買い手法も理解することができます。
『オニールの相場師養成講座』を読むきっかけ

グロース株を勉強するにあたり、オニールが提唱するCANSLIMを避けることはできません。
CANSLIMを学ぶ方法として、『オニールの成長株発掘法』を読む方法がありますが、この本以外にもオニール氏が様々な本を出版していることを知りました。
『オニールの成長株発掘法』で銘柄選定をし、『オニールの相場師養成講座』でトレード方法を学べます。
有名な『オニールの成長株発掘法』以外の本も読み、オニール氏の投資法についての理解、グロース株への理解を深めたいと思いました。
『オニールの相場師養成講座』を読んで勉強になったこと

『オニールの相場師養成講座』では、CANSLIM以外にも
- 最高の銘柄だけを最適なタイミングでだけ購入する
- 上下への大きな値動きを示唆するチャートを見極める
- 売り時を心得る
- リターンを最大化するようにポートフォリオを管理する
を学ぶことができます。
章ごとにまとめさせていただきます。
ステップ1 市場全体の方向性を見きわめる方法
なぜ市場全体の方向性を見極めなければならないかというと、市場全体が天井を付けて下落すると、個別株が素性・勢いに関係なしに下落するからです。
そのためには、毎日の市場平均の値動きだけでなく、毎日の出来高にもっと注目しなければなりません。
どんな上昇トレンドでもいずれ売りが買いを上回るときがやってくる。それは「ディストリビューション」と呼ばれ、それが起こっているのを見きわめられることが大事だ。
引用:オニールの相場師養成講座,p.30 3〜6項
ディストリビューションを見極め、下降トレンドの始まりを知るのに大事なのことは、売買比率の変化を知ることであり、2つの方法が挙げられています。
- 2〜4週間の間に出来高ディストリビューションが3〜5回
- 前日と同等の出来高を伴って数ポイントしか上昇しない「ストーリング(失速)」
ベア相場は寄り付きで上げ、大引けで下げることがよくあり、ブル相場では逆に寄り付きで下げ、大引けで上がることがあります。
また、安値の非優良の出遅れ銘柄が出来高リストの上位を占めていたら、それは市場全体が軟化するシグナルです。
上昇トレンドの相場では、ほとんどの場合、価格と出来高が連続的に上昇している。それは、市場が売りよりも買いが優勢な「アキュムレーション」状態にあることを示している。
引用:オニールの相場師養成講座,p.29 20〜23項
トレンドが下げから上げに転じたと一般的に確信できるのは、反発が4日続いた場合です。
反発の確認(フォロースルー)は、反発局面の4〜7日に現れ、前日よりも多い出来高を伴って、約1.7%以上の強い上昇をする日をもって判断します。
ステップ2 利益と損失を3対1に想定する方法
ほかの銘柄の2〜3倍以上値上がりするような主導株でも、ピークに達した後は平均72%下落します。
また、ブル相場における主導株で、次回以降のブル相場においても主導株になった銘柄は8つに1つだけです。
そのため、損切りをする現実的なルールが必要になります。
保有株の株価が買値から20〜25%まで上がったところで利確・7〜8%まで下がったところで損切りをする「3対1の利益対損失比率」でトレードをすることです。
相場状況によっては%を変えても良いが、3対1のバランスだけは変えないようにアドバイスしています。
この戦略を後押しする形として、偉大な投資家ジェシー・リバモアの名言「人は恐れなければならないときに願い、願わなければならないときに恐れる」も説明に添えられています。
ステップ3 最高の銘柄を最適なタイミングで買う方法
最高の銘柄を選択するための12の法則が説明されています。
- 直近四半期における1株当たり利益が前年同期より少なくとも25%増、できればそれ以上増えていること
- 利益の伸びが、以前の伸び率と比較して、最近の各四半期の特定の時点で伸びが加速していること
- 過去3年間の年間利益が年率25%以上で増えていること
- 最近の1つ以上の四半期における売上が25%以上増えているか、直近3四半期における伸び率が少なくとも加速していること
- 直近四半期における税引き後利益率が新記録か少なくとも新記録に近く、その企業が属する業界で最高水準にあること
- 資本利益率が15〜17%以上であること
- ハイテク企業はキャッシュフロー1株当たり利益が通常の利益よりも大きいこと
- 通常のブル相場では、1株当たり利益とレラティブストレングスの両レーティングがほとんどの場合90以上であること
- その銘柄が属する産業グループが、IBD紙が追跡している197の産業グループのなかで上位10位か、20位以内にランクされていること
- その銘柄がミューチュアルファンド、銀行、保険会社などの機関によって保有されていて、組み入れられているミューチュアルファンドの数が数四半期にわたって四半期ごとに増えていること
- 企業が自社株を買い戻している場合ー望ましくは5〜10%以上ーそれは一般的にプラス材料である
- どんな銘柄でも、その企業の実態が本当に確認できている銘柄を買うこと
また、チャートでは日足・週足で出来高を追っており、5つのチャートパターンを見つけることを勧めています。
- カップウィズハンドル
- ソーサー
- ダブルボトム
- フラットベース
- 上昇ベース
出来高にも注目して、ディストリビューションにさらされていない銘柄は、平均以上の出来高を伴いながら下落する週よりも上昇する週の方多いことにも注目します。
ステップ4 利益を確定する最適なタイミングで売る方法
2倍や3倍になる株は、1〜3週間で20%以上急騰するため、買ったばかりにこうなるとステップ2のルールを除外し、長期保有する例外扱いをし、利益を伸ばします。
そのときに、どのタイミングで手仕舞うかというと、大物主導株の5つに4つは「クライマックスストップ」を付け、これを利用します。
クライマックスストップでは、何ヶ月も上げ続けていた主導株が突然地を離れ、それまでのあらゆる週よりもはるかに早いテンポで急騰し始める。
引用:オニールの相場師養成講座,p.124 7〜9項
クライマックスストップをつけた株にみんなが群がるので、バブルが弾ける前兆・天井を把握します。
また、「チャネルライン」も利用し上抜けたら売る、ベースから4回上放れしたら売るという戦略を取るなど、テクニカルな手法もまとめられています。
ステップ5 ポートフォリオ管理―損を抑えて利益を伸ばす方法
リスクヘッジとして銘柄分散・資産分散をするのは、知識不足に対するヘッジにしかならず、ダメな行動です。
ポートフォリオ内の銘柄数を厳密に制限することを勧めています。
また、保有すべきポジションの半分だけ最初に買い、20〜25%上がる兆しを、2〜3%の上昇を確認してからもう半分を買い増しする戦術も取り上げています。
逆にナンピン買い下がりは絶対にしてはいけないように記載されており、低位株投資も否定し20ドル未満の株を買わないなど、値段が低いのはそれなりの理由があるだとしています。
空売りについても言及されており、買うようも複雑で難しく、下値支持線を割ってからでは遅すぎます。
3〜4週目の10〜20%以上の反発が下げに転じ、10週移動平均価格線を割り込んで出来高が増えた日に空売りをしなければならないとしています。
着実に成長する企業は、配当を出さない企業への投資を勧めています。
付録ーCANSLIM
付録には、CAN SLIMについて記載されています。
- C = Current earnings:当期利益
- A = Annual earnings:通年利益
- N = New product or service:新製品・新サービス
- S = Supply and demand:需給関係
- L = Leader or laggard?:主導株か出遅れ株か
- I = Institutional sponsorship:機関投資家の好み
- M = Market:相場全体の地合い
C:当期利益=EPSは高い方が良い
- 今期のEPS成長率は前年同期比で大幅に増加している(最低でも18%から20%)
- 企業の1回限りの特別利益は無視する
- 四半期利益の伸びが加速している銘柄を探す
- 四半期売上の伸びが25%、または少なくとも過去3四半期利益の強い伸びを示しているほかの銘柄が少なくとも1つ存在する
A 通年の利益=年間EPSが急成長している方が良い
- EPSの年間福利成長率が最低25%
- 過去3年間のEPSの伸びが毎年著しいこと
- 翌年の収益に関するコンセンサス予想が当年より高くなければならない
- 株価資本収益率が17%以上
- 年間1株当たりキャッシュフローが実際の1株当たり利益よりも少なくとも20%大きい銘柄を探す
- 収益が過去3年間にわたって安定していなければならない
N 新製品・新サービス・新高値:利益成長の原動力であること
- 強力な新製品・新サービスが登場した
- 経営陣の大きな交代
- 業界で良い変化があった
- 揉み合いを経た後、新高値またはそれに近い値をつけている
S 需要と供給:発呼済み株式数と大量の需要
- 株式数の少ない株の方が上昇力があるが、下落するときもそれだけ速い
- トップの経営陣が大きな割合を所有している銘柄は一般的に有望
- 公開市場で自社株を買っている企業を探す
- 負債比率が低い企業と過去数年間に負債比率が下がっている企業を探す
L 先導株・出遅れ株
- 強い産業グループ内のトップ2・3銘柄から選んで買う
- レラティブプライスストレングスを使って先行株と出遅れ株を区別するーレラティブストレングスランキングが70%未満の銘柄は出遅れており、避けるべき
- レラティブストレング力スランキングが80%以上でチャートパターンがベースにある銘柄を探す
- 相場の調整時は平均パフォーマンスよりも弱い銘柄は買わない
I 機関投資家の好み
- 複数の機関投資家によって保有されている銘柄を探す。最低10機関
- 保有車の質を見るー少なくとも1人か2人の有能なポートフォリオマネージャーが保有している銘柄を見つける
- 保有者数が減っているのではなく、増えている銘柄を探す
- 保有されすぎている銘柄は避ける
M 相場の地合い
- トレンドに逆らっても勝てないので、相場がブルかベアかを見極める
- 毎日、市場全体の平均の動向を追跡し、理解する
- 相場が天井をつけ、大転換を始めたときは25%を現金化するように努める
- 大した値上がりがないのに出来高が大きく増えたら天井の兆しの可能性があるが、最初の下落時は出来高が少ない可能性がある
- 相場の強さをヒントとして主導株を追跡する
- より弱い、狭い相場の動きへの主要な転換点における、主要平均と指数の差を見る
- センチメント指数は、大きな心理的転換点を見極めるのに役立つ
- 公定歩合の変化は、相場の動きの確認として注目しておく価値のある指標
『オニールの相場師養成講座』を読んで今後勉強すべきこと

『オニールの相場師養成講座』では、天井・反発の確認に「出来高」を利用しています。
そのため、出来高分析に視点をおいた投資方法の勉強をしたいと思いました。
出来高分析については、本書と同じパンローリングから『出来高・価格分析の完全ガイド』という専門書籍が出ていますので、そちらで勉強したいと思います。

また、CANSLIMについて本書で取り上げられていますが、より詳しく記載されている『オニールの成長株発掘法』を読んでみます。
まとめ
『オニールの相場師養成講座』を書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんがご紹介させていただきました。
投資をしていくためには、まだまだトレーニングが必要ではありますが、少しずつ実践していこうと思います。
より優れた投資家になるために、色々な本を読んでみたいと思います。