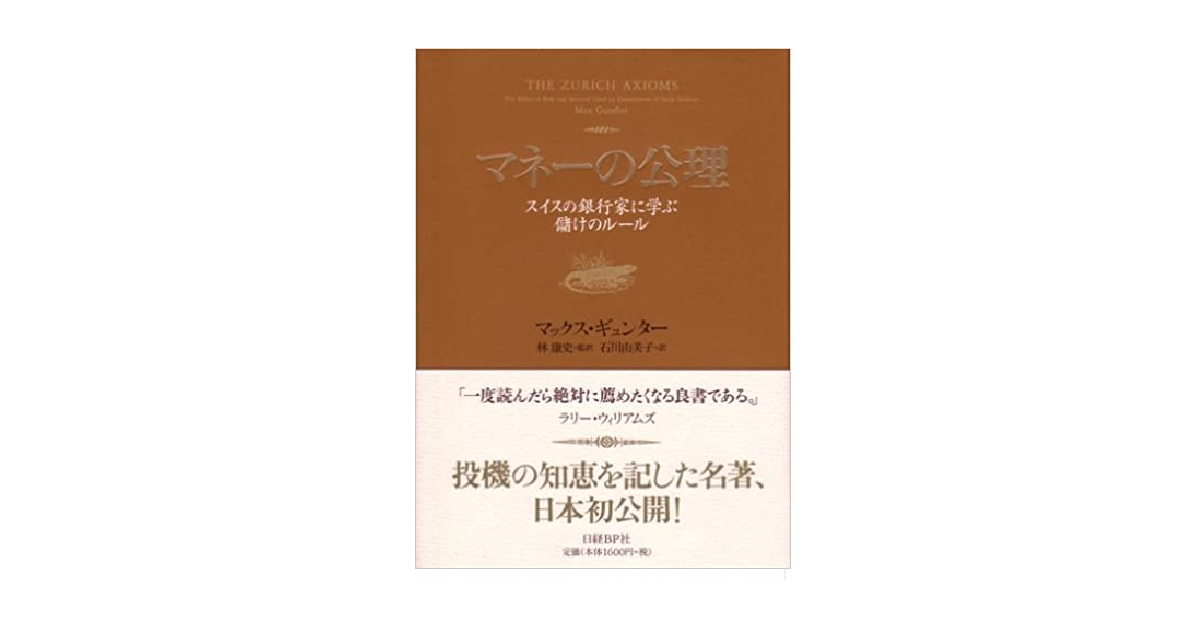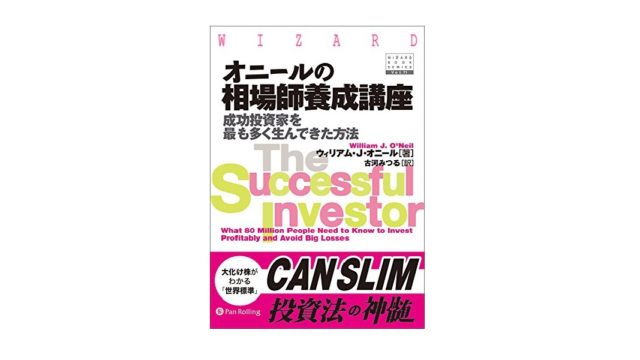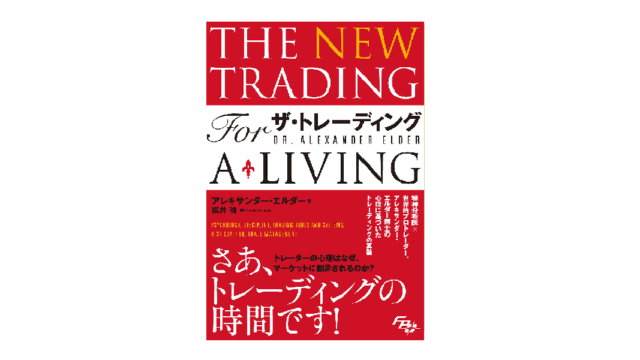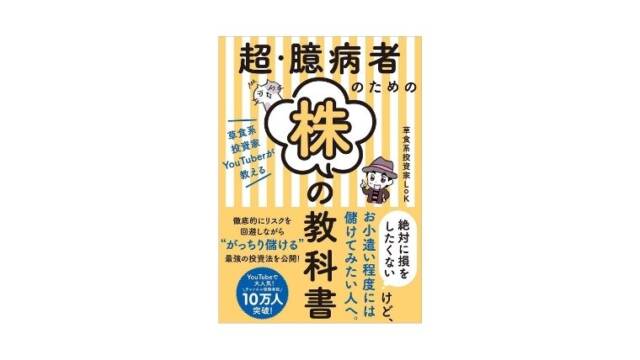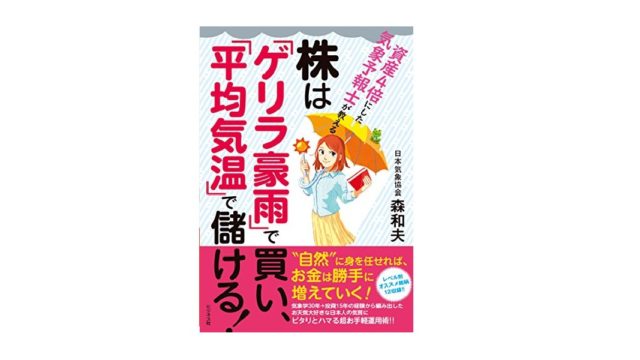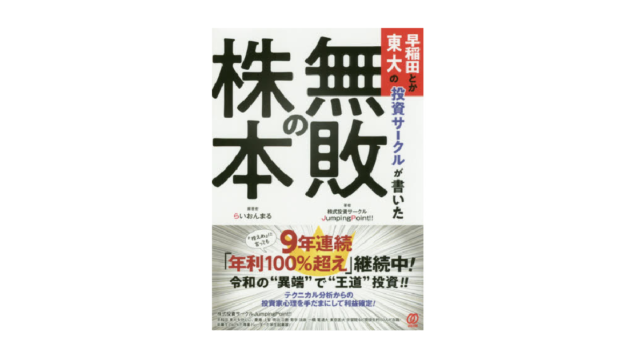投資の勉強をするために、たくさんの本を読んで勉強しています。
『マネーの公理』を読んでいるだけでは記憶になかなか残りにくいため、インプットした知識を整理して、
- 「読んで勉強になったこと」
- 「理解が及ばず、さらに勉強をしなくてはいけないこと」
を感じたままに書き留めています。
とても勉強になりましたので、書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんがご紹介いたします。
目次
『マネーの公理』とは?
| 読みやすさ | |
|---|---|
| 専門性 | |
| 役立ち度 |
- 著者:マックス・ギュンター (著)・林 康史 (翻訳)・石川 由美子 (翻訳)
- 出版社:日経BP
- 発売日:2005/12/22
- ページ数:256ページ
【目次】
- はじめに:公理とは何か、どこからきたのか
- 第一の公理:リスクについて
- 第二の公理:強欲について
- 第三の公理:希望について
- 第四の公理:予測について
- 第五の公理:パターンについて
- 第六の公理:機動力について
- 第七の公理:直観について
- 第八の公理:宗教とオカルトについて
- 第九の公理:楽観と悲観について
- 第十の公理:常識について
- 第十一の公理:執着について
- 第十二の公理:計画について
- 監訳者あとがき
『マネーの公理』は、英国で1976年に出版され、ウォール街で密かにロングセラーになっていた「The Zurich Axiims」の日本語版です。
株式市場・商品取引に参加したスイス投機家たちのクラブが用いた「チューリッヒの公理」を初めて明文化されました。
具体的な方法ではなく、姿勢・心情などの方針が学べます。
正しいリスクの取り方を身につけ、資産を積みあげていくための「投機」の叡智を凝縮した1冊です。
『マネーの公理』を読むきっかけ

『マネーの公理』は、優良古典として有名な投資家がよくおすすめの1冊として挙げています。
「ラリー・ウィリアムズの相場で儲ける法」で知られているラリー・ウィリアムズ氏が、「一度読んだら絶対に薦めたくなる」と絶賛しています。
投資ではなく「投機」と銘されておりますが、株式投資・FXなどの投資家がこぞってこの本を読んでいるため、気になり読んでみました。
『マネーの公理』を読んで勉強になったこと

「チューリッヒの公理」は、12の公理と16の副公理で構成されています。
- 第一の公理:リスクについて「心配は病気ではなく、健康の証である。もし、心配なことがないなら、十分なリスクをとっていないということだ」
・副公理Ⅰ:いつも意味のある勝負に出ること
・副公理Ⅱ:分散投資の誘惑に負けないこと - 第二の公理:強欲について「常に、早すぎるほど早く利食え」
・副公理Ⅲ:あらかじめ、投機からどれだけの利益がほしいのかを決めておけ。そして、それを手に入れたら、投機から手を引くのだ。 - 第三の公理:希望について「船が沈みはじめたら、祈るな。飛び込め。」
・副公理Ⅳ:小さな損失は、人生の現実として甘んじて受けよ。大きな利益を待つ間には、何回かそういう経験をすると考えろ。 - 第四の公理:予測について「人間の行動は予測できない。誰であれ、未来がわかると言う人を、たとえわずかでも信じてはいけない。
- 第五の公理:パターンについて「カオスは、それが整然と見え始めない限り、危険ではない」
・副公理Ⅴ:歴史家の罠に気をつけろ
・副公理Ⅵ:チャーティストの幻想に気をつけろ
・副公理Ⅶ:相関と因果関係の妄想に気をつけろ
・副公理Ⅷ:ギャンブラーの誤謬に気をつけろ - 第六の公理:機動力について「根を下ろしてはいけない。それは、動きを鈍らせる。」
・副公理Ⅸ:忠誠心やノスタルジーといった感情のせいで、下落相場に捕まってはいけない。
・副公理Ⅹ:より魅力的なものが見えたら、直ちに投資を中断しなければならない。 - 第七の公理:直観について「直観は、説明できるのであれば信頼できる」
・副公理XI:直観と希望を混同するな - 第八の公理:宗教とオカルトについて「宇宙に関する神の計画には、あなたを金持ちにすることは含まれていないようだ」
・副公理XII:もし、占星術が当たるのであれば、すべての占星術師は金持ちであろう
・副公理XIII:迷信は、追い払う必要はない。もし、適当な場所に置いておけば楽しめる。 - 第九の公理:楽観と悲観について「楽観は、最高を期待することを意味するが、自信は、最悪の場合にどのように対処するか知っていることを意味する。ただ単に楽観的というだけで行動してはならない。」
- 第十の公理:コンセンサスについて「大多数派の意見は無視しろ。それはおそらく間違っている。」
・副公理XIV:投機的流行を決して追うな。往々にして、何かを買う最高のときは、誰もそれを望まないときである。 - 第十一の公理:執着について「もし最初にうまくいかなければ、忘れろ」
・副公理XV 難平買いで悪い投資を何とかしようとするな - 第十二の公理:計画について「長期計画は、将来を管理できるという危険な確信を引き起こす。決して重きを置かないことが重要だ。」
・副公理XVI 長期投資を避けよ
第一の公理:リスクについて
第一の公理はリスクについて、「心配は病気ではなく、健康の証である。もし、心配なことがないなら、十分なリスクをとっていないということだ」と記載されています。
一般的な投資に関する本では、「投資は余剰資金で実施すること」「負けても良い金額を賭けること」と説明されることがほとんどです。
しかし、『マネーの公理』では、リスクをとって勝負に出る投機をすることを勧めています。
冷たい真実がここにある。裕福な親戚がいない限り、大多数を占める貧乏人クラスから這い上がる唯一の希望はーリスクをとることである。
引用:マネーの公理 p24 9〜10項
- リスクをとって心配して金持ちを目指すのか
- 安心安全をとって一生貧乏なままなのか
どちらかを選べと言われたら、リスクをとるべきだと本書は示しています。
ただリスクをとり無鉄砲になるのではなく、副公理Ⅰ「いつも意味のある勝負に出ること」が肝心です。
意味のある勝負が複数ある状態はおかしいことから、副公理Ⅱ「分散投資の誘惑に負けないこと」が導かれます。
「すべての卵を一つのカゴに盛るな」ではなく、「すべての卵は一つのカゴに入れろ、そしてカゴを見守れ」ということです。
第二の公理:強欲について
第二の公理は強欲について、「常に、早すぎるほど早く利食え」と記載されています。
欲望を抑えて、「ブームがピークに達するのを待たない」「幸運を引き伸ばさない」ことを実践するため、早く利食うことを勧めています。
そのため、副公理Ⅲ「あらかじめ、投機からどれだけの利益がほしいのかを決めておけ。そして、それを手に入れたら、投機から手を引くのだ。」が重要になります。
「十分とはいくらか?」の答えを明確にして、利確ラインをあらかじめしっかり決めて順守して、投資しなければなりません。
第三の公理:希望について
第三の公理は希望について、「船が沈みはじめたら、祈るな。飛び込め。」と記載されています。
第二の公理は利食いの話でしたが、第三の公理は損切りです。
問題が発生した場合、期待・祈りなどの希望にすがることなく、すぐに立ち去らなければならず、絶対に必要な投機技術です。
「船が沈み始めたら」が肝心で、船が沈んでからではなく、手遅れになる前に行動する素早さが要です。
しかし、これを阻む3つの障害があります。
- 後悔の恐怖にかられる
- 投資の一部を断念しなければならない
- 間違いを認めたがらない
この3つの障壁に立ち向かうために「副公理Ⅳ:小さな損失は、人生の現実として甘んじて受けよ。大きな利益を待つ間には、何回かそういう経験をすると考えろ。」があります。
小さな損失に慣れるための訓練をしなければならないことを教えてくれます。
第四の公理:予測について
第四の公理は予測について、「人間の行動は予測できない。誰であれ、未来がわかると言う人を、たとえわずかでも信じてはいけない。と記載しています。
専門家・エコノミストなどの予測を信じて投機を行ってはいけません。
「SNSなどで〇〇さんが買いだと言っていた」「投資雑誌にそろそろ天井だと予測だと書いてあった」などに翻弄されるのは馬鹿げています。
予測が可能で信頼できるのは、自然現象が対象だからである。しかし、チューリッヒの公理は、お金の世界を対象にしており、人間模様についてのものである。人間模様は、どんな方法でも、誰にも、絶対に予測できない。
引用:マネの公理 p99 11〜13項
金融指標を自然現象のように扱って、予測に従ってはいけないことを教えてくれます。
第五の公理:パターンについて
第五の公理はパターンについて、「カオスは、それが整然と見え始めない限り、危険ではない」と記載されています。
お金の世界にはパターンがなく、無秩序で混沌としています。
秩序が存在しないところに秩序を見つけてはならず、カオスに取り組んでいることを意識しなければなりません。
そのため以下の副公理を理解しなればなりません。
- 副公理Ⅴ:歴史家の罠に気をつけろ:歴史が繰り返すというのは全く根拠がない。
- 副公理Ⅵ:チャーティストの幻想に気をつけろ:トレンドライン・レンジラインなどのチャートの線が秩序があるように見えるが、実際よりも大袈裟で危険である。
- 副公理Ⅶ:相関と因果関係の妄想に気をつけろ:出来事を関連づけることは容易ではなく、偶然の結果をでっちあげてしまっている。
- 副公理Ⅷ:ギャンブラーの誤謬に気をつけろ:「今日はついている」と自分自身を陶酔させてはいけない。
第六の公理:機動力について
第六の公理は機動力について、「根を下ろしてはいけない。それは、動きを鈍らせる。」と記載されています。
根を下ろすとは、恒常化する・常態化することを指します。
「副公理Ⅸ:忠誠心やノスタルジーといった感情のせいで、下落相場に捕まってはいけない。」では人・物・思い出に根を下ろすことで失敗してしまうことを示しています。
「副公理Ⅹ:より魅力的なものが見えたら、直ちに投資を中断しなければならない。」では、投機先に根を下ろすことで失敗してしまうことを示しています。
常に身軽に動ける状態であるからこそ、問題から抜け出したり、チャンスを掴んだりができます。
第七の公理:直観について
第七の公理が直観について、「直観は、説明できるのであれば信頼できる」と記載されています。
直感を軽視してはいけないし、盲信してしまうのもよくないが、慎重に対処すれば有効なツールになります。
直感は、全く当てにならない場合もあれば、無意識のレベルで蓄積されたデータが勝手に関係づけを実施した結果である場合もあります。
直感が役に立つ可能性があるので、識別し仕分けするために、直感を生み出すほど巨大なデータが自分の中にあるか自問する必要があります。
しかし、自分の感覚ではバイアスがかかってしまうため、「副公理XI:直観と希望を混同するな」がでてきます。
自分が起こって欲しいことが起こる直感は希望である場合があり懐疑的である必要があり、自分が望まない結果を示唆する直感は信頼に値します。
第八の公理:宗教とオカルトについて
第八の公理は宗教とオカルトについて、「宇宙に関する神の計画には、あなたを金持ちにすることは含まれていないようだ」と記載されています。
お金と超自然現象が組み合わさると突然うまくいかなくなると表現されています。
「副公理XII:もし、占星術が当たるのであれば、すべての占星術師は金持ちであろう」と、オカルトについてぶった切っています。
しかし、「副公理XIII:迷信は、追い払う必要はない。もし、適当な場所に置いておけば楽しめる。」として、迷信の1つや2つを信じていても良いと言います。
ですが、頼れるのは自分1人だと覚悟しなければなりません。
第九の公理:楽観と悲観について
第九の公理は楽観と悲観について、「楽観は、最高を期待することを意味するが、自信は、最悪の場合にどのように対処するか知っていることを意味する。ただ単に楽観的というだけで行動してはならない。」と記載されています。
投資をする際には、楽観の代わりに、自信を用いなければならない。
楽観主義が悲観主義よりも気分が良いので、判断を誤ってしまう一面もあります。
第十の公理:コンセンサスについて
第十の公理は常識について、「多数派の意見は無視しろ。それはおそらく間違っている。」と記載されています。
大多数が常に間違っているわけではないが、「安い時に買い・高い時に売る」必要があると、「副公理XIV:投機的流行を決して追うな。往々にして、何かを買う最高のときは、誰もそれを望まないときである。」で示しています。
相場の格言で、「人の行く裏に道あり花の山」という言葉があり、「人が売るときに買い、人が買うときには売れ」ということです。
第十一の公理:執着について
第十一の公理は執着について、「もし最初にうまくいかなければ、忘れろ」と記載されています。
銘柄・トレード手法などを試して失敗した時、それに固執することなく、修正していく必要があります。
そのため、「副公理XV:難平買いで悪い投資を何とかしようとするな」ということで、損が出た場合に固執することを注意しています。
第十二の公理:計画について
第十二の公理は計画について、「長期計画は、将来を管理できるという危険な確信を引き起こす。決して重きを置かないことが重要だ。」と記載されています。
カオスに立ち向かっている中、目先のことですら分からないのに、長期のことなど分かるわけがないです。
そのため、「副公理XVI:長期投資を避けよ」と記載されています。
『マネーの公理』を読んで今後勉強すべきこと

『マネーの公理』を読んで、チャート分析などの勉強などよりも心構えが足りないなと思いました。
相場心理学などを学んでいくために「ザ・トレーディング」という本を読みます。
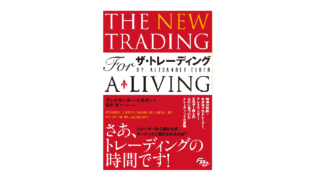
また、本書を推薦しているラリー・ウィリアムズの「ラリー・ウィリアムズの相場で儲ける法」を読んでみたいと思いました。
まとめ
『マネーの公理』を書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんがご紹介させていただきました。
投資をしていくためには、まだまだトレーニングが必要ではありますが、少しずつ実践していこうと思います。
より優れた投資家、いえ投機家になるために、色々な本を読んでみたいと思います。