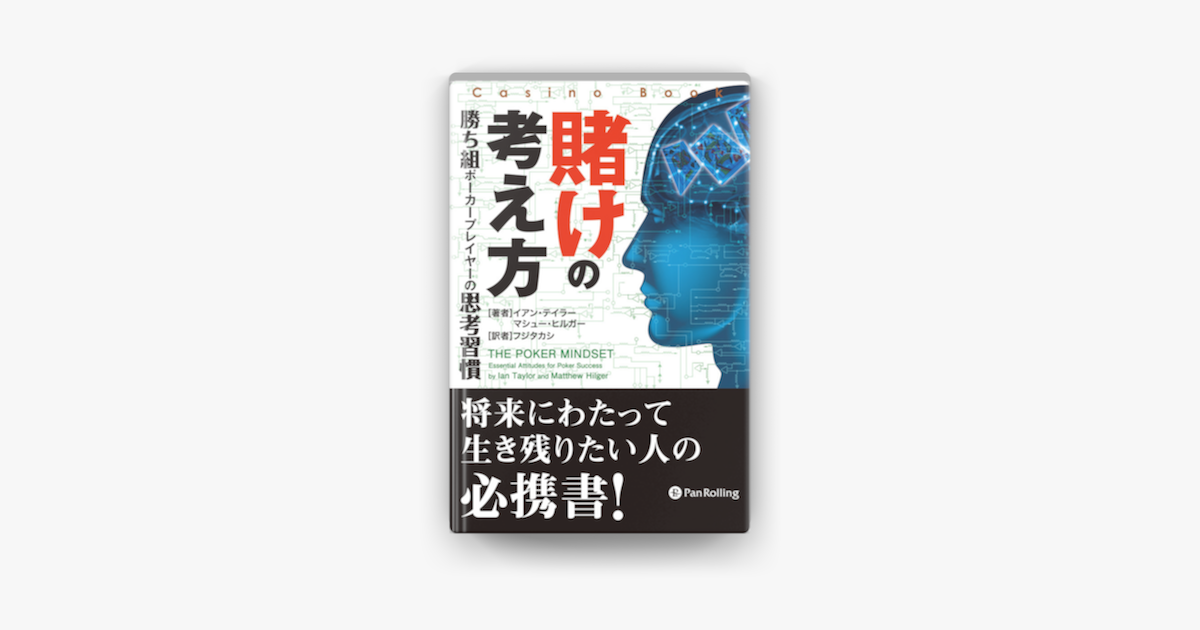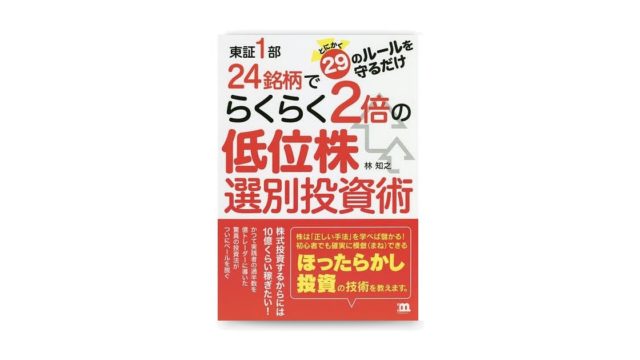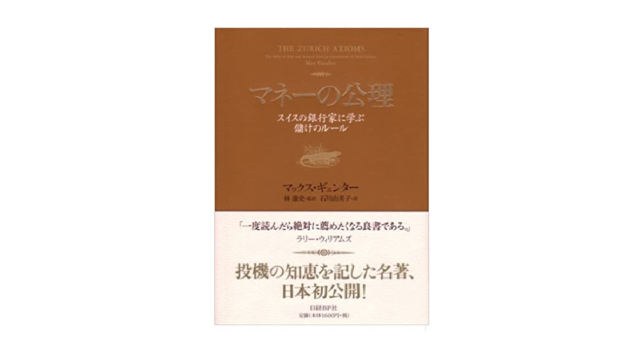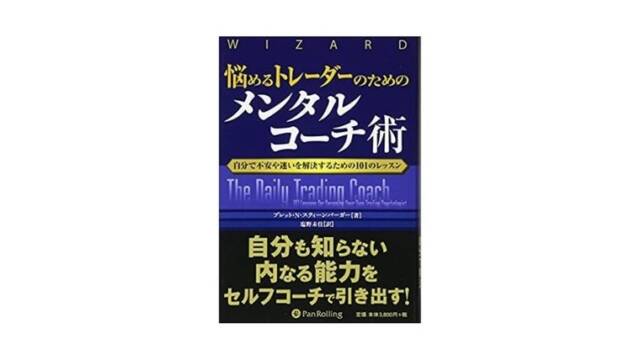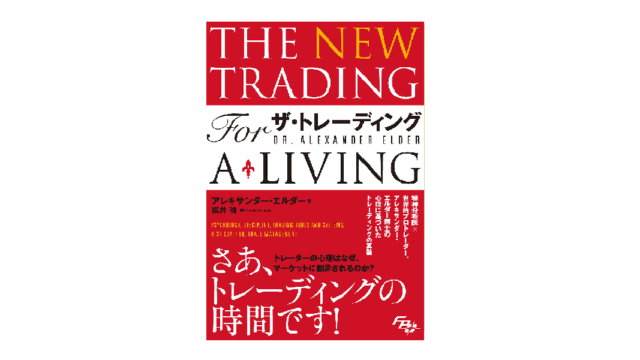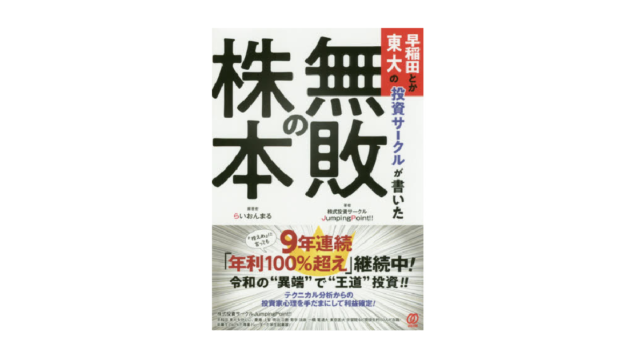投資の勉強をするために、たくさんの本を読んで勉強しています。
『賭けの考え方』を読んでいるだけでは記憶になかなか残りにくいため、インプットした知識を整理して、
- 「読んで勉強になったこと」
- 「理解が及ばず、さらに勉強をしなくてはいけないこと」
を感じたままに書き留めています。
とても勉強になりましたので、書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんがご紹介いたします。
目次
『賭けの考え方』とは?
| 読みやすさ | |
|---|---|
| 専門性 | |
| 役立ち度 |
- 著者:
- 出版社:パンローリング
- 発売日:2011/8/12
- ページ数:413ページ
【目次】
- 第1章:はじめに
- 第2章:賭けの考え方―プレイヤーとして成功するために必要なポーカーの思考習慣
- 第3章:本能を乗り越える―あなたの本能と人生経験はポーカーでは役に立たない?
- 第4章:バッドビートとビッグポットを逃すこと―ビッグポットを逃すことやバッドビートの対処法
- 第5章:ダウンスイング―ダウンスイングとは何か。その対処法と避けるべき落とし穴
- 第6章:ティルト―ティルトを見分け、コントロールし、タイプ別に予防する
- 第7章:バンクロール管理―心理学的見地からのバンクロールの考察
- 第8章:対戦相手の心の中へ―対戦相手の傾向や動機、思考レベルを評価す
- 第9章:応用編―ポーカー心理学に関する上級編
- 第10章:ポーカーと人生―ポーカーとその他の人生との融合
『賭けの考え方』は、勝ち組プレイヤーの思考習慣にフォーカスを当てた「ポーカーの戦略本」です。
ポーカーは、時として技術ノウハウではなく、心理的技術が結果を大きく左右することもあります。
本書が教えることをしっかり学びさえすれば、ポーカーにとどまらず、あなたの人生にプラスの影響をもたらしてくれます。
株・FX・その他ギャンブルにも応用が効く1冊になります。
『賭けの考え方』を読むきっかけ

投資にとポーカーには共通点があります。
- 相手の情報が分からない不完全情報ゲームである
- リスクを取らないとリターンが得られない
- 運の要素がある
投資の心理的技術を学ぶために、ポーカーを学ぶ人は少なくありません。
『マネーの公理』でも、ポーカーを学ぶべきであると主張されていました。
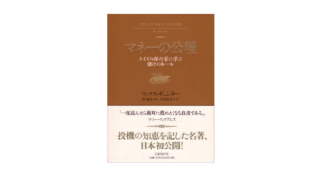
そのため、ポーカーの心理的技術を学ぶために本書を手に取りました。
『賭けの考え方』を読んで勉強になったこと

『賭けの考え方』は、ポーカーの戦略本ながら、ポーカー以外の心構えが学べます。
ポーカーのことをあまり知らなくても理解できるように工夫されていますが、詳細に理解するにはやはりポーカーの知識が必要です。
この本では、
- 勝つための思考法
- ポーカーの直感に関する6つの真実
を学ぶことできます。
本書にて他にも、
- バットビートとビッグポットを逃すこと
- ダウンスイング
- ティルト
- バンクロール管理
- 対戦相手の心の中
などの対策が載っていますが、「勝つための思考法」「ポーカーの直感に関する6つの真実」に帰結します。
ポーカーについて書かれていますが、投資全般について通じる心理戦略です。
投資について置き換えながら、読むとすごい勉強になりました。
勝つための思考法
長期的に勝つためには、以下の考え方を身につける必要があります。
- さまざまな現実を理解し受け入れる
- 長期的視野でプレイする
- 金を儲けることよりも正しい決断を下すことを優先させる
- 金への執着を捨てる
- 自尊心を持ち込まない
- あらゆる感情を決断から排除する
- 分析と改善のサイクルを継続的に繰り返す
①さまざまな現実を理解し受け入れる
不完全情報であるゲームに参加しているため、5つの現実を受け入れないといけません。
- Ⅰポーカーは技術と運が共存するゲームである
- Ⅱ短期的には運が物を言う
- Ⅲ長期的には実力が物を言う
- Ⅳポーカーは利幅の小さいゲーム
- Ⅴポーカーは分散の大きいゲーム
②長期的視野でプレイする
短期間の結果には運の要素もあるので無視をして、平均的にいちばん儲けることができるハンドに徹しなければなりません。
自分に落ち度がなくても負け続けることもあるので、短期的には負ける可能性があるリスクを受け入れ、長期的に正しい行動に心がけます。
③金を儲けることよりも正しい決断を下すことを優先させる
正しい判断をすることで第1原理であり、結果は気にしません。
正しい行動に、後から結果として金がついてくるだけです。
④金への執着を捨てる
最適ではない判断をしてしまい、勝てる可能性を下げる原因が「金への執着」です。
「怖がっている金では勝てない。」という使い古されたポーカーの決まり文句があります。
大きな損失を単に肩をすぼめて済ませられるような境地に至らなければなりません。
縮こまったプレイを避けるために、金への執着を減らす以下の3つが大事です。
- 経験:賭ける金額に慣れる
- バンクロール:長期的にプレイするために十分な金を確保すること
- 分離:日常に使う金と賭けに使う金を分ける
⑤自尊心を持ち込まない
自尊心が儲けを食い潰してしまいます。
自尊心を抑制しないと以下の落とし穴にはまります。
- コールすべきでないベットをコールする
- 個人的恨みが決断力を鈍らせる
- 取り返そうと躍起になる
- 勝ち目のない勝負を挑む
- 相手にいいところを見せつけようとする
- 必要なのにリミットを下げない
- 相手にうっかり情報を与えてしまう
- 残ってほしいプレイヤーを追い払ってしまう
相手にどう思われているかよりも、ゲーム自体と正しい決断を下すことに集中しなければなりません。
⑥あらゆる感情を決断から排除する
意思決定の過程に感情がいかなる影響を与えてはいけません。
感情のスイッチを完全にオフにすることは不可能だが、防御法が2つあります。
- プレイが悪化する原因となる感情を抱いているときには、プレイするのをやめよう。
- 自分の感情を認めよう。その上で、それが決断に影響を及ばさないようにしよう。
⑦分析と改善のサイクルを継続的に繰り返す
析・研究・学習・改善をし続けるプレイヤーがどこまでも上達することが求められます。
「自己満足・極めたという幻想・情熱の喪失・停滞」が学習への情熱を失わせてしまいます。
学ぶことにひたむきになり、変化への応対力を持たなければなりません。
ポーカーの直感に関する6つの真実
「普段と少し違う考え方をしなければ、最高の結果を得られない」と理解しなければなりません。
それについて6つの局面があり、それを見極める必要があります。
- 作用と反作用
- 目標を設定する
- 「平均」でも問題ないか?
- リスク嫌い
- 欲
- 筋の通らない考え
①作用と反作用
ポーカーにおいて、決断と結果の相関関係は分かりにくいです。
決断によって結果がどうなったかを観察することがとても難しいです。
勝っているからといってプレイが上手いとは限らず、負けているからといってプレイが下手だとは限らない。
引用:賭けの考え方 p75 8〜9項
本能的に、良い結果を出そうと行動を変えたいと思ってしまいます。
短期的結果を基にいちいちプレイに変化を加えていては、巨額の損失を被ることになってしまいます。
短期的には運が結果を左右してしまうので、行動に関する結果を気にする必要がありません。
もしも絶対的関連性を求めるならば、本当に多くの試行の結果を見つめなければいけません。
②目標を設定する
一般的に目標を設定することは良いことである。
しかし、ポーカーにおいて、金銭的な目標であってはならない。
それは以下の理由によります。
- 金銭的目標で達成できる力は限られている
- 金銭的目標を達成できなかった場合に結論を導き出すのは難しい
- 金銭的目標はあなたを本来の目標から遠ざける
そのため、2つの条件を満たす場合においてのみ目標を立てることができます。
- その目標を達成し得る能力があなたにあること
- その目標が、できるだけ頻繁に最善の意思決定を行うという本来の究極の目標と矛盾したり、それを遠ざけたりしないこと
例えばテーブルから離れた目標、1ヶ月にポーカーの本を何冊読む・毎週数時間は復習に時間を作ろうなどが良いです。
③「平均」でも問題ないか?
平均的なポーカープレイヤーであるなら、お金を失ってしまいます。
レーキ・諸経費を計算に入れると、平均以下になってしまいます。
また、平均的プレイヤーと思っていても、思い込みにより実際は平均未満である可能性が高いです。
そのため、平均に達する努力だけでは不十分だということです。
④リスク嫌い
日常生活の時とは違い、ポーカーテーブルではリスクに中立な立場で、リスクを好んでも嫌ってもいけません。
リスクを回避してしまうと
- 必要以上に相手をポットから追い出してしまう。
- しっかりとバリューベットしない。
- 利幅の小さいゲームでプレイする。
というミスを犯してしまいます。
⑤欲
「欲は悪である」という理屈は全て捨て去らなければなりず、むしろ欲は必要な要素です。
ポーカーは利幅の小さなゲームであるため、全てを奪うべきで、後ろめたさを感じる必要はありません。
多くの金を儲けることがポーカーの目的なので、欲という概念自体ポーカーテーブルにはないとも言える。
⑥筋の通らない考え
ポーカーは全ての決断が重要であるので、筋の通らない考えが少しでもあると、その分金を失ってしまいます。
優れたプレイヤーは、以下のような考えを避けています。
- 見当違いの変数を考慮に入れる
- 確率についての誤解
- 結果に基づいた考え
- 見かけ上の回帰
- 正義のために
- 迷信
『賭けの考え方』を読んで今後勉強すべきこと

ポーカーの知識を浅いレベルで知っていましたが、『賭けの考え方』を読むことで心理戦略を学ぶ以外にも、ポーカーの奥深さにも触れることができました。
有名な投資家・投資本などでも、ポーカーをやることで自分のメンタルを鍛えるように勧めていることも少なくありません。
ポーカー自体をプレーすることが少なかったので、ポーカーをやってみようと思いました。
本書のようなポーカーの心理面について記載された書籍も読んでみたいと思います。
また、相場心理学についても深く学ばなければなりません。
これに関する名著として、『ゾーン「勝つ」相場心理学入門』がありますので、読んでみようと思います。
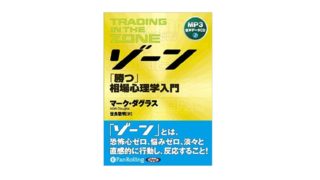
まとめ
『賭けの考え方』を書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんがご紹介させていただきました。
投資をしていくためには、まだまだトレーニングが必要ではありますが、少しずつ実践していこうと思います。
より優れた投資家になるために、色々な本を読んでみたいと思います。