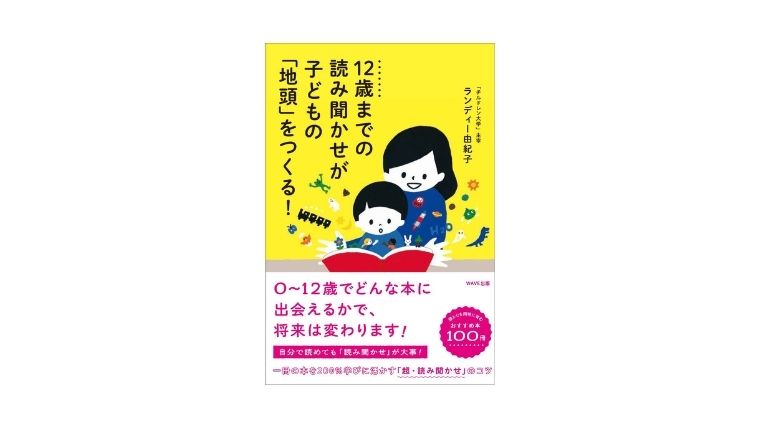子育てをするために、たくさんの本を読んで勉強しています。
『12歳までの読み聞かせが子どもの「地頭」をつくる!』を読んでいるだけでは記憶になかなか残りにくいため、インプットした知識を整理して、
- 「読んで勉強になったこと」
- 「理解が及ばず、さらに勉強をしなくてはいけないこと」
を感じたままに書き留めています。
とても勉強になりましたので、書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんがご紹介いたします。
目次
『12歳までの読み聞かせが子どもの「地頭」をつくる!」の親の言葉』とは?
| 読みやすさ | |
|---|---|
| 専門性 | |
| 役立ち度 |
- 著者:ランディー 由紀子 (著)
- 出版社:WAVE出版
- 発売日:2015/7/1
- ページ数:192ページ
【目次】
- CHAPTER 1 「読み聞かせ」は頭と心を同時に育む究極の英才教育!
- CHAPTER 2 本を120%学びにつなげる「超・読み聞かせ」をやってみよう
- CHAPTER 3 子どもを伸ばす「学び」の仕組み
- CHAPTER 4 親が変われば子どもも変わる
- 読み聞かせお薦め本リスト
『12歳までの読み聞かせが子どもの「地頭」をつくる!」は、0〜12歳の発達に必要な読み聞かせについて学ぶことができます。
一冊の本を200%学びに活かす「超・読み聞かせ」で、「読解力・思考力・判断力・集中力・表現力・共感力・優しさ」の7つの力につきます。
継続した「読み聞かせ」が、学力の土台と「自分で考える力」を養うことができます。
『12歳までの読み聞かせが子どもの「地頭」をつくる!』を読んで勉強になったこと

『12歳までの読み聞かせが子どもの「地頭」をつくる!』では、読み聞かせを通して、自分の頭で考えて行動できる、本当の意味での賢さである「地頭」を育てることに主眼を置いています。
読み聞かせを有効に活用できるかのポイントは「いくつかのシンプルなコツ」と「継続」できるかどうかにかかっています。
本書で重要だと思ったところを章ごとにまとめます。
CHAPTER 1 「読み聞かせ」は頭と心を同時に育む究極の英才教育!
【chapter1の小見出し】
- 学校の勉強だけでは通用しない時代
- お金と時間をかけなくてもできる家庭教育
- できる子の親が「これだけはしていた」こと
- 読み聞かせは究極の英才教育
- 「読み聞かせ」と「超・読み聞かせ」の違い
- 読み聞かせは何歳まで?
- 大きくなっても「読み聞かせ」をするワケ
- 目標は年間1000冊
- 継続のためのカギ
- column 1 英語の絵本の読み聞かせについて
点数上の学力以外の能力が求められる時代で、家庭教育はとても重要な役割を担っています。
しかし、収入等の家庭環境によって、家庭教育を受けられることに格差が生じています。
その中でも、本の読み聞かせは、お金と時間をかけなくてもできる家庭教育です。
著者が勧めている「超・読み聞かせ」は以下の方法です。
- 「対話型」の読み聞かせをする
- 本を「ネットワーク型学習」に結びつける
- 読み聞かせを絵本から本へ移行させる
- 読み聞かせを12歳頃まで継続する
- 読み聞かせを毎日の習慣とする
- 1日30分以上の読み聞かせをする
読み聞かせは親子のコミュニケーションツールであり、子どもが何に興味・疑問を持っているのかを知ることができます。
古本・図書館をどんどん活用して、1日3冊・年間1000冊を目標にして、地道に継続してい火なければなりませ。
CHAPTER 2 本を120%学びにつなげる「超・読み聞かせ」をやってみよう
【chapter2の小見出し】
- 本の効果を何倍にもする「対話型」読み聞かせのコツ
- 興味を実体験につなげる「ネットワーク型」読み聞かせのコツ
- 子どもの「学びたい欲」を見逃さない
- 学びは色んなところにある
- 「本大好き!」な子にするには
- 学校の勉強と家での教育
- 子どもの将来にビジョンを持つ
- 読み聞かせは誰のため?
- column 2 図書館に行こう
漠然として読み聞かせではなく、対話型の読み聞かせが勧められています。
その方法は以下の通りです。
- 「これは何?」「これはなんだと思う?」とたくさん質問しながら読み進める。質問はタイミング良く。
- 本を一緒に読みながら制約のない会話をする。「制約がない」という点が大切。答えがある話でなくてもいい。できるだけ子どもに自由に発想させる。
- 子どもの興味に沿って会話を進める。どんどん話がずれてもOK。親は一方的に会話を押しつけない。
本を読むだけではなく、知識と体験を実際の中でリンクさせる「ネットワーク型」読み聞かせも大事です。
本で読んだ知識を実体験させる、または実体験を本を通じて復習させ、知識を派生させ学ぶことを好きにさせる方法です。
興味を応じた本をさりげなく置いておき、少し子どもにとって難解だと思えてもさまざまなものごとのコンセプトを教えておくのが良いです。
CHAPTER 3 子どもを伸ばす「学び」の仕組み
【chapter3の小見出し】
- 読み聞かせで強化する!「3つの学習タイプ」
- 視覚のトレーニング
- 聴覚のトレーニング
- 身体のトレーニング
- 「リスペクト」なしには学べない
- 学ぼうとしないときには
- ときには本気でサバイバルさせる
- 学びに通じる「叱り方」のコツ
- 成長につながる「ほめ方」のコツ
- column 3 「考える習慣」は何歳からでも養える!
学習には主に3つの感覚を使うとされており、人それぞれに優先的に使う感覚が違います。
- 視覚タイプ:お絵描きや字を書くのが好き・文章を読んだり絵や表を見たりして情報を取り入れるのが得意
- 聴覚タイプ:聞いたセリフなどをすぐ覚え役になりきれる・聞いたり話したりするのが好きで情報は聞いて覚えて理解するのが得意
- 体感覚タイプ:興味のあるものに対しての集中力がすごい・触ったり身体を動かしたり動きを真似したりすることで学ぶことが得意
子どもタイプを理解して、それに寄り添ってリスペクトすることで、学ぶ姿勢を身につけることができます。
褒め方のコツは以下の通りです。
- やったことを認める
- 良くできた点に気づく
- 否定はせずに、次なる課題を投げかける
- 次の課題は本人に決めさせる
CHAPTER 4 親が変われば子どもも変わる
【chapter4の小見出し】
- 大人が子どもになることを学ぶ
- 子どものそのままを大切にする
- 競争ではなく共有しよう
- 幸せな人間を育てるには
- column 4 子どもの「心の知能指数」を育てる
子どもは何をするのにも目が輝いており、今在ることに集中しています。
何のフィルターも通さずに世の中を見ています。
その姿勢を大人も見習う必要があり、親も変わっていかなければなりません。
読み聞かせお薦め本リスト
読み聞かせにおすすめな100冊の本が紹介されています。
3つに大別されています。
- 0〜2歳向けの絵本
- 3〜5歳向けの絵本
- ドキュメンタリー、かがく絵本&図鑑
一部抜粋すると以下のものが紹介されていました。
【0〜2歳向けの絵本】
【3〜5歳向けの絵本】
【ドキュメンタリー、かがく絵本&図鑑】
『12歳までの読み聞かせが子どもの「地頭」をつくる!』を読んで今後勉強すべきこと

『12歳までの読み聞かせが子どもの「地頭」をつくる!』では、親が子どもにしてあげられることの1つとして「読み聞かせ」を学ぶことができました。
読み聞かせ以外にも、子どものためにしてあげるべきことがたくさんあります。
そこで、200人を超える東大・京大・早慶を中心とした突出したリーダシップを発揮してさまざまなグローバル企業に進んだ学生に、両親に教育を振り返って感謝している点・直してほしかった点のアンケート結果が紹介されている『一流の育て方』を読んでみます。
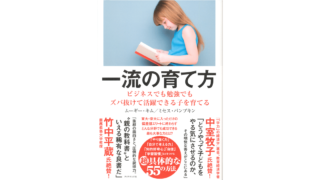
また、史上最年少プロ棋士・藤井聡太さんが幼児期に受けた教育として一躍脚光を浴びている「モンテッソーリ」教育を学ぶことができる『モンテッソーリ教育×ハーバード式 子どもの才能の伸ばし方』を読んでみます。
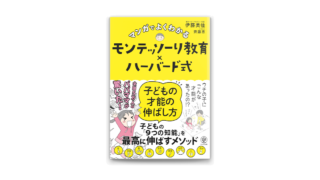
まとめ
『12歳までの読み聞かせが子どもの「地頭」をつくる!』を書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんがご紹介させていただきました。
ですが、まだまだ育児について深く学んでいかなければならないと思いました。
そのため、いろんな本を読んでいきたいと思います。