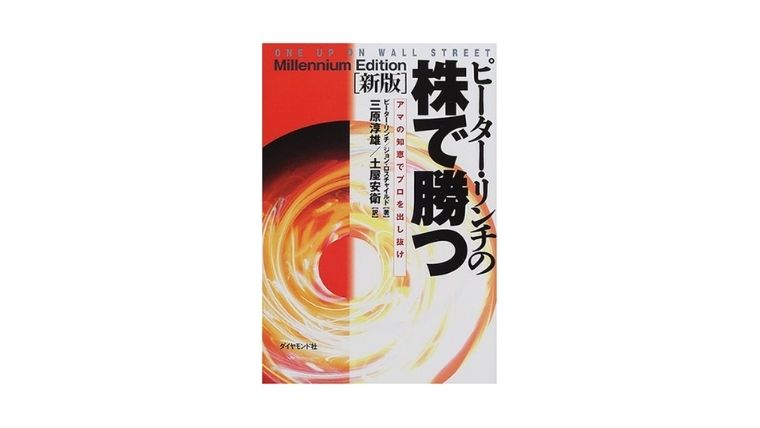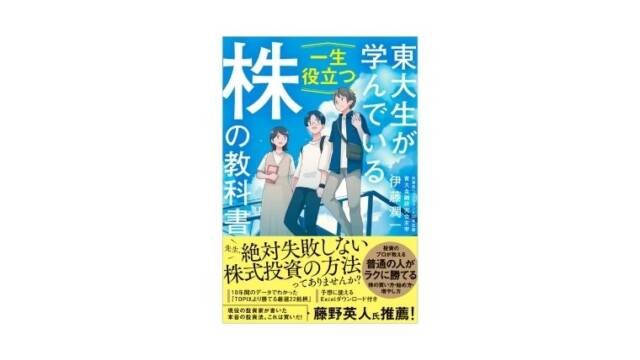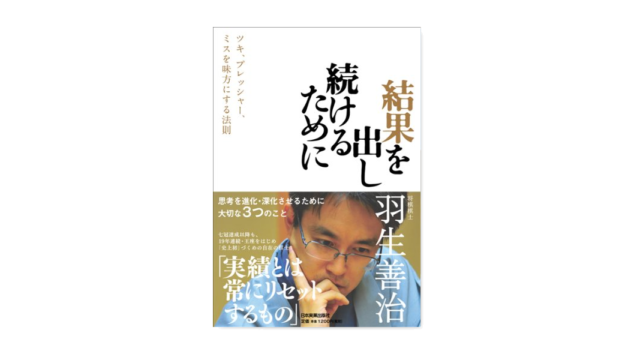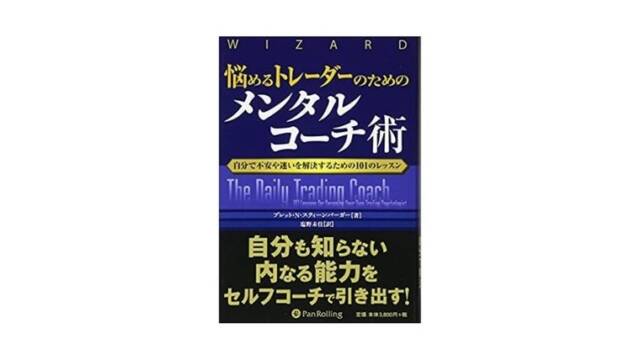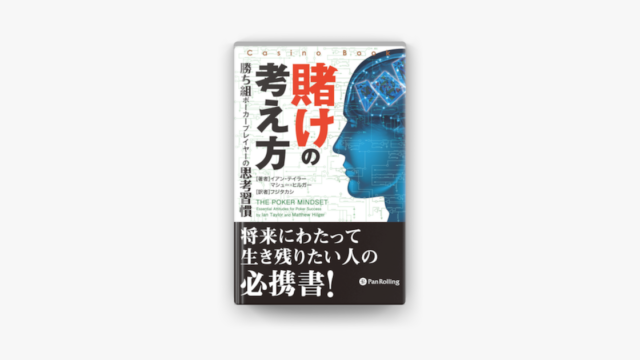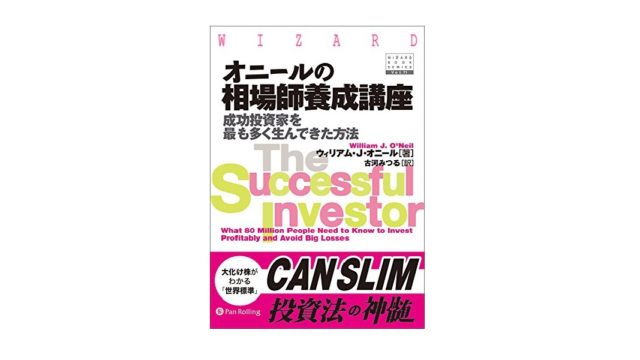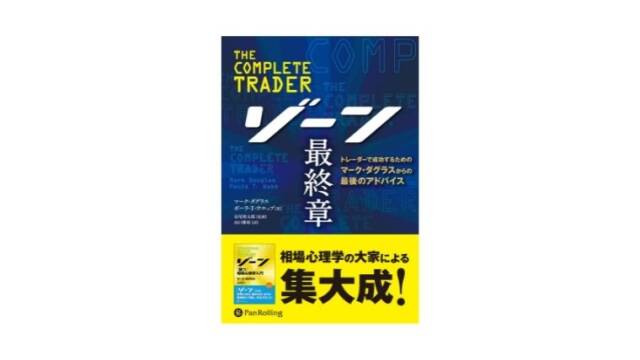投資の勉強をするために、たくさんの本を読んで勉強しています。
『ピーター・リンチの株で勝つ』を読んでいるだけでは記憶になかなか残りにくいため、インプットした知識を整理して、
- 「読んで勉強になったこと」
- 「理解が及ばず、さらに勉強をしなくてはいけないこと」
を感じたままに書き留めます。
とても勉強になりましたので、書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんが紹介いたします。
目次
『ピーター・リンチの株で勝つ』とは?
| 読みやすさ | |
|---|---|
| 専門性 | |
| 役立ち度 |
- 著者:
- 出版社:ダイヤモンド社
- 発売日:2001/3/1
- ページ数:347ページ
【目次】
- ミレニアム版への序章
- プロローグ/アイルランド便り
はじめに/アマチュアの強み - 第1部 投資を始める前に
第1章 株式投資家になるまで
第2章 ウォール街の矛盾した表現
第3章 これはギャンブルなのか? 何なのか?
第4章 鏡の前のテスト
第5章 相場はよいかって? そんなこと聞かれても困る - 第2部 有望株の探し方
第6章 10倍株をねらえ
第7章 ついに見つけたぞ! 何を?
第8章 完璧な株、なんて素晴らしい!
第9章 私が避ける株
第10章 収益、収益、そして収益
第11章 2分間の訓練
第12章 事実を手に入れる
第13章 知って役に立つ幾つかの数字
第14章 ストーリーを再チェックする
第15章 最終チェックリスト - 第3部 長期的視野
第16章 ポートフォリオをつくる
第17章 売り買いのベストタイミング
第18章 株価についてよく聞く多くの馬鹿げた(そして危険な)話
第19章 オプション、先物、カラ売り
第20章 5万人のフランス人も間違えることはある - エピローグ/備えあれば憂いなし
- 訳者あとがき
『ピーター・リンチの株で勝つ』は、ファンドマネジャーの座を降りた直後の1989年に出版された原書『ONE UP ON WALL STREET』の邦訳です。
何度も増刷され、millennium editionとして刷新されたものです。
本書は、個人投資家に向けて「基本的な情報と勇気を与えるため」に書かれたもので、アマチュアの優位性を遺憾なく発揮した投資法が紹介されています。
- 株の判断に役立つ数字
- 株の分類による株動向のとらえ方
- 情報収集のポイント
- ポートフォリオ
- 売買のタイミング など
『ピーター・リンチの株で勝つ』を読んで勉強になったこと

ピーター・リンチは、10倍株(テンバガー)や、自分が知っているものに投資しろといったような投資界隈でよく使われる言葉の生みの親となっています。
テンバガーなどの成長株だけに主眼を置くのではなく、ファンダメンタルズ分析をしっかり行うバリュー投資の専門書でもあります。
本書で重要だと思った箇所を、章ごとにまとめます。
はじめに アマチュアの強み
最初に示されているルールは、「プロのいうことに惑わされるな」です。
プロが買っている株も無視するべきであり、その理由は3つあります。
- プロが間違っているかもしれない。
- その銘柄を買って成功しても、プロが心変わりして売るかもしれない。
- アマチュアの周りに良い情報がいくらでもあるから。
よく知っている銘柄への投資の方が、よくわからない難しい銘柄に投資するよりもずっと良い成績が期待できます。
第1章 株式投資家になるまで
ピーター・リンチは、投資アナリストとして、フィデリティ・マゼランのファンド運用を任されます。
1400銘柄以上、総資産90億ドルにもなります。
ウィル・ロジャース流に、「ギャンブルはいけないよ。貯蓄をしていて、よい株が見つかったら買う。それを上がるまでジッと待ってから売るんだ。上がらないような株なら、買っちゃだめだよ。」と記しています。
第2章 ウォール街の矛盾した表現
「プロの投資家」というのは、逆比喩的な矛盾した言葉だと著者はいいます。
素晴らしいファンドマネージャーはごく少数の例外に過ぎません。
魅力的な株でもウォール街のアナリストですら推薦していないことがある、「ストリート・ラグ」が良い例として示されています。
ファンドマネージャーは、無名で面白い銘柄を買わないための正当な理由を探しており、万一そんな突飛な銘柄が上がってしまった時に十分言い訳が立つようにいつも身構えているからです。
投信・年金などのファンド預かる運用者は、素晴らしい投資収益を狙わず、損するとしてもたかが知れている安定感のある会社で堅実さを望むものです。
会社の制限に引っ掛からなくても、SEC(証券取引委員会)の規定に制約されてしまいます。
機関投資家はこうした制約があるので、アマチュア投資家は機関投資家の真似をしなくて良いのです。
アナリスト・ファンドマネージャーが情報を得る前に、近所・職場で起こっている出来事から素晴らしいチャンスを掴むことができます。
第3章 これはギャンブルなのか? 何なのか?
ブラックマンデーのような下げがあると、債券に逃げ込む投資家が必ず出ます。
しかし、1927年から60年間多くの変動にもかかわらず、株式投資は社債より15倍儲かり、国債より30倍以上儲かります。
歴史的に見て、「投資手段として歓迎される場合」「ギャンブルとして見放される場合」を周期的に繰り返し、株が賢明かつ適切な投資手段になるのは、実は最もそうは思われていない時期ということになります。
第4章 鏡の前のテスト
株で投資をする前に、自分の状態について以下の3つのことを知っておかないといけません。
- 家を持っているか:アメリカでは住宅価格は上がるものなので、株より家を先に買う
- お金が必要か:万一失敗したとしても、将来的に見て、毎日の生活に支障のない余裕資金の範囲で株式投資をすべきだ
- 株で資質が備わっているかどうか:忍耐強さ・自主性・常識・苦痛についての耐久力・こだわりのない自由な思考力・利害に対して超然としていられる強さ・根気・謙虚さ・柔軟性・独自の調査をする意欲・失敗を認める強さ・パニックを無視する力・完全な情報がない中で決断する能力・自分が持つ変な信念や思い込みを取り除くこと
第5章 相場はよいかって? そんなこと聞かれても困る
株で金儲けをするのに株式市場全体の予測をする必要はないのです。
誰も継続的に役立つほどの相場予測などできません。
著者は、アマチュアはカクテルパーティー理論で判断するのはどうだろうかと提案しています。
パーティーの出席者がどれくらい株式市場について話を聞きたがっているかで、相場の加熱具合を確認します。
- 第1段階(底):全く興味を示さない
- 第2段階(15%上昇):少し話を聞いてくれる
- 第3段階(30%上昇):ひっきりなしにどの株を買うべきか聞きたがる
- 第4段階(ピーク):どの株を買うべきかと教えたがる
第6章 10倍株をねらえ
ウォール街よりも先に、自分の周りの情報からテンバガーを見つけることができます。
特に景気循環株をいつ買えば良いのかを肌感覚で知るのに役に立ちます。
一般消費者の知識は、急成長する新興の中小企業、特に小売業の中から有望株を拾い出すのに役に立ちます。
第7章 ついに見つけたぞ! 何を?
身近な情報から手がかりを掴んだからといって、調査をせずに投資をしてはいけません。
会社の規模は株価の動きに大いに影響し、大きな会社はあまり値動きがなく、小さな株の方が大きな動きを見せます。
株は以下の6つの分類して、株価の動きを捉えることができます。
- 低成長株:大きく古い会社で、事業拡張の余地がないので配当が高く安定している株
- 優良株:年10〜12%程度の成長が期待でき、不況にも強く、1〜2年で株価が1.5倍になれば良い株
- 急成長株:年20〜25%程度の成長をし、うまくいけば株価は10〜40倍あるいは200倍にもなりそうな積極性のある少企業の株
- 市況関連株:拡大と縮小を繰り返すので、売上と利益が循環的に上下する株
- 業績回復株:業績不振の淵から立ち直った株
- 資産株:現金・不動産・特許などの資産を持っている株
企業はいつでも同じ状態にいるわけではないので、急成長株から市況関連株になったりするので、どこに分類されるか調べ続けなければいけません。
第8章 完璧な株、なんて素晴らしい!
投資対象の選別にあたって、最も需要な13項目が記載されています。
- 面白みのない、または馬鹿げている社名
- 変わり映えのしない業容
- 感心しない業種
- 分離独立した会社
- 機関投資家が保有せず、アナリストがフォローしない会社
- 悪い噂の出ている会社
- 気の滅入る会社
- 無成長産業であること
- ニッチ産業であること
- 買い続けなければならない商品
- テクノロジーを使う側であること
- インサイダーたちが買う株
- 自社株買い戻し
基本的に割安に放置されていたり株、安定したビジネスの株を選択することを勧めています。
第9章 私が避ける株
ピーター・リンチが何よりも避けたいのは、以下のような株です。
- 超人気産業の中の超人気会社株
- 第二の〇〇株と人々が言い出した株(本家も危ない)
- 馬鹿げた買収をするなど多悪化する企業の株
- 美味しそうなストーリーだけの穴株・耳打ち株
- 下請け会社の株
- 名前の良い会社の株
第10章 収益、収益、そして収益
株とは、宝くじではなく、ある会社の部分所有権です。
収益が上がれば株価が上がるので、株価が収益に先行すると株価の方が下がって調子を合わせます。
会社が投資額を稼ぎ出すのに何年かかるかの目安となるPER(株価収益率)を用いて、割安か割高かを判断することができます。
異常なまでに高いPERの株に投資するのは避けるべきで、市場全体のPERが高騰しているときは株価暴落に備える必要があります。
第11章 2分間の訓練
株を実際に買う前には、「その会社の魅力・成長性・弱点」などもう1度2分間だけ自問自答してみましょう。
子どもにも理解してもらえるまでに理解がこなれていれば、その会社の株に対する投資準備は万全と言えます。
第12章 事実を手に入れる
アマチュア投資家であっても知っていれば役に立つ情報は、入手できないことはなく、容易に知りうる状態にあります。
目論見書・四半期報告書・年次報告書・刊行物などの中に役に立つ情報があります。
特別な質問を持っているなら、会社のIRの担当に直接相談してみると良いです。
会社というものは、株主に対しては正直に、素直に答えてくれるものです。
本社訪問・株主総会・実地検証をすることでも情報を得ることができます。
第13章 知って役に立つ幾つかの数字
知って役に立つ数字について、以下のものが紹介されています。
- 売上に対する比率:総売上高の中に商品シェア割合
- 株価収益率(PER):高すぎず、低すぎない化
- キャッシュ・ポジション:ネットベースでのキャッシュ
- 負債科目:負債対資本比率・どんな負債か
- 配当:不況期や最も悪い時期に配当をできるかどうか
- 簿価・含み資産:過大評価・過小評価されていないか
- キャッシュ・フロー:フリーキャッシュ・フローが高いか
- 在庫:在庫が増えていないか
- 成長率:福利計算して将来の収益を予想
- ボトムライン:税引き後の利益率が高いか
第14章 ストーリーを再チェックする
数ヶ月おきに会社に関するストーリーを再点検してみると良いです。
四半期報告書で予定通りに利益が保たれているかどうかといった収益の状況を確認できます。
商品が魅力的か、繁栄している雰囲気があるか、店に行って確認もできます。
企業の成長段階を3つに分け、どこに属しているかを再点検します。
- 始動段階:企業の成功が明確になっていない時期
- 上昇段階:成功パターンを繰り返す最も利益上げられる安定な時期
- 成熟段階:企業の限界に近づきつつあり、他の方法を模索する時期
第15章 最終チェックリスト
第2章を総括したチェックリストが記載されています。
【株式全般について】
- PERは高いか低いか、同業他社との比較においてはどうか
- 機関投資家の持ち株比率はどうか
- インサイダーが買っているか、会社自体が自社株の買い戻しを行っているか
- 最高の利益はどれくらいか、それは偶発的か安定的か
- 賃借対照表は負債資本比率から見て健全か
- 流動比率はどうか
【低成長株について】
- 増配が定期的に行われているか
- 配当性向を確認し、景気悪化にも耐えうる余裕があるか
【優良株について】
- PERが割高じゃないか
- 将来、多悪化の可能性があるか
- 長期的な成長率を保っているか
- 過去の不況・市場の低迷を如何に乗り切ったか
【市況関連株について】
- 在庫・需給関係について注意深く見守る
- 景気回復にもかかわらず、PERが低下する可能性がある
- 身近な市況商品について知っているか
【急成長株について】
- 会社に利益を与える商品が主要商品であるか
- 最近の収益の成長率はどうなのか
- 拡大戦略が有効か、拡大余地があるか
- 株価が成長率に相応しい水準になっているか
- 拡大のスピードが上がっているか下がっているか
- 機関投資家の持ち株比率が小さく、アナリストがほとんど関心を寄せてないか
【業績回復株について】
- 債権者からの攻勢に耐えられるか
- 倒産しても株主に何が残るか
- どのような方法で業績を回復させようとしているか
- そのビジネスが活気を取り戻しつつあるか
- 経費の削減は行われているか
【資産株について】
- 資産の価値はどれくらいか
- 資産から引かれる負債はどの程度あるか
- 資産の含み益を株主に獲得させるきっかけを作るような乗っ取り屋が関係していないか
第16章 ポートフォリオをつくる
株式投資の収益率を出す上で忘れてならないのは、全てのコストを含めるということです。
ニュースレターや金融関係雑誌の購読料・手数料・セミナー参加費など投資に要した全ての費用を含めなければなりません。
これらを含めると、一般的・歴史的な長期株式投資の収益率は9〜10%です。
これを前提にすると、S&P500連動の投資信託1つに投資すればこれだけの利益を手に入れられるところ、自分で銘柄選びをするのであるならば複利で12〜15%には回るようにせねばなりません。
この収益率をもたらすためのポートフォリオとして、
- 自分の得意分野に関連する銘柄
- あらゆる調査の結果、非常に有望な見通しを発見した銘柄
を3〜10銘柄保有するのが良いです。
もし、10倍株を探し当てようとするなら、保有する銘柄が多ければ多いほどよいが、入れ替える柔軟性が求められます。
「低成長株・優良株・急成長株・市況関連株・業績回復株・資産株」とカテゴリーに分けて分散して持つことで、リスクを最小にすることもできます。
第17章 売り買いのベストタイミング
株を買うタイミングとして、良いバーゲンタイミングとなる時期が2つあります。
- 年末の恒例の税金対策のための売りが出る時期
- 数年に一度の大暴落
これらは、売りが売りを呼び、とんでもない水準まで下げてしまうので割安に買うことができます。
株を売り急いではいけなく、確かな株を見つけて買った時に、さらに値上がりする証拠があって全て考えている方向になっている場合に売るのは恥ずべきことです。
株を本当に売るタイミングは、株の分類別に以下の通りです。
【低成長株を売るとき】
- 株価が30〜50%値上がり
- ファンダメンタルが悪化
- 2年連続でマーケットシェアを落とし、新たに1つ広告会社を雇い入れた
- 新製品の開発がなく、研究開発費を切り詰め、過去の影響にしがみついている
- 最近、業種の違う会社を2社ほど買収したものの、ますます業績を悪化させている。ところがさらに、「技術力のある」会社の買収に意欲を見せている
- 買収のために多額の出費をしたために、財務状況を悪化させてしまっている
- 低株価にもかかわらず、投資家を惹きつけるだけの配当利回りさえない
【優良株を売るとき】
- 直近2年間に投入された商品の評価がまちまちで、試作段階の新商品が市場に出るまでには1年以上も間がある
- 同業他社のPERが11〜12倍であるのに、その株が15倍になった
- 前年、役員が自社株を購入していない
- 利益の25%を占める主力部門がマクロの経済指標によって影響を受ける
- 成長率が鈍化し、合理化効果がそれほど期待できない
【市況関連株を売るとき】
- 景気循環の終了時
- 在庫が積み増しされている
- 石油・鉄鋼などの市況の悪化
- 競争の激化
- 労組が協約時に譲歩していた賃金と福利厚生費の全面復活を要求している
- 設備投資予算が倍増
- 外国製品との価格競争に太刀打ちできない
【急成長株を売るとき】
- 減益になり、PERが悪化
- PERが高すぎる
- 最近の四半期業績で店の売上が3%落ちた
- 新店舗の売上が良くない
- 役員が2人、優秀な社員と共にライバル企業に移った
- 機関投資家相手に非常に強気な説明をする
【業績回復株を売るとき】
- 業績が回復して、成長株・市況関連株などに戻った
- 借入金が増えている
- 在庫の増加
- 収益予想に対してPERが高すぎる
- 売上減少
【資産株を売るとき】
- 乗っ取り屋が出てきた
- 増資を発表した
- 資産の価値が下がった
- 税額控除が減った
- 機関投資家の持ち株比率が上がった
第18章 株価についてよく聞く多くの馬鹿げた(そして危険な)話
株価の動きを説明するおなじみの根拠のない格言がたくさんあります。
- もうこんなに下がったのだから、これより下がりようがない
- 株価が底に来たら、それとわかるものだ
- こんなに株価が上がってしまって、これ以上の上値などあるはずがない
- わずか三ドル。何を失うというのだろう
- 結局、株価は戻る
- 夜明け前はいつも一番暗い
- 10ドルに戻ったら売る
- 何を心配することがあろう。保守的な株はあまり値が動くことはないのに
- 何が起こるには、もう時間がたちすぎている
- 得べかりし利益、なぜ買わなかっただろう
- これは逃してしまったが次は捕まえよう
- 株価は上がったのだから正しかったのだ。下がってしまったから間違っていたのだろう
第19章 オプション、先物、カラ売り
ピーター・リンチは、先物もオプションも一度も買ったことはない。
専門のトレーダーでもない限り勝のは不可能だと言われる先物・オプションに惑わされることなく、株式市場の普通株で儲けるだけでも大変なことです。
空売りには、株を借りている間配当を受ける恩恵を受けることができない、暴騰したら青天井に損失が膨らむなどが欠点です。
第20章 5万人のフランス人も間違えることはある
市場の動きも個別株と同様に、短期ではファンダメンタルズと反対に反応することがあります。
『ピーター・リンチの株で勝つ』を読んで今後勉強すべきこと

『ピーター・リンチの株で勝つ』を読んで、投資の古典の本をもっと読んで勉強しなくてはいけないなと感じました。
まず、ウォール街で密かにロングセラーになっていた「The Zurich Axiims」の日本語版である『マネーの公理』を読んでみたいと思います。
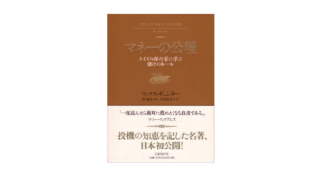
さらに、四季報・決算短信・有価証券報告書などを駆使して、「ファンダメンタル投資」を実施することが学ぶことができる『ファンダメンタル投資の教科書』を読んでみます。
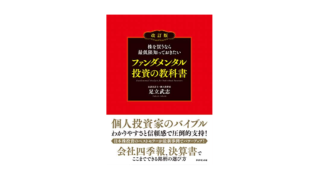
まとめ
『ピーター・リンチの株で勝つ』を書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんがご紹介させていただきました。
投資をしていくためには、まだまだトレーニングが必要ではありますが、少しずつ実践していこうと思います。
より優れた投資家、いえ投機家になるために、色々な本を読んでみたいと思います。