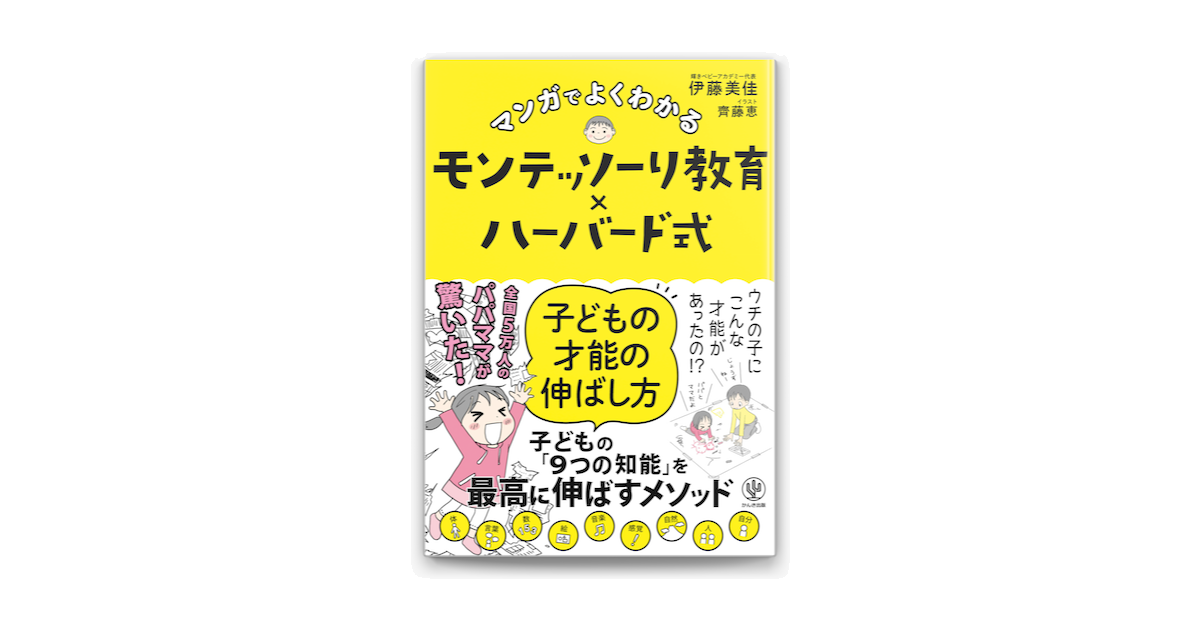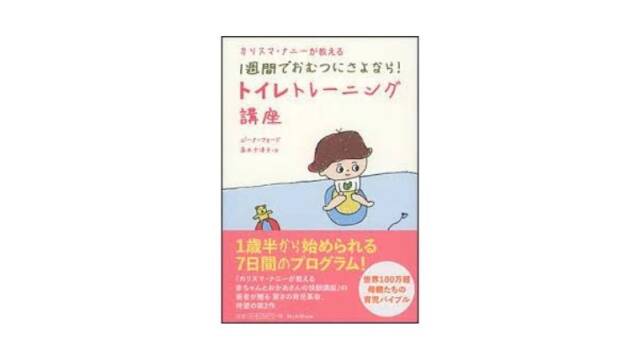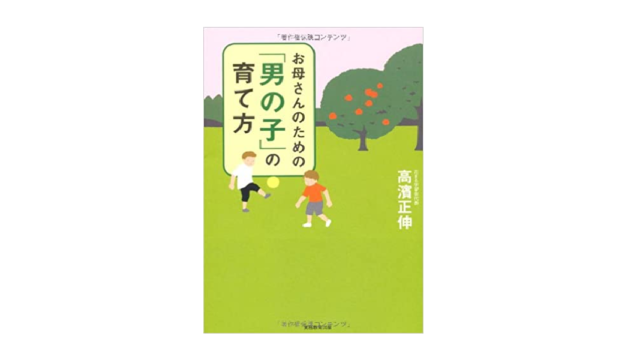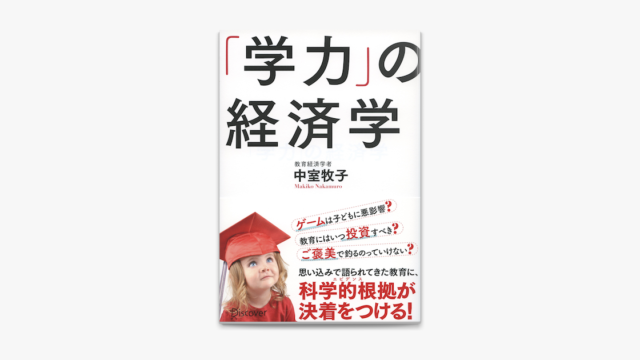子育てをするために、たくさんの本を読んで勉強しています。
『マンガでよくわかる モンテッソーリ教育×ハーバード式 子どもの才能の伸ばし方』を読んでいるだけでは記憶になかなか残りにくいため、インプットした知識を整理して、
- 「読んで勉強になったこと」
- 「理解が及ばず、さらに勉強をしなくてはいけないこと」
を感じたままに書き留めています。
とても勉強になりましたので、書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんがご紹介いたします。
目次
『マンガでよくわかる モンテッソーリ教育×ハーバード式 子どもの才能の伸ばし方』とは?
| 読みやすさ | |
|---|---|
| 専門性 | |
| 役立ち度 |
- 著者:伊藤美佳
- 出版社:かんき出版
- 発売日:2020/2/19
- ページ数:184ページ
【目次】
- 第1章:イタズラする!言うこと聞かない! 子どもの行動のヒミツ
- 第2章:自立心と集中力がしっかりと育つモンテッソーリの教え 6歳までの育て方で未来が変わる
- 第3章:ハーバード式 世界にはばたく才能を伸ばす「9つの知能」
- 第4章:モンテッソーリ流 子どもへの「接し方8カ条」
- 第5章:モンテッソーリで大切にしている 0~6歳の育て方
一躍脚光を浴びています。
『マンガでよくわかる モンテッソーリ教育×ハーバード式 子どもの才能の伸ばし方』を読んで勉強になったこと

『マンガでよくわかる モンテッソーリ教育×ハーバード式 子どもの才能の伸ばし方』は、著者が代表理事を務める乳幼児親子教室「輝きベビーアカデミー」で用いられている「輝きメゾット」が紹介されています。
題名にもある通り、輝きメゾット=モンテッソーリ教育×ハーバード式で表現されます。
これら本章の内容について勉強になったことを、章ごとに抜粋しまとめさせていただきます。
第1章:イタズラする!言うこと聞かない! 子どもの行動のヒミツ
子どもはよくイタズラをしたり、悪さばかりするように大人目線では感じてしまいます。
大人としては困った行動も、子どもにとっては伸ばしたい能力を試している最中です。
なので、怒ったりせずに優しく見守ってあげる必要があり、心構えについて以下にように記載されています。
それどころか、イタズラに夢中になっている子どもを見て、「こんなに集中して、自分の能力や才能を伸ばしている最中なんだ!」と前向きにとらえることができます。
引用:マンガでよくわかる モンテッソーリ教育×ハーバード式 子どもの才能の伸ばし方 p34 7〜8項
しっかり才能が伸びている最中は、「才能のかたまり」ではなく、「はみ出しっ子」として見られがちです。
見方を変えれば、「子どもの行動が遅い」は「集中力が高い」に、「ボーッとしている」は「想像力が豊か」だということになります。子どもは1人残らず、その子なりの才能を持っていて、その才能を伸ばす力があります。
引用:マンガでよくわかる モンテッソーリ教育×ハーバード式 子どもの才能の伸ばし方 p38 8〜10項
子どもは飽きっぽくてコロコロ好きなこと・やりたいことが変わります。
これは、やりきったときに別の能力を使いたくなるので、興味・関心がどんどん移っていくためですので、受け入れてあげましょう。
第2章:自立心と集中力がしっかりと育つモンテッソーリの教え 6歳までの育て方で未来が変わる
モンテッソーリ教育の基本的な考え方について以下のように記載されています。
「子どもは自らを成長させ、発達させる力を持って生まれてくる。大人である親や教師は、子どもの成長欲求をくみ取り、自由を保障し、子どもたちの自発的な活動を援助する存在に徹しなければならない」というもの
引用:マンガでよくわかる モンテッソーリ教育×ハーバード式 子どもの才能の伸ばし方 p44 3〜5項
子どもは時期によって発達させる能力の旬があり、モンテッソーリ教育ではその時期を「敏感期」と読んでいます。
6歳までが大事な時期とされており、特に将来の人格や人生の土台になるような発達は3歳までが重要です。
敏感期にもともと持っている能力を引き出すのに、「遊び・運動・コミュニケーション」が大事になり、多くの刺激を体験することによって能力が伸びていきます。
そのために、子どもが集中状態(フロー状態)を経験できているかが重要になります。
子どもがこの状態に入っているときの表情は以下のように記載されています。
子どもが遊びに夢中になっているときは、表情ですぐにわかります。唇をとがらせ、なかには夢中になって口が開いてしまい、思わずよだれが出ても気づかない子もいます。
引用:マンガでよくわかる モンテッソーリ教育×ハーバード式 子どもの才能の伸ばし方 p60 7〜8項
フローに入るための5つのステップが紹介されています。
- やりたいことをする
- 何度もやる
- 集中してやる
- 達成感を味わう
- 次の新しいことに挑戦する
ステップ4の「達成感を味わう」のが肝になり、ちょっと難しいものであることが大事です。
第3章:ハーバード式 世界にはばたく才能を伸ばす「9つの知能」
ハーバード式とは、ハーバード大学教育学大学院教授であるハワード・ガードナー教授が唱える「知能MI(マルチプル・インテリジェンス)」にある、「8つの能力」が原点になります。
8つの能力は、「言語能力、論理的・数学的能力、空間能力、身体・運動能力、音感能力、人間関係形成能力、自己観察・管理能力、自然との共生能力」になります。
これを日本人向け・幼児教育向けに9つの知能としてアレンジしたものハーバード式として用いています。
9つの知能
- 「体」の知能
- 「言葉」の知能
- 「数」の知能
- 「絵」の知能
- 「自然」の知能
- 「感覚」の知能
- 「音楽」の知能
- 「人」の知能
- 「自分」の知能
①「体」の知能
「体」の知能は、体の全体・一部位を、問題解決・創造のために使う能力のことを指します。
この知能が高い子は、運動神経のいい子、手先が器用な子と表現される子です。
体の発達段階に合わせて、時期に必要な動きを経験させることが大事になります。
知能を伸ばすアクティビティとして、「お手玉遊び・ジェスチャー遊び・ぞうきんがけ競争」が紹介されています。
②「言葉」の知能
「言葉」の知能は、話し言葉・書き言葉を効率的に使いこなす能力のことを指します。
乳幼児期からたくさん話かけてあげることが大事になります。
知能を伸ばすアクティビティとして、「言葉探しゲーム・オノマトペ遊び・絵本」が紹介されています。
③「数」の知能
「数」の知能は、計算・暗算したり、問題を論理的に分析する能力のことを指します。
最近はプログラミング思考が注目されているようです。
知能を伸ばすアクティビティとして、「数遊び・磁石と鈴遊び」が紹介されています。
④「絵」の知能
「絵」の知能は、視覚的に空間パターンを認識する能力のことを指します。
空間認識力もこの知能が大きく関係しています。
知能を伸ばすアクティビティとして、「タオルハンカチ遊び・空き箱積み・模造紙で大きな地図づくり」が紹介されています。
⑤「自然」の知能
「自然」の知能は、自然・人工物の種類を識別する能力のことを指します。
自然の豊かな表情に五感を使ってたくさん触れることで、感性・センスが磨かれます。
知能を伸ばすアクティビティとして、「落ち葉遊び・夜空の観察・影踏み遊び」が紹介されています。
⑥「感覚」の知能
「感覚」の知能は、五感を駆使して、様々な情報を敏感に受け取れる能力のことを指します。
五感で多くを感じ取ること体験をしてきた子どもほどセンスがよく、表現力が豊かな人に成長する傾向にあります。
知能を伸ばすアクティビティとして、「ふれあい遊び・センサリートイ・すり鉢」が紹介されています。
⑦「音楽」の知能
「音楽」の知能は、音楽の種類・リズム・音程などを識別する能力のことを指します。
この知能が高まると、作曲・演奏だけではなく、聞く力も伸びて言葉を扱う能力にも関わります。
知能を伸ばすアクティビティとして、「これなんの音遊び・なんでも楽器遊び・わらべ歌」が紹介されています。
⑧「人」の知能
「人」の知能は、他人の感情・意図・動機・要求を理解して、他人とうまくやっていく能力のことを指します。
コミュニケーション能力・人間関係の構築に大きく影響されます。
知能を伸ばすアクティビティとして、「おままごと遊び・おうちごっこ・おうちの手伝い」が紹介されています。
⑨「自分」の知能
「自分」の知能は、自分自身の長所・短所を理解した上で、目標達成・動機付けなどを自律的に行う能力のことを指します。
頭の中で深く考える内省的になれます。
知能を伸ばすアクティビティとして、「砂絵遊び・世界地図・おだんご作り」が紹介されています。
第4章:モンテッソーリ流 子どもへの「接し方8カ条」
モンテッソーリ教育で提唱している「子どもと接するときの心構え12カ条」をベースに著者の経験を加味して、8つの接し方としてまとめられています。
- すべてを受け入れる:大人の常識を押し付けない
- 自分で選ばせる:小さなことでも選ばせる
- 信じて、待つ:自分で気づくまで待つ
- 満足するまでやらせる:時間などのルールを決めて、その中では好きにさせる
- 子どもに解決させる:ケンカやトラブルなどを安全を確保した中で見守る
- 間違いを訂正しない:失敗して自分で考えさせる
- 子どもと「楽しい!」を共有する:親が遊び心を持って子どもと接する
- 自然の中で遊ぶ:家にいるよりも刺激が多く、フロー状態に入る機会が多い。
第5章:モンテッソーリで大切にしている 0~6歳の育て方
子どもの年齢に応じて、適した育て方が紹介されています。
子どもができる能力・悩み・伸ばすべき能力もしっかりまとめられています。
0歳
0歳の能力
- 原始反射(把握反射)で、手のひらに触れたものをギュッと握れる。
- ママ・パパの声を聞き分けることができる。
- 生まれてすぐには視界はぼんやり。白黒やはっきりした色が好き。だんだん正常な視力がついてくる。
- 3ヶ月くらいから首がすわり、5〜6ヶ月には背筋がついてきて飛行機のようなポーズも。
- 足の力が強く、早い子では6ヶ月未満にはすりばいを始める。
0歳に伸びる能力は、「体」「感覚」です。
寝てる状態からつかまり立ちまで、凄まじいスピードで成長します。
いろいろな人・ものに触れ合わせ、見守りながらチャレンジさせるようにします。
1歳
1歳の能力
- 二足歩行ができるようになり、背筋がしっかりしてくる。
- 単語が話せるようになる
- 1歳後半になると、「イヤ」など自己主張ができるようになる。
- 親指・人差し指・中指でものが掴めるようになる
1歳に伸びる能力は、「自分」「体」「数」です。
自分で行動が決められるようになり、自己確立のスタートです。
手先が器用になり、数の概念がわかるようになります。
子どもが体験できる環境を与え、気持ちをできる限り読み取って言葉でフォローするようにします。
2歳
2歳の能力
- 2語文でを言うようになる。
- 狙ったところにボールが投げられる。
- 人のマネをすることができる。
- 歩く・走る・ジャンプするなど運動能力が高まる。
- 階段をゆっくり降りるなど、手足と目の協調性が出てくる。
2歳に伸びる能力は、「自分」です。
自我が芽生え、イヤイヤ期に入り、すぐ癇癪を起こすようになります。
子どものやりたいを叶えてあげて、成功体験を作ってあげます。
3歳
3歳の能力
- 3語文以上を話せるようになる。
- 両手で体重を支えられる。うさぎ跳びができる。
- 箸が使えるようになる。
- 箱をハサミで切り開くことができる。
- ジュースなどをこぼさずに注げる
3歳に伸びる能力は、「体」「言葉」「絵」です。
思いっきり体を使って運動能力、おしゃべりをする能力がを伸びます。
さらに、絵を描くなどの表現もできるようになります。
達成感を味わせるために、最後までやり抜きたい気持ちが湧きます。
途中で無理やりやめさせてしまうと良くないので、時間などの枠組みを作ってあげましょう。
4歳
4歳の能力
- でんぐり返し、階段飛び降りなどができる。
- ダンスが踊れる
- 一文を書くことができる。
- 100まで数えられる。
- 片足立ち・平均台を歩くなどバランス感覚が発達
4歳に伸びる能力は、「自分」「音楽」です。
音楽の能力が大きく伸び、音を耳で聴き、それに合わせて楽器を使えるようになります。
自己確立も最終段階になるため、子どものよき理解者になり、固定観念を押し付けないようにします。
5歳
5歳の能力
- 逆立ちなどスピーディで器用な動きができる。
- 蝶々結びができる。
- 鉛筆が上手に使える。
- 自転車に乗れる。
- 想像力を働かせ、粘土や泥で自分なりの表現ができる。
5歳に伸びる能力は、9つ能力すべてです。
なんでもやりたいことをやらせることが大事です。
家事も手伝うことができるようになり、さまざまな能力を育てるのに最適なのでやらせてみましょう。
6歳
6歳の能力
- 手先がますます器用になる。
- ルールや決まり事が守れるようになる。
- 知識欲が高まる。
- 見えない部分の積み木・展開図などが分かるようになる。
- 縄跳び・一輪車・竹馬など、運動能力が高まる。
6歳に伸びる能力は、「人」です。
自己が確立するので、コミュニケーション能力も高まり、周りとの関係性が気になり出します。
人との社会性が育つ過程で、トラブルが生じやすいですが、子供だけで解決できるように導きましょう。
『マンガでよくわかる モンテッソーリ教育×ハーバード式 子どもの才能の伸ばし方』を読んで今後勉強すべきこと

『マンガでよくわかる モンテッソーリ教育×ハーバード式 子どもの才能の伸ばし方』は、輝きメゾットを理解することができますが、モンテッソーリ教育そのものではなく改変されたものが理解できます。
そのため、一度純粋なモンテッソーリ教育について勉強してみたいと思い、『0~3歳までの実践版 モンテッソーリ教育で才能をぐんぐん伸ばす!』『3~6歳までの実践版 モンテッソーリ教育で自信とやる気を伸ばす!』を読んでみます。
また、ハーバード式として取り上げられているハワード・ガードナー教授が唱える「知能MI(マルチプル・インテリジェンス)」についても勉強したいと思い、『MI:個性を生かす多重知能の理論』を読んでみます。
まとめ
『マンガでよくわかる モンテッソーリ教育×ハーバード式 子どもの才能の伸ばし方』を書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんがご紹介させていただきました。
ですが、まだまだ育児について深く学んでいかなければならないと思いました。
そのため、いろんな本を読んでいきたいと思います。