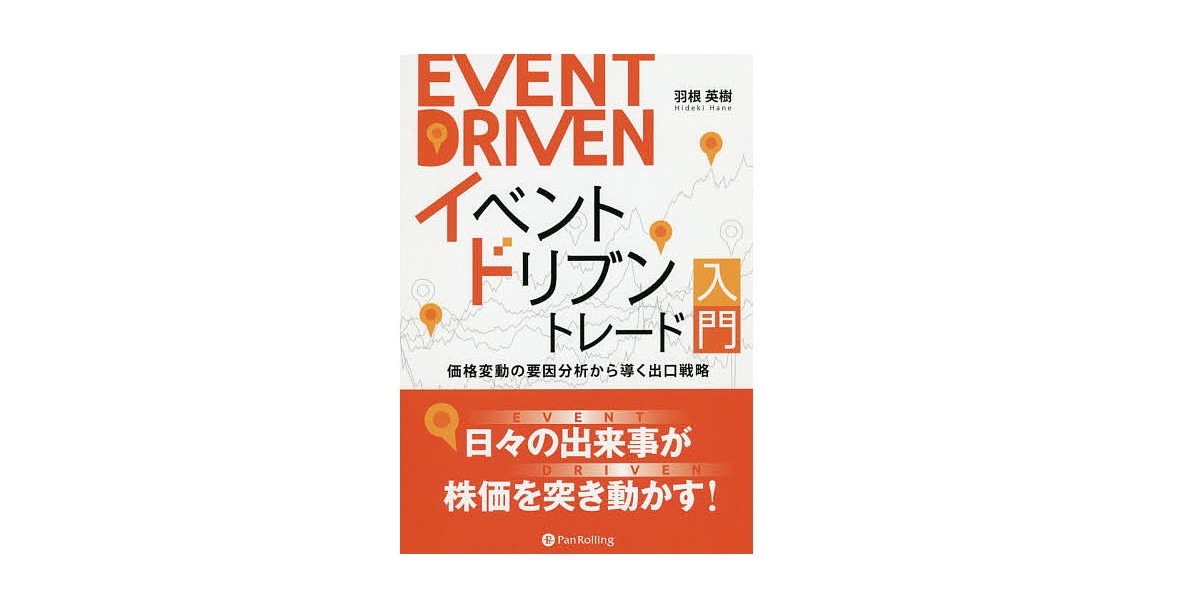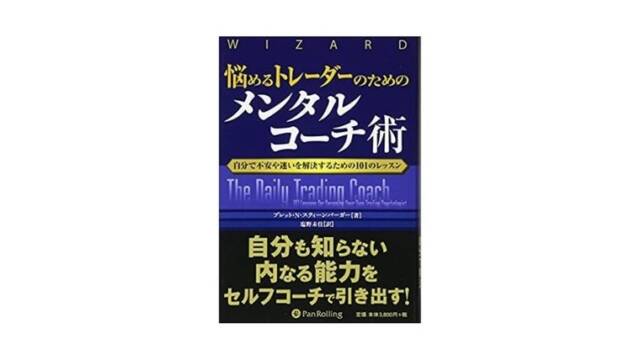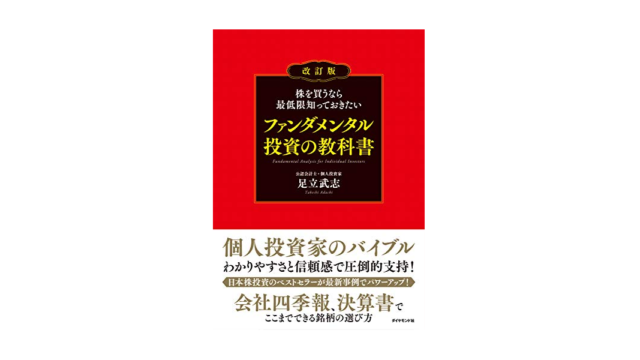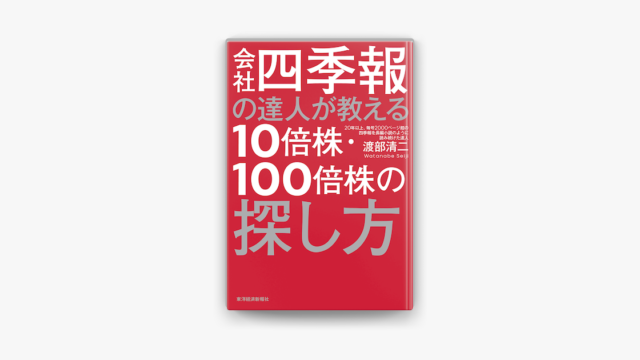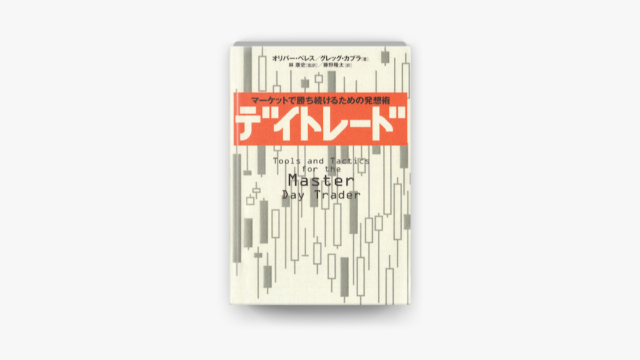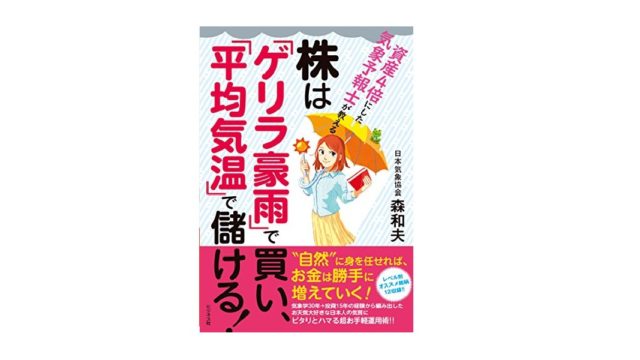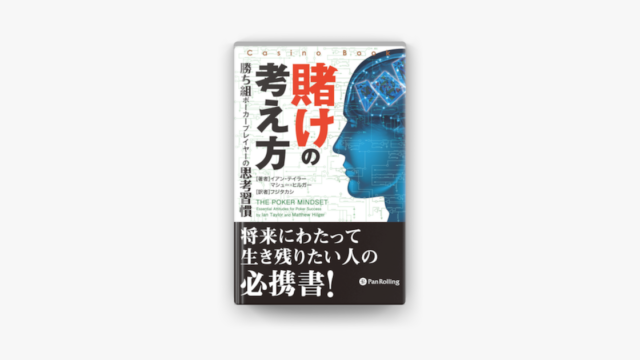投資の勉強をするために、たくさんの本を読んで勉強しています。
『イベントドリブントレード入門』を読んでいるだけでは記憶になかなか残りにくいため、インプットした知識を整理して、
- 「読んで勉強になったこと」
- 「理解が及ばず、さらに勉強をしなくてはいけないこと」
を感じたままに書き留めています。
とても勉強になりましたので、書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんがご紹介いたします。
目次
『イベントドリブントレード入門』とは?
| 読みやすさ | |
|---|---|
| 専門性 | |
| 役立ち度 |
- 著者:羽根英樹
- 出版社:パンローリング株式会社
- 発売日:2019/2/17
- ページ数:283ページ
【目次】
- 第1章:イベントドリブンとは何か
- 第2章:株価指数と機関投資家の売買行動
- 第3章:公募増資
- 第4章:TOB(公開買い付け)
- 第5章:株主優待の本質
- 第6章:新規公開株イベントでの売買
- 第7章:その他のイベント
- 第8章:イベントを探す
- 第9章:ヘッジ
- 第10章:検証と売買ルール
- 第11章:売買の上達を目指して
- おわりに
イベントドリブンとは、「価格を動かす正体が分かっているものに対して、その現象を利用し利益を上げようとする手法」です。
対象となるイベントは多岐にわたり、『イベントドリブントレード入門』ではそれぞれのイベントの特徴・検証結果がをまとめられています。
著者の羽根氏は、サヤ取りを主力にトレードする個人投資家でもあり、数々の書籍を出版している実力者です。
『イベントドリブントレード入門』を読んで勉強になったこと

イベントドリブンの対象は、M&A・TOB・MBO・公募増資・立会外分売・株主優待などの企業活動から、不祥事・事故・事件など多岐に渡っており、それらについて詳細に記載されております。
『イベントドリブントレード入門』の章ごとに、重要だと思ったところをまとめさせていただきます。
第1章 イベントドリブンとは何か
イベントドリブンでは、株式市場独自のルール・慣習・制度や売買主体の違いなどが産み出す需給の歪みを利益の源泉とします。
これらは一部を除いてトレードスパンが決まっているため、資金管理・ポジション管理が容易になります。
「イベント終了=手仕舞い」と出口戦略がはっきりしているからです。
また、上げ相場下げ相場に左右されにくい「全天候型のトレード手法」で、毎年毎年こつこつと利益を上げていくタイプの手法になっています。
そのため、デイトレード・スキャルピングと違い、細かいタイミングを計る必要もなく、時間にゆとりを持ち、サラリーマンでも十分に実践できます。
第2章 株価指数と機関投資家の売買行動
インデックスファンドは、指数より儲けていけないため、市場に合わせてリバランス・銘柄入れ替えを行います。
機関投資家のそうした動きのタイミングを利用した取引を実施します。
指数の算出ルールなどは改定が行われることがあるので、指数の特徴などを深く理解しておく必要があります。
指数への採用・除外・リバランスを利用してトレードを行います。
日経225
日経225は、日本経済新聞社が銘柄選定を行っており、東証1部の225銘柄で構成されています。
単純平均を採用しているため、値嵩株の影響を受けやすい指数です。
例年9月頃に定期的に銘柄入れ替えが実施され、上場廃止・東証1部からの移動などでも銘柄入れ替えが実施されます。
入れ替えの時期になると採用銘柄・除外銘柄の予想が証券会社等から発表されます。
10銘柄近く候補が上がりますが、実際に的中するのは1銘柄あれば良い方です。
そのため、採用候補にすべて空売りしておいて、正式な入れ替えがあってから買い戻す戦略が成り立ちます。
また、入れ替え発表から組み入れ日までの間で、採用銘柄の買い集め・除外銘柄の売り出しが始ります。
採用銘柄が株価の高い・入れ替えまでの日数が短い場合は、値上がりしやすい傾向にあります。
TOPIX
TOPIXは、東証一部全銘柄の平均を示す指数で、浮動株基準株価指数という「浮動株が多いほど指数に対する寄与度が上がる」方式を採用しています。
浮動株の比率をFFWと言い、年4回の見直しがあります。
FFWの定期見直しの時期が近づくと、FFWの増減予想レポートが証券会社等から出てきます。
増資などで大きく株主が大きく変化する場合は、臨時の見直しがされます。
また、東証一部に上場した場合、翌月末からこの指数に反映されます。
TOPIXで注目すべきは、組み入れを先回りしすぎで、組み入れ直後に下がる傾向があることです。
海外の指標【MSCI・FTSE】
MSCIは、アメリカのモルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社が算出しているアメリカの指数です。
5月・11月の月末に大きなリバランスがあります。
FTSEは、イギリスのFTSEインターナショナル社が算出している欧州の指数です。
3・6・9・12月の中旬に年4回のリバランスがあります。
第3章 公募増資
公募増資とは、上場企業が市場から広く資金調達をするために、発行株式数を増やして増資を行います。
数%ディスカウントされた金額で、受け渡しがされます。
第三者割当投資は特定の投資家に引き受けてもらいますが、公募増資は不特定多数の投資家に引き受けてもらいます。
この際に、一株あたりの価値が下がるため、株価が下落することが多くなります。
そのため、空売りで下げを狙う戦略がメインとなります。
賃借銘柄が対象になるため、公募期間中の空売り禁止・株価安定のための株価操作に気をつけながらトレードする必要があります。
売出し
公募増資と同じ手順で、「売出し」というものが実施されます。
違う点は、新株が発行されず、大株主が大量の手持ち株を手放す時に実施されます。
そのため、公募増資のような希釈化は起こりませんが、浮動株が増えることにより短期的に小規模に株価が下落することが多いです。
立会外分売
立会外分売は、売出しと同じことを、市場外で行います。
売出しよりも手続きが簡便であり、「株主数を増やす」という目的で行われることが多いため、実施頻度が高いです。
株主数を増やす目的は、東証1部等の上位市場への昇格を狙ってる場合が多いです。
そのため、昇格の条件が揃っている会社が立会外分売が実施された場合、株価が上昇することがあります。
あまりにも大規模で立会外分売が行われた場合は、浮動株が増えすぎるので下落する場合があります。
立会外分売に応募して短期で売却した場合、多くの場合利益が出るとデータからわかっています。
この場合、ディスカウント率と利益の相関関係がないことが示されています。
第4章 TOB(公開買い付け)
TOB(公開買い付け)は、持ち株数を増やして会社の支配権を強化することです。
TOBの中でも株式を全て買い取って完全に支配下に収め、上場廃止となることをMBO(マネージメント・バイアウト)と呼んでいます。
TOBの対象となる会社と合意が済んでいる場合がほとんどですが、対象会社の乗っ取りを企てた「敵対的TOB」がされる場合があります。
それに対して、会社会社側が行う「カウンターTOB」、後から他の会社が敵対的買収から企業を守る「ホワイトナイト」による友好的なTOB、株式交換によるMBO、特別配当付きTOBなど、様々な形でプレミアムがついたTOBがされる場合があります。
この場合、株価がどんどん吊り上げっていくことになり、会社に高く買い取ってもらえます。
もし何もなければ、TOB価格ー購入価格=利益になるため、買いで入る戦略になります。
MBOが実施されるとき、残った株主からTOB価格で株を買い取るスクイーズアウトが実施されるので、買取応募をせずそれまで待つという選択もあります。
TOBは最低買付け株数に達しないほど応募が少ないと不成立となるため、下落の危機はあります。
第5章 株主優待の本質
企業が株主優待を実施するのは、会社のPRなどもありますが、大きな目的としては「株主数の確保」「株価の維持」です。
単元株を買ってもらい、個人投資家に買い支えてもらうため、小口株主に有利になるように優待を設定することがほとんどです。
最近は、長期株主を優遇する傾向にあります。
この株主優待をイベントとして捉えた場合、原則優待人気の値上がりを利用して、優待権利日の数ヶ月前から買って、優待権利日までに売る戦略をとります。
権利日を跨ぐと、権利落ち日に配当・優待分の暴落が生じるからです。
また現物株と同数の信用売りの両建てを行うことで、優待だけを取る「優待クロス」という方法もあります。
一般信用売りを利用して逆日歩をさけるなど、テクニックは入りますが、優待をノーリスクに近い状態で獲得することができます。
株主優待の新設について、魅力的なものであれば上昇しますが、他社と遜色ないものの場合は上昇しても長続きしません。
逆に株主優待の廃止・解約については、株価が下がることになります。
第6章 新規公開株イベントでの売買
新規公開株(IPO)は、公開価格で株を入手して、上場後に売却する戦略のほか、セカンダリーの売買もあります。
セカンダリーは、上場後の市場での売買を実施するので、IPOの抽選と違い、運は左右しません。
データ・グラフを用いて、IPO銘柄の特徴が以下の通りであると示されています。
- 初値が公開価格に対して高いほど、初値後に株価が上昇しにくい
- 上場前決算の経常利益が高いほど、初値後に株価が上昇しやすい
- 公募売出総数が少なければ少ないほど、初値が上がりやすい
- 売出比率が低いほど、初値が上がりやすい
- ベンチャーキャピタル持株率が低いほど、初値が上がりやすい
- 吸収金額(公募価格×公募売出総数)が小さいほど、初値が上がりやすい
- オファリングレシオ(公募売出総数÷発行株式数×100)が小さいほど、初値が上がるやすい
- 仮条件の上限以外で決まった場合、初値が公開価格を下回りやすい
- 東証2部でのIPOは、初値後に株価が上昇しにくい
- 東証1部・東証REITでのIPOは、組み入れの関係から、上場後1ヶ月のところにピークがある傾向にある
第7章 その他のイベント
株価が動きそうな出来事についてまとめて記載されています。
オリンピック・ワールドカップ関連銘柄は、開幕の数日前にピークをつけ、開催中は下落します。
事件・事故・不祥事などのマイナスなニュースは、パニック的な投げ売りが起きて実態以上に下がるため、リバウンド狙いの買いの戦略が立ちます。
台風上陸が多いと、損害保険会社の支払いが多いのではないかという思惑から、一時的に下げが生じるため、リバウンド狙いの買いの戦略が立ちます。
震災などでは、公共事業に特需があるのではという思惑から、建設・土木銘柄に買いが集まります。
コモディティーによる季節アノマリーを用いて、穀物が秋に底値、灯油は冬に底値になりやすいことを取り上げています。
第8章 イベントを探す
イベントドリブンの醍醐味は、自分でイベントを探し出すことです。
トレード日誌を書いて、後からトレードを思い出し、関連するイベントが見つかるかもしれません。
他のトレーダーの会話からヒントを得られることもあり、投資セミナー・懇親会に参加することで得られる情報があります。
書籍・証券会社のレポート・SNS・論文なども情報源になります。
第9章 ヘッジ
イベントに対して持っているポジションに対して、リスクヘッジを取らないと突発的な事象に巻き込まれて、思いもよらない損失を被ってしまいます。
日経225の先物やETFで、イベントポジションに対して反対のポジションを確保することが主なリスクヘッジとして紹介されています。
ポジションの取り方として、
- 同じ金額の反対ポジションを作る「売買代金ニュートラル」
- 同じ変動幅で反対ポジションを作る「ボラティリティニュートラル」
- 市場平均に対する個別株の感応度を同じにしたポジションを作る「βニュートラル」
があります。
第10章 検証と売買ルール
イベントドリブンは、イベントが株価にどのような影響を与えているかを知ることが検証で大事なのですが、一般的な検証ソフトを利用することができません。
そこで、表計算ソフトを利用することで、検証をします。
検証をしっかりしても売買ルールが適切でなければなりません。
資金量に対して過大なポジションを持ちすぎることが大きな損失につながりやすいため、資金の半分までのポジションに抑えるべきです。
また、イベントシナリオが狂ったときは、きっちり損切りも必要です。
第11章 売買の上達を目指して
売買の上達のために、以下のことが記載されています。
- プライドは上達の妨げになる
- 謙虚さが大事
- 売買日誌をつける
- 相場全体の予想は捨てる
- モチベーションを保つ
最後に「売買べからず集」がまとめられています。
- 資金に対してポジションを大きすぎてはいけない
- 説明のつかないポジションを持ったままにしてはいけない
- 思いつきでトレードしない
- 誤発注のポジションを保持しない
- 相場は自分の都合に合わせてくれない
- 意地商いをしてはいけない
- 投資とトレードを一緒にしてはいけない
- 銘柄に惚れ込んではいけない
- トレードの結果をいつまでも引きずってはいけない
- 無計画なナンピンをしてはいけない
- 休まないでトレードをしてはいけない
- 家族に内緒でトレードしてはいけない
- 大逆転に賭けてはいけない
- 社会正義をトレードに持ち込んではいけない
- 自分のポジションを公開してはいけない
- 他人に安易に売買の相談をしない
- 相場観の議論をしない
- アナリストやエコノミストの言葉をうのみにしない
- 銘柄を教えてもらうことは相場の勉強とは言わない
- 一度にあれこれ手を出さない
- 相場の損失を他人のせいにしてはいけない
- ニュースに振り回されてはいけない
『イベントドリブントレード入門』を読んで今後勉強すべきこと

『イベントドリブントレード入門』で、イベントドリブンの基礎知識について知ることができたと思います。
より深くイベントドリブンについて理解するために、関連書籍を読まなくてはいけません。
イベント投資について、手堅く毎月10万円というワードが気になりましたので、『安定的に利益を出せる 先回りイベント株投資』を読んでみます。
また、アノマリー投資の本も読んでみたいと思ったので、『アノマリ投資 市場のサイクルは永遠なり』を読んでみます。
まとめ
『イベントドリブントレード入門』を書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんがご紹介させていただきました。
投資をしていくためには、まだまだトレーニングが必要ではありますが、少しずつ実践していこうと思います。
より優れた投資家になるために、色々な本を読んでみたいと思います。