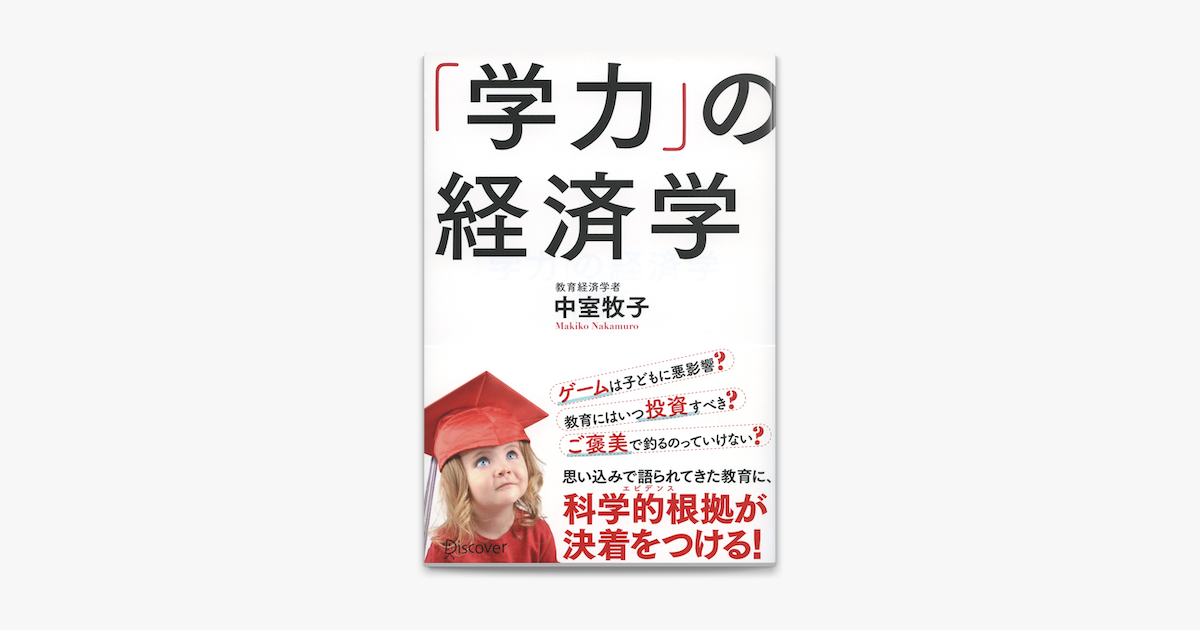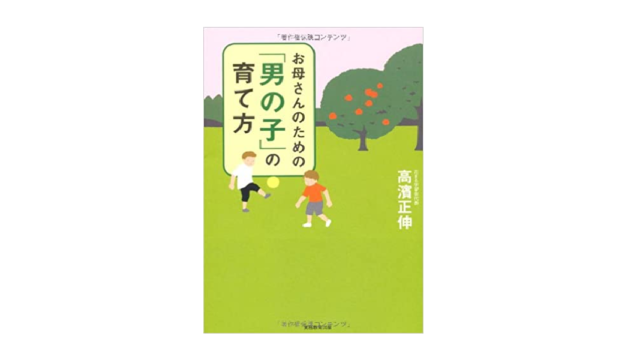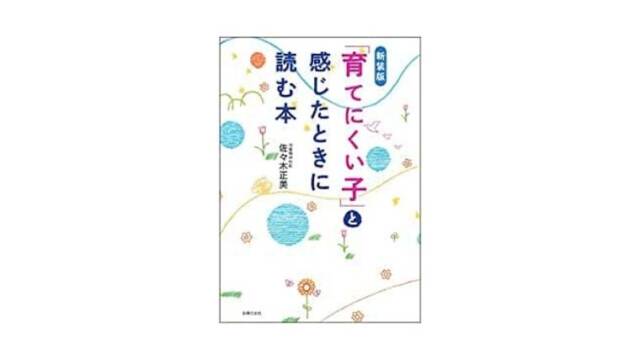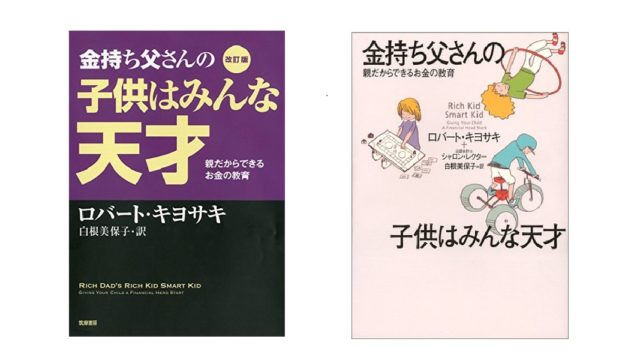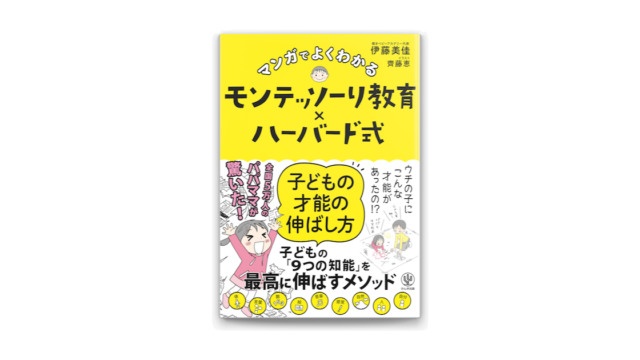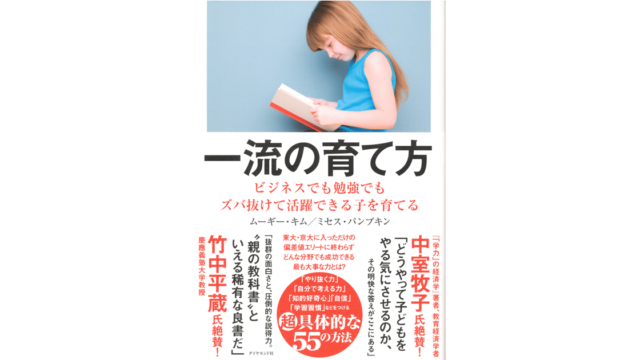子育てをするために、たくさんの本を読んで勉強しています。
読んでいるだけでは記憶になかなか残りにくいため、インプットした知識を整理して、
- 「読んで勉強になったこと」
- 「理解が及ばず、さらに勉強をしなくてはいけないこと」
を感じたままに書き留めています。
書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんがご紹介いたします。
目次
『「学力」の経済学』とは?
| 読みやすさ | |
|---|---|
| 専門性 | |
| 役立ち度 |
- 著者:中室牧子
- 出版社:マイルストーンズ
- 発売日:2018/6/26
- ページ数:203ページ
【目次】
- 第1章 他人の“成功体験”はわが子にも活かせるのか?-データは個人の経験に勝る
- 第2章 子どもを“ご褒美”で釣ってはいけないのか?-科学的根拠に基づく子育て
- 第3章 “勉強”は本当にそんなに大切なのか?-人生の成功に重要な非認知能力
- 第4章 “少人数学級”には効果があるのか?-科学的根拠なき日本の教育政策
- 第5章 “いい先生”とはどんな先生なのか?-日本の教育に欠けている教員の「質」という概念
教育・子育てについて、「教育評論家」「子育てに成功した親」による個人的経験に基づいて、主観的な意見が紹介されることが多いです。
その中でも『「学力」の経済学』は、データに基づき教育を経済学的な手法で分析する教育経済学が紹介されています。
社会心理学の分野でも頻繁に出てくる実験や理論が様々紹介されており、統計学的な根拠などに基づいたとても貴重な1冊です。
「まんがでわかる」版も発売されて、より気軽に読めるようになりました。
『「学力」の経済学』を読むきっかけ

育児について勉強するために色々な本を漁っている中で、東大に合格させた親の話などの一部の成功体験を紹介している本ばかりで、少しウンザリしていました。
科学的根拠に基づく教育提言がなされているものを探していたら本書に出逢いました。

また、林先生が驚く初耳学での特別授業でも取り上げられたこともあり、この本を読んで見たいと思いました。
『「学力」の経済学』を読んで勉強になったこと【3点】

『「学力」の経済学』読んで特に勉強になったことを3点で選んでみました。
- インプット・アウトプットのどちらに褒美を与えればいいのか?
- 周りからの影響をどのように受けるのか?
- 幼児教育に力を入れるべき
インプット・アウトプットのどちらに褒美を与えればいいのか?
本書では、第2章で子どもを“ご褒美”で釣ってはいけないのかについて解説されており、「目先の利益」が「遠い将来の利益」よりもよく見えるため、褒美を与えることを条件つきで良いとされておりました。
条件とは褒美の与え方を間違えなければ良いというものでした。
それはアウトプットにではなく、インプットに褒美を与えることです。
勉強した結果としての「テストの順位の向上」などに褒美を与えるのではなく、「本を読む・宿題をする」などの勉強のきっかけに対して褒美を与えたほうが、学力が高まるという統計結果なのです。
ついつい、「学年順位1桁に入ったら、お小遣いを増やそう」などとしてしまいがちで、そのほうが成功しそうな主観を持ってしまいますが、データでは違うということです。
周りからの影響をどのように受けるのか?
周りから受ける影響を「ピア・エフェクト」といい、外的環境が子どもの学力にどのような影響を与えるか解説されていました。
学力の高い友人に囲まれていれば学力が高まると思ってましたが、あまりにも学力が乖離してしまうことが指摘されていました。
また、習熟度別学級はピア・エフェクトの効果を高め、全体の学力を押し上げるのに有効な政策であるとされていますが、子供の学齢が低い時に習熟度別学級を実施すると、格差が拡大し、平均的な学力も下がってしまうと指摘されています。
子どもが周りからどのような影響を受けるとのかを考えるきっかけにもなりました。
幼児教育に力を入れるべき
学力テストでは計測することができない非認知能力が、人生の成功において極めて重要で、以下のような能力のことを指し、「生きる力」とも表現されます。
- 自己認識
- 意欲
- 忍耐力
- 自制心メタ認知ストラテジー
- 社会的適性
- 回復力と対処能力
- 創造性
- 性格的特性(神経質・外交的・好奇心が強い・協調性がある・誠実)
この非認知能力は、幼児教育を実施することで向上し、特に自制心・やり抜く力(GRIT)を鍛えると良いことが示されています。
自制心は、計画・記録・管理させることで力を伸ばすことができます。
やり抜く力は、能力は後天的に伸ばすことができると思わせることで伸ばすことができます。
『「学力」の経済学』を読んで今後勉強すべきこと

『「学力」の経済学』にて、教育経済学という分野に初めて接したので、より詳しい教育経済学の勉強をしたいと思います。
教育経済学では、以下のことが取り扱われています。
- 教育の経済的効果
- 教育の費用負担
- 教育における効率性と教育計画
- 教育の便益に関する分析
これについて、より詳細に知るために教育経済学の入門書などを読んでみたいと思います。
また、非認知能力について紹介された中で「GRIT」という言葉が出てきました。
これについても、書籍を本屋で見た記憶があります。
GRITについては、FacebookのCEOマーク・ザッカーバーグ氏が成功の鍵の一つとして挙げるなど、注目されている能力になります。
子どものためではありますが、自分のためにも一読して見ようと思います。
まとめ
『「学力」の経済学』を書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんがご紹介させていただきました。
「原因と結果」の経済学、という他の本も出版しており別の機会に読んでみたいと思います。
ここが変だよ「学力の経済学」、という反対意見を唱える電子書籍もありましたので、とても気になっておりますので、購入してみたいと思います。
読みたい本がいっぱいあって、時間が足りなくて困ってますが、1冊ずつ読み進めたいと思います。