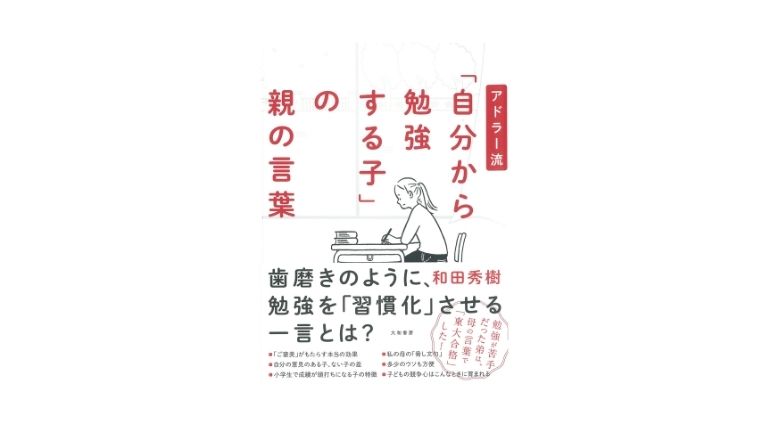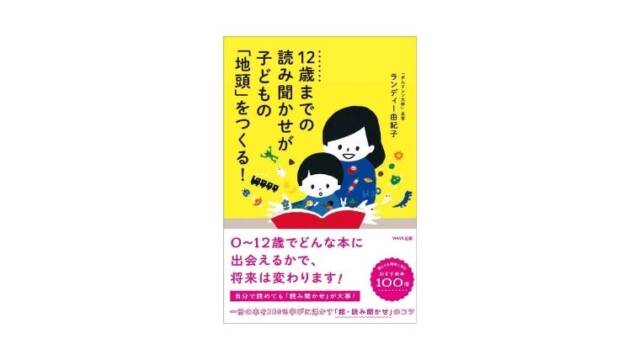子育てをするために、たくさんの本を読んで勉強しています。
『アドラー流「自分から勉強する子」の親の言葉』を読んでいるだけでは記憶になかなか残りにくいため、インプットした知識を整理して、
- 「読んで勉強になったこと」
- 「理解が及ばず、さらに勉強をしなくてはいけないこと」
を感じたままに書き留めています。
とても勉強になりましたので、書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんがご紹介いたします。
目次
『アドラー流「自分から勉強する子」の親の言葉』とは?
| 読みやすさ | |
|---|---|
| 専門性 | |
| 役立ち度 |
- 著者:和田秀樹 (著)
- 出版社:大和書房
- 発売日:2016/6/18
- ページ数:232ページ
【目次】
- 第1章 アドラー流「考える子」を育てる
- 第2章 子どもが自分から机に向かう言葉かけ
- 第3章 何気ない口ぐせが子どもを勉強嫌いにさせる
- 第4章 「自分で考えられる子」は最後に強い
- 第5章 子どもの「劣等感」にどう向き合うか
- 第6章 子どもが失敗したとき、効果的な言葉
- 第7章 親の一言が子どもの人生を前進させる
- 第8章 心が強い子を育てる
『アドラー流「自分から勉強する子」の親の言葉』を読んで勉強になったこと

『アドラー流「自分から勉強する子」の親の言葉』で登場する「アドラー流」とは、親子の関係は対等なものであると考え、子どもが人生の課題に取り組み、乗り越えていくための勇気を与えること(勇気づけ)が大切であることを指しています。
母親の声がけの影響の大きさは計り知れません。
章ごとに重要だと思った箇所についてまとめます。
第1章 アドラー流「考える子」を育てる
【第1章の小見出し】
- アドラ心理学を子育てに生かす
- 人は誰でも成長願望を持っている
- 子どもの能力を引き出そう
- 劣等感を持つことは悪いことではない
- 「勝てた」という経験をさせよう
- 「勇気づけ」をしていた私の母親
- 弟の勉強コンプレックスを見事解消!
- 原因論ではなく目的論で考える
- 「未来志向」で子どもを育てよう
- なぜ子どもを褒めてはいけないのか
- “子どもの関心“に関心を持つ
- 「性格もよくて勉強もできる」子に育てる
- 社会の厳しさを教えることが大切
- 勝つだけではなく、優しくなることを目指す
- 「嫌われる勇気」の本当の意味
第1章では、「アドラー心理学とは何か」ということがまとめられています。
アドラー心理学の最大の特徴は、「人は何かの原因によって行動するのではなく、目的に向けて行動する」と捉えていることです。
その目的は「優越権の追求」という、人間は誰もが他人と競争して勝ちたいという欲求を持っていることから動機付けられます。
そのため、人は放っておいても頑張れる存在なので、親はコーチとなって子どもの能力を引き出すため「未来志向」のアドバイスをすることが求められます。
アドバイスで注意する点は、アドラー心理学では親子は対等な関係であることが望ましいので、「褒める/褒められる」の上下関係を作らず、共感による「勇気づけ」が必要です。
第2章 子どもが自分から机に向かう言葉かけ
【第2章の小見出し】
- 今日は学校で何を教えてもらったの?
- ここまでの問題をやってみよう
- 他の子よりできるんだから、もっと難しいのやってみよう
- ゲームは1時間までにしようね
- 〇〇ができるようになったね。すごいね。
- 自分で読んでみようか?
- その本の内容をお母さんにも教えて
- テストで成績が上がったら買ってあげるね
- 友達にも勉強を教えてあげるといいよ
- 親の学歴は関係ないよ
- お父さんのおじいちゃんは勉強ができたんだよ
第2章では、子どもが自ら勉強を始めるための言葉がけがまとめられています。
子どもの成長したいという気持ちを後押しするため、
- ここまでの問題をやってみよう
- 他の子よりできるんだから、もっと難しいのやってみよう
- 〇〇ができるようになったね。すごいね。
- 自分で読んでみようか?
- その本の内容をお母さんにも教えて
などの声がけを用います。
「テストで成績が上がったら買ってあげるね」などのアメの使い方については賛否がありますが、「本書では努力すれば認めてもらえる」という実感を得ることができるようになると前向きに捉えています。
第3章 何気ない口ぐせが子どもを勉強嫌いにさせる
【第3章の小見出し】
- 全然できていないじゃない!
- 次に勉強をサボったら外出禁止だよ
- 遊びより勉強のほうが先でしょ!
- どうせ、またサボってゲームやるんでしょ?
- なんで汚い字で書くの?
- 算数は得意なはずなのに…
- もっと勉強しなさい
- いつになってもできないな
- 勉強だけできてもダメだよ
- 地元の大学に入れれば十分
- 大きくなったらわかるよ
- それは、まだ難しいと思うな
- お前の考えは間違っている!
第3章では、子どもを勉強から遠ざけてしまう「ダメな言葉がけ」がまとめられています。
「結果を褒めて、行動を叱る」ように心がけ、「こうすればできるようになるよ」とアドバイスを添えるようにしなくてはいけません。
アドバイスをする際には、決めつけをすることなく、未来に目を向けて「どうすれば勉強ができるか」を一緒に考えていく必要があります。
第4章 「自分で考えられる子」は最後に強い
【第4章の小見出し】
- どうしてスマホが必要だと思うの?
- 仲間はずれを恐がる必要はないよ
- 言いたいことはきちんと言おうね
- 本当のこと話してくれてありがとう
- 〇〇してくれてありがとう
- 欲しい物があったらプレゼンしてみて
- どんな人も、社会の役に立っているよ
- あなたは、どう思う?
- テレビが正しいことを言っているわけじゃないよ
- 先生の言うことが正しいとは限らないよ
- あとで聞くね
- 〇〇君のいいところはどんなところ?
- どうすればいいか、一緒に考えようか
第4章では、厳しい社会で生きていくため、自分の頭で考えて意見をいう力を育む言葉がけがまとめられています。
理由を考えさせて言葉にする訓練を日頃から積めるように、考えさせる機会を多く与えます。
考える能力・伝える能力・共感能力などが鍛えられ、自信を持った発言ができるように導きます。
第5章 子どもの「劣等感」にどう向き合うか
【第5章の小見出し】
- 勉強のやり方を変えてみようか
- 先生の教え方が悪いだけだよ
- あなたは〇〇に関してはホントにすごいね
- お姉ちゃんより、できたね!
- 足が遅くても問題ないよ
- (よくないことがあっても)大丈夫だよ
- あとで合格すればいいんだよ
- こんな人、バカでカッコ悪いよね
- 他の子からどう思われても気にしなくていいよ
第5章では、「優越権の追求」から劣等感を抱きやすいため、劣等感のケアの言葉がけがまとめられています。
劣等感自体は誰しもが持つので否定するものではなく、成長の糧にすることができるのかが大事になります。
劣等感を克服するためには「勝つ経験」「不安の払拭」が必要です。
第6章 子どもが失敗したとき、効果的な言葉
【第6章の小見出し】
- 次、頑張ろう
- ママが間違っていたよ
- 相手に言うと傷つくよね
- 間違える場所がわかったね
- (失敗したことについて)次はどうすればいいと思う?
- まずは謝ることが大事だよ
第6章では、子どもが失敗した際に親がするべき声がけがまとめられています。
失敗を叱るのではなく、「失敗は1つの経験」だと認めて未来に向けたアドバイスをすることが求められます。
声がけも大事ですが、子どもが失敗したときの対処方の手本として親は振る舞わなければなりません。
第7章 親の一言が子どもの人生を前進させる
【第7章の小見出し】
- ママとパパはあなたの味方だよ
- 何になりたいの?
- 勉強できないと食べられなくなるよ
- やっぱり東大はすごいね
- 医者は立派な仕事だね
- 東大を出ておけばとりあえず困らないよ
- 世の中なんて、いつかは変わるよ
- 挑戦しなくていいの?
- 勉強しないと、将来どうなるかな?
- グリーン車に乗ってみよう
- お父さんと一緒に散歩に行こう
第7章では、子どもの将来の目標を描くための声がけがまとめられています。
子どもが道を謝ったり迷ったりするのは、目標が明確でないからです。
そのため、子どもと「将来の夢・職業」などのヒントを与える「視野を広げる言葉がけ」をして、自分の進むべき道・目標を自ずと獲得させる必要があります。
第8章 心が強い子を育てる
【第8章の小見出し】
- 負けても当たり前だよ
- いじめられるのは性格がいい子らしいよ
- できないんだったら答えを見てもいいよ
- こういう言い方をしたほうが得するよ
- 自分は自分のままでいいんだよ
- 惜しいね。今度は勝とうね
- できないことがあっても問題ない
第8章では、自分を保って強い心を持つための言葉がけがまとめられます。
親に対して弱音を吐きやすいように、肯定感・安心感を与えます。
競争心を支えるする親の姿勢が示されています。
『アドラー流「自分から勉強する子」の親の言葉』を読んで今後勉強すべきこと

『アドラー流「自分から勉強する子」の親の言葉』では、親が子どもにしてあげられることの1つとして「言葉がけ」を学ぶことができました。
本書は、和田家における1つ方針であるので、多くの子育て方法を集約ではありません。
そこで、200人を超える東大・京大・早慶を中心とした突出したリーダシップを発揮してさまざまなグローバル企業に進んだ学生に、両親に教育を振り返って感謝している点・直してほしかった点のアンケート結果が紹介されている『一流の育て方』を読んでみます。
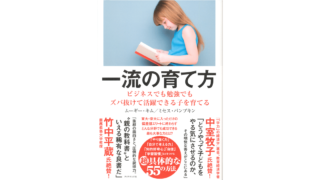
また、史上最年少プロ棋士・藤井聡太さんが幼児期に受けた教育として一躍脚光を浴びている「モンテッソーリ」教育を学ぶことができる『モンテッソーリ教育×ハーバード式 子どもの才能の伸ばし方』を読んでみます。
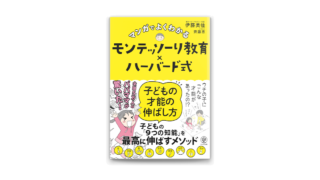
まとめ
『アドラー流「自分から勉強する子」の親の言葉』を書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんがご紹介させていただきました。
ですが、まだまだ育児について深く学んでいかなければならないと思いました。
そのため、いろんな本を読んでいきたいと思います。