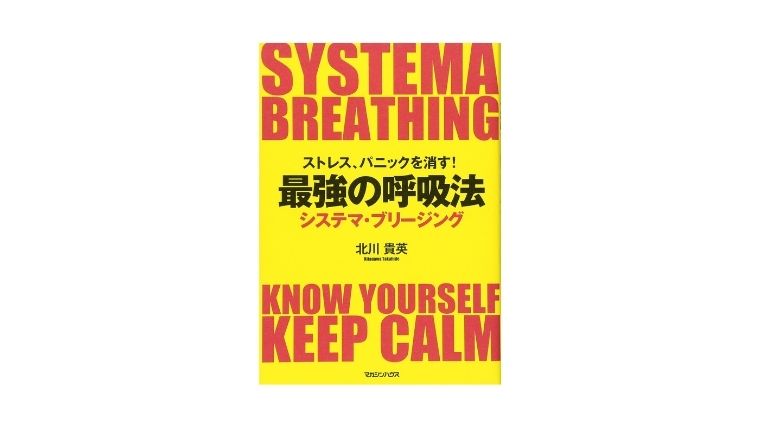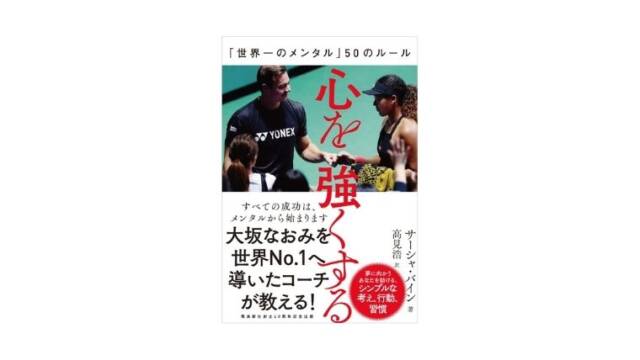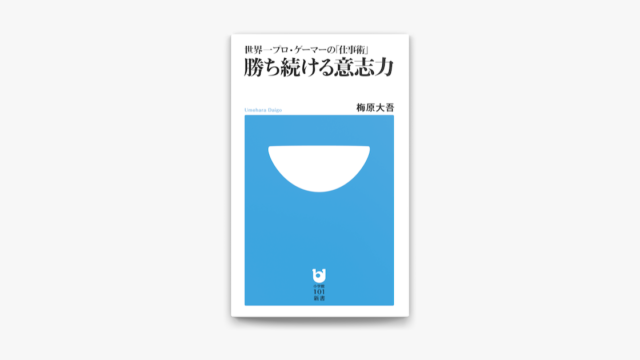適切なマインドを保ち、健全に生きていくためには、メンタルヘルスについて意識的に学んでいく必要があります。
たくさんの本を読んで勉強していますが、『最強の呼吸法 システマ・ブリージング』を読んでいるだけでは記憶になかなか残りにくいため、インプットした知識を整理して、
- 「読んで勉強になったこと」
- 「理解が及ばず、さらに勉強をしなくてはいけないこと」
を感じたままに書き留めています。
とても勉強になりましたので、書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんがご紹介いたします。
目次
『最強の呼吸法 システマ・ブリージング』とは?
| 読みやすさ | |
|---|---|
| 専門性 | |
| 役立ち度 |
- 著者:北川貴英
- 出版社:マガジンハウス
- 発売日:2011/11/17
- ページ数:207ページ
【目次】
- 1 何故あなたは恐怖を感じるのか?
- 2 恐怖が生む三つの足かせ
- 3 恐怖心を消すには「ブリージング」せよ
- 4 最強の呼吸法 基礎編
- 5 最強の呼吸法 日常への応用編
- 6 現代を生き抜く護身術編
- 7 ロシア武術「システマ」とは?
『最強の呼吸法 システマ・ブリージング』は、ロシアの特殊部隊が採用している武術システマの呼吸法を学ぶことができます。
戦場での恐怖から来るパニックやストレスを消す為の呼吸法を有効活用し、日常生活でも応用出来るものが紹介されています。
著者の北川氏は、日本人では二人目となるシステマの公認インストラクターに認定され、防衛大学課外授業や公立小学校など公的機関での指導実績もあります。
『最強の呼吸法 システマ・ブリージング』を読んで勉強になったこと

『最強の呼吸法 システマ・ブリージング』では、現代を生き抜く為の、癒しを超えた攻めの呼吸が学べます。
1 何故あなたは恐怖を感じるのか?
恐怖心はさまざまな形で感情を掻き乱し、正常な判断・行動力を失わせる原因になっています。
科学の進歩によって昔に比べて格段に安全な環境に住んでいるにも関わらず、「豊かさ」を手に入れたことでそれを失う恐怖を抱えてしまいます。
恐怖の感情を突き詰めていくと、「死への恐怖」と繋がっているため、恐怖心と完全に縁を断つことはできません。
そうであれば、共存してしまう他なく、恐怖心のマイナス面を抑えてプラス面を引き出すことで恐怖心を味方にすれば良いのです。
そのためには、緊張しすぎでもリラックスしすぎでもない、適度位バランスの取れた状態が必要です。
2 恐怖が生む三つの足かせ
恐怖心が「肉体・思考・精神」にどんな影響を与えるのかを知っておくことは、恐怖心のマイナス面を抑えてプラス面を引き出す一歩になります。
肉体への足かせとして、恐怖心は筋肉を緊張し、呼吸が浅くなります。
思考への足かせとして、パニックを起こしてしまい、思考停止を起こしてしまいます。
精神への足かせとして、動揺したり、逆に興奮したりしてしまいます。
これらの恐怖心への反応は、「萎縮・攻撃・無反応」で、恐怖心と折り合いをつけるために知らず知らずのうちに身につけてきた技術です。
まずは、この無意識の反応を認識することから始めます。
感情に支配されるうちは、必ずそのマイナス面が大きく膨れ上がって悪い結果をもたらす可能性がどんどん高まっていくためです。
3 恐怖心を消すには「ブリージング」せよ
【基礎のブリージング】
- 鼻から息を吸います。
- 口を軽くすぼめて口から息を吐きます。
吸い過ぎでもない、自分が快適に感じる深さで呼吸をしてください。
胸式や腹式にこだわらず、自然に空気が出入りするのに任せます。
ブリージングには、体を本来あるべき状態へと回復させる働きがあります。
苦痛の記憶・未来へのネガディブな予想ばかりが膨らむことで恐怖心が生まれ、筋肉が緊張することで実在のものに変化していまい、さらに一段と緊張するように負のスパイラルが起きます。
このスパイラルを断ち切るために、筋肉をリラックスさせる必要があり、「呼吸」が鍵を握っています。
自分の意思でコントロールできる唯一の生命活動で、静かで深い呼吸で脈拍は遅くなり血圧は低下します。
【エクササイズ】
- 座った状態で、鼻から限界まで息を吸います。
- 息を吸いきったまま、全身の状態を観察します。
- 少し苦しさを感じたら呼吸を再開し、体を元の状態に回復させます。
- 口から息を限界まで吐ききって全身を観察し、吸いきった時とどう違うか、確認します。
- これを何度か繰り返し、気づいた違いを全てリストアップします。
吸う息が心身を緊張させ、吐く息には弛緩をもたらす傾向がわかります。
緊張状態の時は、普段とは違う何らかの変化を生じているはずなので、理解することが大事です。
「恐怖の源は未知である」ので、自分の強さ・弱さの限界を知らないといけません。
4 最強の呼吸法 基礎編
ブリージングは、「鼻から息を吸い、軽くすぼめた口から息を吐く。」だけです。
何らかのストレスを感じたら、いつもより多めに空気を出し入れるするつもりで呼吸をします。
心身を活性化させる強化版の「バーストブリーシング」が紹介されています。
【バーストブリーシング】
- 息を吸いながら肩から拳まで両腕全体を力いっぱい緊張させます。
- 両腕の緊張を保ったまま、鋭く口から吐き、鼻から吸う小刻みな呼吸を行います。
- 緊張が限界に達したら鼻からゆっくりと息を吸い、口から吐きながら両腕をリラックスさせて終了です。血流が流れ込むことで、腕に軽いピリピリ感や温度の上昇が感じられるでしょう。
短い時間でたくさんガス交換を行うためのブリージングで、体内の圧力を一定に保つことで姿勢を崩すことなくガス交換ができます。
これは「システマ4原則」を体現するために重要になります。
- 呼吸をし続ける(キープ・ブリージング)
- リラックスを保つ(キープ・リラックス)
- 正しい姿勢を保つ(キープ・ポスチュア)
- 動き続ける(キープ・ムービング)
5 最強の呼吸法 日常への応用編
日常生活にはあらゆるストレスが満ちており、ブリージングで対処することで揺るがぬ強さを心と体で養うことができます。
- スッキリ目覚めるブリージング
- 抜けない疲れを癒すマッサージ
- 満員電車を快適に過ごすコツ
- 怒りを鎮めるエクササイズ
- 「あがり」を解消するエクササイズ
- 古傷とトラウマへの対処法
- デスクワークの疲労回復
- 柔軟な思考を取り戻すエクササイズ
- 会議室で発想を転換する方法
- 活力を引き出すエクササイズ
- 突発なトラブル、パニックに対するブリージング
- 対人関係に活かすブリージング
- 自分の間合いを確認する
- 組織力を高める「シェアリングタイム」
- 恐怖心を克服するマッサージ
- 寒さから身を守るブリージング
- 悪酔いから身を守るブリーシング
が記載されています。
この中でも「デスクワークの疲労回復」が重要だと思いました。
【リフレッシュするブリージング】
- 息を吸いながら全身の筋肉を緊張させます。
- そのまま息を止め、筋肉を硬直させたまま全身をチェックします。力が抜けてしまっているところを探し、見つけ次第全て力いっぱい緊張させていきます。
- 体の隅々まで緊張しきったら、ゆっくりと息を吐きながら全身をリラックスさせます。1回で全力を尽くすつもりでやりましょう。これを1〜3回ほどやります。
- 終わるときには、エクササイズの余韻を感じるようにします。こうしてリラックスの感覚を体と意識に染み込ませると、リラックスした状態を長持ちさせることができます。
デスクワークが続くと長時間同じ姿勢でいるため、筋肉の緊張や血流の停滞などから疲労感が生じてしまい、集中力の低下・思考の停滞を招いてしまいます。
職場でも目立つことなくできるエクササイズなので、簡単に導入することができます。
6 現代を生き抜く護身術編
護身術と聞くと、悪漢を撃退する技術というイメージが一般的ですが、日常に潜む脅威はそれだけではなく、病気・事故・災害などもあります。
侮れない日常の脅威として「転倒」が挙げられています。
システマでは「ローリング」と呼ばれる受け身が行われています。
地面に衝突するときに、ブリージングによって体を柔らかく保つことで衝撃を分散させ負傷を防ぎ、さらに肉体的苦痛だけではなく恐怖心に対処する意味合いもあります。
倒れ方・立ち上がり方ともに決まった形はなく、柔道のような床を手でバンと叩く動作はやりません。
7 ロシア武術「システマ」とは?
4原則以外にも、システマについて知っておくべきことがあります。
システマを相手の殺傷を目的とせず、相手も自分もできるだけ傷つけることなく、衝突を終わらせることを目指します。
システマのトレーニングにおける戒めを1つ挙げるとしたら、自分や仲間を傷つけてしまうことです。
厳しく締め付けるのではなく、自由で和やかな雰囲気を大切にするのは、学習能力を最大限開花させ、生き抜く能力を効率良く伸ばすためです。
『最強の呼吸法 システマ・ブリージング』を読んで今後勉強すべきこと

『最強の呼吸法 システマ・ブリージング』では、システマの呼吸法を通じたメンタルコントロールについて学べました。
これらシステマについて、またメンタルケア・コントロールについてもっと学びたいと思いました。
同じ著者によるシステマの呼吸術を学べるま『ストレスに負けない最高の呼吸術』を読んでみます。
また、システマを用いたリラックス方法を学べる『最強のリラックス システマ・リラクゼーション』を読んでみます。
まとめ
『最強の呼吸法 システマ・ブリージング』を書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんがご紹介させていただきました。
禅ばかり勉強していたので、システマの考え方を学べたのは新鮮でした。
メンタルケア・コントロールをしっかりして、ストレス耐性を高めたいと思っています。