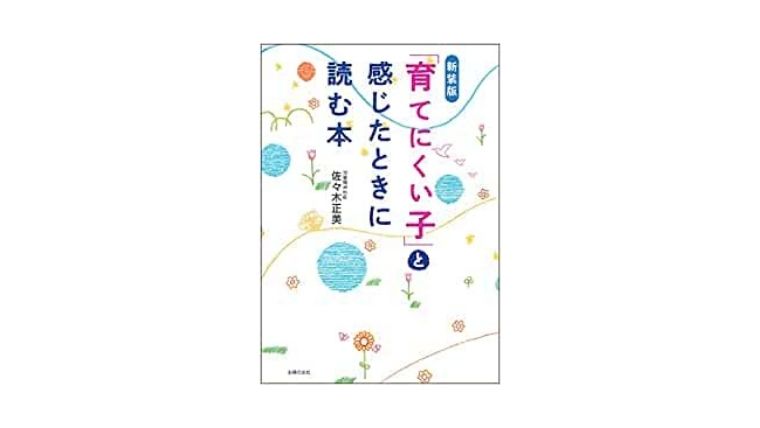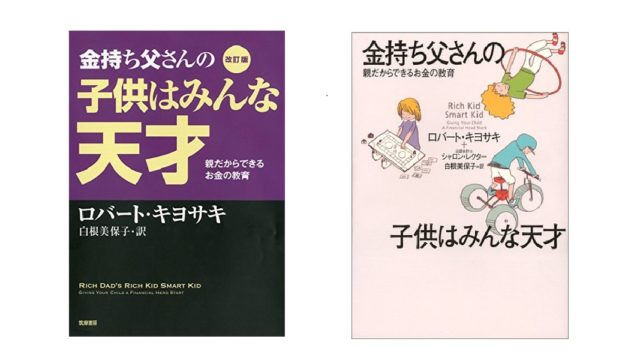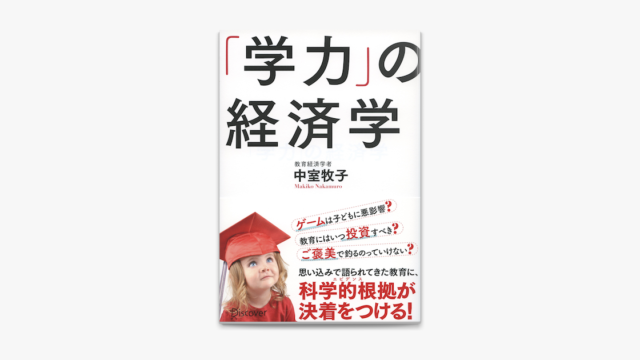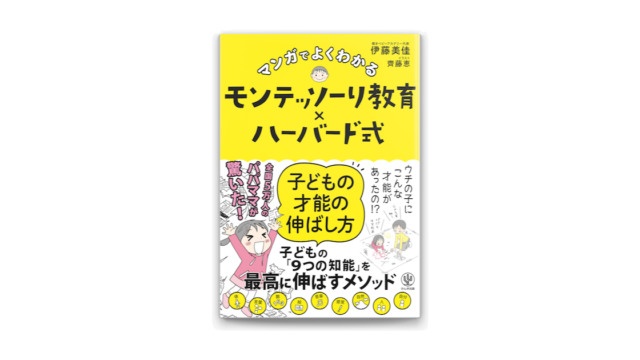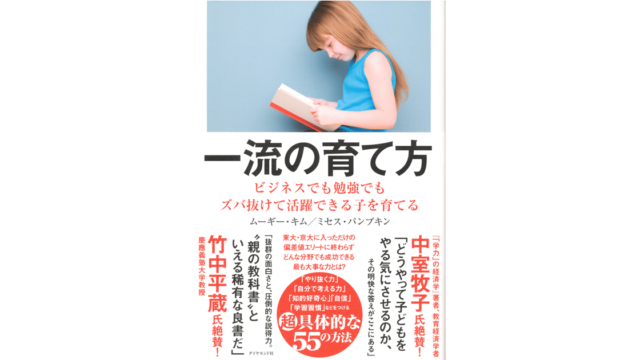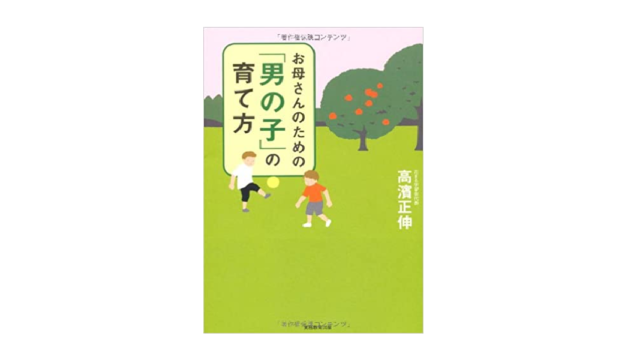子育てをするために、たくさんの本を読んで勉強しています。
『「育てにくい子」と感じたときに読む本』を読んでいるだけでは記憶になかなか残りにくいため、インプットした知識を整理して、
- 「読んで勉強になったこと」
- 「理解が及ばず、さらに勉強をしなくてはいけないこと」
を感じたままに書き留めます。
とても勉強になりましたので、書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんがご紹介します。
目次
『「育てにくい子」と感じたときに読む本』とは?
| 読みやすさ | |
|---|---|
| 専門性 | |
| 役立ち度 |
- 著者:佐々木正美(著)
- 出版社:主婦の友社
- 発売日:2008/6/27
- ページ数:192ページ
【目次】
- 第1章 悩み多き時代の子育てだからこそ
- 第2章 わがままな子、心配な子と言われて
- 第3章 集団生活の入り口で
- 第4章 上の子の気持ち、下の子の気持ち
- 第5章 ママだって傷ついている
雑誌「Como」で4年半にわたって続いてきた「子育て悩み相談室」に寄せられた子育ての悩みとそれに対する佐々木正美先生のアドバイスが記載されています。
NHK「おはよう日本」でも紹介されるなど、子育てに悩む方の助けになっています。
『「育てにくい子」と感じたときに読む本』を読んで勉強になったこと

『「育てにくい子」と感じたときに読む本』は、悩み相談に対する先生の答えが記載されています。
それ以外にもコラムが記載されており、子育ての悩みにしっかりフォーカスされています。
章ごとに重要だと思った箇所についてまとめます。
第1章 悩み多き時代の子育てだからこそ
子育てに悩んでいる人の特徴を、著者の佐々木正美先生は以下のように示しています。
子育てが難しいと思っている人は、家庭の中だけではなく、地域社会の人、学校や幼稚園のお母さん同士の関係、実家の親きょうだい、親戚関係、そういった人間関係が、うまくいっていないことが少なくないのです。うまくいっていないわけではなくても、他者との関係の中でリラックスできていない人が多いのです。
引用:『「育てにくい子」と感じたときに読む本』,p12 12〜15項
逆に人と積極的に関わる人は、価値観が多様になるので、自分の子とよその子を比べて悩んだり落ち込んだりすることが少ないようです。
著者が気にしていることは、親の前で手のかからないフリをしてしまう子です。
家庭で安心できないために欠点をさらけ出すことができず、そのような子の多くが成長して反社会的・非社会的になることがわかっています。
手がかかるということは、子どもにとって良い環境を整えられているといる証です。
注意しなくてはいけないのは、「過干渉な親」が現在多いことです。
過干渉は自立の芽を摘んでしまいますが、過保護は自分は大事にされているという承認のもとにいきいきとした子に育ちますので、過保護は勧めらています。
第2章 わがままな子、心配なこと言われて
わがままな子というのは、信頼感があるからこそ激しい感情をぶつけます。
感情のコントロールが弱い子は、往々にして自己肯定感が低くなってしまいがちです。
自己肯定感を高めるため、「あなたはあなたのままでいいんだよ」という親からの需要が欠かせません。
- Q.ささいなことで泣きわめき続けます
- A.お母さんもつらいでしょうけれど、いちばん苦しいのは子の子なのです。救えるのはお母さんだけですよ
泣きわめいている時は、お母さんがなんとかしてくれるんじゃないかと期待して、必死に泣いて訴えています。
可能な範囲でその願いを叶えて、無理であれば手間・時間をかけてゆっくり言葉で説明し、子どもの気持ちに寄り添いましょう。
感情をコントロールする力を身につけていくためには、母親と感情を分かち合う体験を積み重ねることから始まります。
1番大事なのは「喜びの共有」で、「子どもが喜びことをしてあげることが親の喜びなのだ」ということが伝わっている子は、早い時期から感情のコントロールができるようになります。
- Q.母親に対してわがまま大爆発の三男
- A.手がかかる子や、要求の多い子は蘭や菊の花なんですよ。手をかければ見事な大輪の花を咲かせます。
お母さんが自分のために動いてくれるということにこだわって、受け止めて欲しいという欲求が働いています。
他のきょうだい・お父さんに頼んだことに腹が立ってしまうのでしょう。
「お母さんは、お願いをちゃんと聞いてくれるのだ」と理解できれば、逆にお母さんの願いを聞いてあげようと思えるようになります。
十分甘えさせることが、自立にもつながります。
- Q.感情が爆発すると1時間以上泣き止まない
- A.この子はお母さんといろいろなことがしたいんですね。でも思いつかない。だから泣いてダダをこねるんです。
もっとお母さんに甘えたいのに、上手に甘えられない場合があります。
してほしい遊びを色々やってあげることが大事です。
泣き続けてしまうことは、「抱っこ」をしてあげるのがいいと勧められています。
- Q.保育園に迎えに行っても1時間以上帰ろうとしない
- A.最後の最後までしからないんですよ。どんなに待ってあげても最後に怒ったら意味がありません。
お母さんと遊び足りていない子は、自分と遊んでくれる保育園から帰りたがりません。
家でに十分遊んであげると、保育園から帰るのを惜しまなくなります。
- Q.ほかの子のことが気になってしかたがない
- A.いい子になろうとがんばりすぎています。あまりほめないこと、しかりすぎないこと、評価しないことを心がけて
保育園でお友達や周りの目を気にする場合、家の中ではお母さんの目も気にしています。
お母さんにほめられることに敏感になりすぎているので、多少ほうっておく必要があります。
薬で容量を守らないと副作用が出るように、適量に褒めなければなりません。
- Q.本当は優しい子なのに、カッとなると手が出てしまう
- A.心が満たされない子は攻撃的になります。「乱暴してはいけない」と言うよりも甘えさせてあげることの方が大事です。
親に伝えたいこと・わかってほしいことがあるのに臆病で言えないため、乱暴になってしまいます。
臆病で自信をなくし、欲求不満からも攻撃的になってしまいます。
甘えさせてあげて、心を癒してあげる必要があります。
- Q.乱暴、すぐどなる、友達に怖がられる息子
- A.このお母さんはわかっていらっしゃる。どならない子に育てたければ親自身がどなるのをがまんしなくては
子どもではなく、親から怒らなくなることから始めなくてはいけません。
「これはダメ」ではなく「こうするのがいいんだよ」と短い言葉で具体的に教えてあげましょう。
第3章 集団生活の入り口で
他者との関係を作る前に、2〜3歳ごろまでには「親との関係」をしっかり作っていく必要があります。
親との基本的な信頼感で人間関係の基礎を構築することで、先生・友達などを信頼できます。
子どもと一緒にいる時間も大事ですが、質の高い親子時間が送れているのかが重要です。
- Q.消極的なのは、親の育て方で悪かったせい?
- A.過保護とは「子どもが望むこと」をしてあげることです。この子の望みは集団で遊ぶことなのでしょうか?
幼稚園・保育園などで集団に溶け込める年齢は4歳ほどからで、それまでは集団で遊ぶのが苦手でも当たり前です。
また、子どもが集団で遊びたいと思っていないのに、過干渉に「こうなってほしい」と押し付けている場合があります。
子どもがやってみたくなるのを、親は見守ってじっと待てばいいのです。
どうすればいいのかは、育児書ではなく我が子に教えてもらいましょう。
- Q.幼稚園が怖くて行けなくなってしまった
- A.心の傷が小さなPTSDとして残ったのです。つらい記憶を忘れるためには友達と楽しく遊ぶことがいちばんです。
子どものSOSを受け入れられる親でなければいけません。
幼稚園だけではなく家にお友達を呼んであげたり、親が一緒に遊んであげてもいいです。
子どもが「心に負った傷」を忘れるためには、友達と楽しく遊ぶことがいちばんです。
- Q.1人遊びが好きなのは小さいころ遊んであげなかったせい?
- A.子どもと遊ぶのが苦手なお母さんほど家に他人を入れたほうがいい。子どもは本来、誰かと遊ぶことが大好きなのです
幼少時代に「友達と遊んで楽しかった」という経験は人間が健全に育っていく上で絶対に必要なことです。
しかし、家庭内の人間関係が決まったパターンになりがちで、おもちゃ・ゲームも充実しているので、1人で遊べる環境が整っています。
外で自由に遊べる場所がなくなって、友達と自由に遊べることが制限されています。
- Q.幼稚園で話せなくなってしまう娘
- A.緘黙の子には感受性の鋭い子が多いです。だから親の期待を察知してしまいます。大事なことは十分に甘えさせてあげること
緘黙症とは、「言葉や知能に問題がないにもかかわらず、話すことができない」というものです。
能力が高く感受性が鋭い子に多く見られますが、家庭で十分安心できていない子ほど外で話せなくなります。
子どもをリラックスできる環境づくりが大事です。
- Q.「学童クラブに行きたくない」と言うのはなぜ?
- A.保育園と学童クラブは違います。小学生になったら、家庭でのやすらぎがさらに重要になるのです。
保育園には「家庭のかわりに子どもが生活する場」という役割があり、1対1の関わり合いがあります。
学校や学童クラブは、1人の先生が集団に勉強を教えるなど「1対多」の関わりです。
そのため、家庭的なくつろぎが足りていない場合があるので、「食事・睡眠・就寝」で十分な関わりが必要です。
- Q.友達ができない、思ったことが言えない
- A.どんなに不安であろうとも「きみはそのままでいいんだよ」という親の姿勢を崩してはいけませんよ
友達をつくることを焦ってはダメで、安心して話すためには相手を信頼しなくてはなりません。
人に対して安心できない子ならば、親自身に対する安心感・信頼感を培っていく必要があります。
気心の知れた親族などがいるのであれば、夏休みなどで泊まらせることで、親以外とのコミュニケーションを練習してみましょう。
- Q.落ち着きがなく忘れ物も多いのですが…
- A.集中できない子、忘れ物の多い子は「好きなこと」に熱中し集中する力がある。得意なことを見つけ伸ばしてあげましょう
忘れ物や落ち着きのなさと「しつけ」はまったく関係がありません。
単に「大人が集中してほしいと思っていることに集中していない」というだけのことです。
「我を忘れて夢中になれる」という力は、教えて学べるものではない、素晴らしい才能なのです。
弱い部分を補強するのではなく、得意な部分を伸ばす発想で、先生にも協力してもらえるようにお願いしましょう。
- Q.ひっこみじあんの息子が心配です
- A.人に対して構えすぎるのは現代人に特徴的な傾向です。まずは親が、家庭内の中でリラックスできたらいいですね
親が神経質になりすぎです。
「選ぶ・決める」を練習するとして、図書館で「あなたの好きそうな本を3つ見つけてきたから、この中から1つ選んでご覧」と、少ないものの中から選ばせてあげるといいです。
- Q.忘れ物が多く片付けられない長女を厳しくしかってしまう
- A.手にかかる子には十分手をかけましょう。母親に助けられて育った子は他人を信じ、他人をたいせつにできる子に育ちます。
「この子をちゃんと育てられるのは自分だけ」という静かな誇りを持って育てましょう。
そうすることで、人を信じられ、人を大切にできる強さを持った、優しい人になれます。
親が必要な場面にのみ手を貸し、丁寧に教えながら子どもを導いてあげましょう。
第4章 上の子の気持ち、下の子の気持ち
きょうだいを同じように育てる必要はありません。
大事なのは、きょうだいが何人いても「1対1の時間」を欠かさないようにして、一人っ子の時間を与えることです。
- Q.毎日繰り返されるきょうだい喧嘩がイヤ!
- A.きょうだい喧嘩はスポーツです。良いも悪いもない。親が下手に価値判断すると必要以上にこじれるだけです
親の役目は試合終了を告げることだけで、介入も仲裁も無用です。
どちらかが泣いた時点で勝敗は決まりますから、泣き声が聞こえた瞬間に「はい、もうおしまい」と声をかけるだけです。
ラグビーの試合終了時は「ノーサイド(敵も味方もない)」言いますが、きょうだい喧嘩もその精神です。
きょうだい喧嘩の素晴らしさは「自然な仲直り」ができ、「ごめんなさい」がなくても人間関係が修復できる点です。
- Q.3人に物を買ってあげるのは難しい
- A.物の与え方は、各家庭のルールを決めて。私自身は、がまんさせることばかりが必ずしもいいことだとは思いませんよ。
人間は、人と同じものが欲しくなるもので、きょうだいでも同じです。
しかし、無限に買い与えることは不可能なので、親が「我が家の方針」を決めることは大事だと思います。
- Q.姉が弟のジャマばかりしているなんて
- A.上の子が下の子を思いやれないのにはどうしようもない理由があるのです。まず上の子をたっぷり思いやってあげて
上の子が下の子が可愛がられているのに対して、やきもちをやいたり、腹いせに邪魔をしたり、邪険に扱ったりするものです。
「まずはお姉さんが先ね」などと優先してあげると、上の子は「弟が先でいいよ」というようになります。
- Q.意地悪な兄を冷静にしかるなんてできない
- A.乱暴は満たされていない心の表れです。たたき返し、けり返しても、乱暴にさらに拍車がかかるだけです。
子どもの自尊心を傷つけるような叱り方はいけません。
上の子に「たたいてはいけない」と教えたかったら、お母さん自身が叩く事をがまんしなくてはいけません。
もしも、親が間違った叱り方をした場合は、しっかり謝ることで子どもの自尊心は救われます。
- Q.上の子をかわいいと思えないのです
- A.かわいがれば、かわいい子になりますよ。逆に、「かわいい子になって」と願いすぎると、かわいくない子になるのです
下の子に手がかかかると、上の子にはできるだけ手をかけたくないという気持ちになることもあります。
上の子だってまだ幼いのに、「早くお兄ちゃんらしくなってね」と要求してしまい、欲求不満でいっぱいになってしまい、「退行」「攻撃性」といった形で表に現れてきます。
そうならないためには、「上の子優先」で育てる必要があります。
第5章 ママだって傷ついている
幸せに見える人は、必ず誰かを幸せにしている人です。
子どもを幸せにすることで、親自身が幸せになっていくのです。
逆も然りで、夫婦関係が良いと、子どもとの信頼関係も良好です。
- Q.怒り出すと歯止めが効かなくなる自分がイヤ
- A.自制心や自立心が育つのは幼児期前半。親にゆったり見守られて育った子は、自制心・自立心の強い大人になります
幼児期前半(3〜4歳)に自制心・自立心が育まれるが、うまくできないことが多いです。
自制心をもてない親は、自制心をもてない子を育ててしまいます。
そのため、親はゆったり見守ることが大事です。
- Q.離婚したことで子どもが寂しい思いをしているが…
- A.大事なことは今の生活に満足すること。子どもの笑顔を見てお母さん自身も幸福になれるといいですね
「子どもが喜ぶことをしてあげることが、自分の喜びなのだ」という気持ちになれる時間をつくることが大事です。
喜びを分かち合う経験は非常に大切で、それが幸せに繋がります。
- Q.顔の大きな娘を見るのがつらい
- A.苦しくつらい日々を歩んできたのですね。心の傷を克服していくためにも自分を認め、幸せにしてあげましょう
親が幼い頃に自己肯定感を育ててもらえなかった場合、我が子を無条件に愛することができずに苦しんでしまうことがあります。
家族を幸せにすることで自分が幸せになり、それが自己肯定感の育て直しの1つになります。
- Q.自分の母を許すことができない
- A.人間関係に不満と絶望を感じている人は、人に優しくはなれないのです。不足した愛情を補ってください
乳児期に愛情を受容できなかった場合、人として成熟することができません。
親に代わる人に、愛情を注いでもらうことで成熟することができます。
- Q.次女に対して大人気なく怒る夫を変えたいが…
- A.ご主人とお子さんがぶつかり合うとき、間を取り持てる人間はあなただけです。人としての成熟が問われる場面です。
自尊心が傷ついた人は、素直に謝ることができません。
親と子の両方の自尊心が傷ついているので、第3者の立場から引っ込みがつくようにしてあげればいいのです。
『「育てにくい子」と感じたときに読む本』を読んで今後勉強すべきこと

『「育てにくい子」と感じたときに読む本』では、子育ての悩み解決について理解できたと思います。
親の目線での子育て論だったので、子ども目線から教育論について見てみたいと思いました。
そこで、200人を超える東大・京大・早慶を中心とした突出したリーダシップを発揮してさまざまなグローバル企業に進んだ学生に、両親に教育を振り返って感謝している点・直してほしかった点のアンケート結果が紹介されている『一流の育て方』を読んでみます。
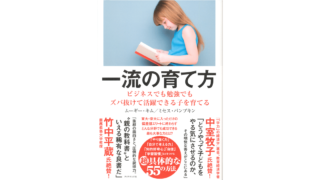
また、史上最年少プロ棋士・藤井聡太さんが幼児期に受けた教育として一躍脚光を浴びている「モンテッソーリ」教育を学ぶことができる『モンテッソーリ教育×ハーバード式 子どもの才能の伸ばし方』を読んでみます。
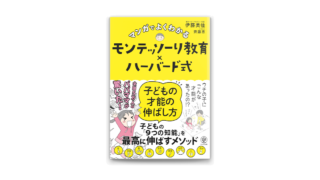
まとめ
『「育てにくい子」と感じたときに読む本』を書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんがご紹介させていただきました。
ですが、まだまだ育児について深く学んでいかなければならないと思いました。
そのため、いろんな本を読んでいきたいと思います。