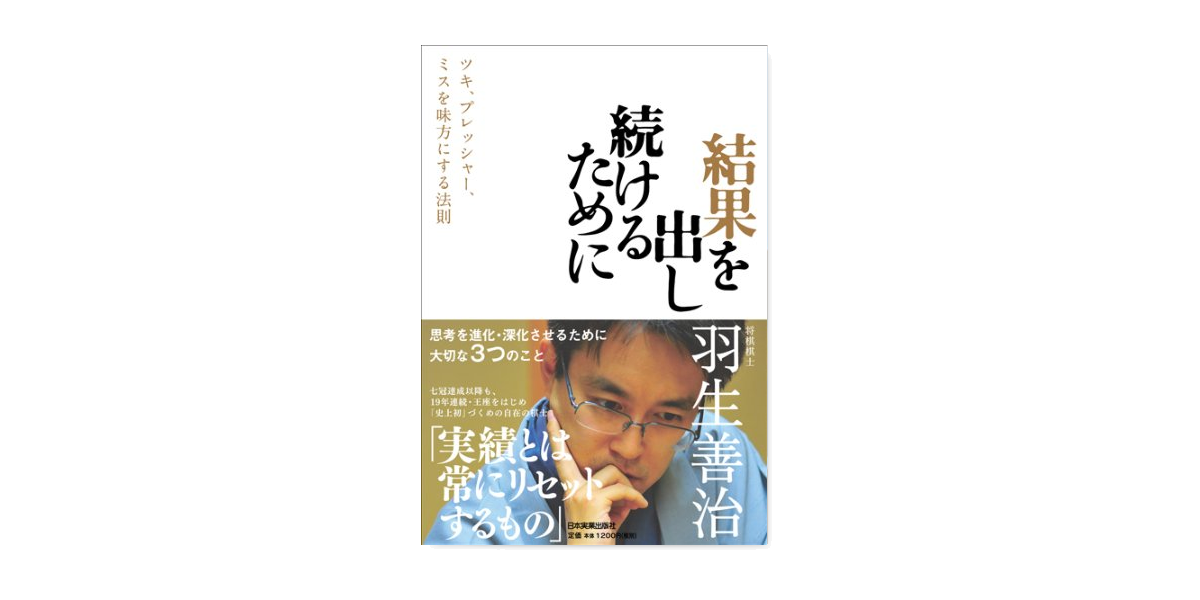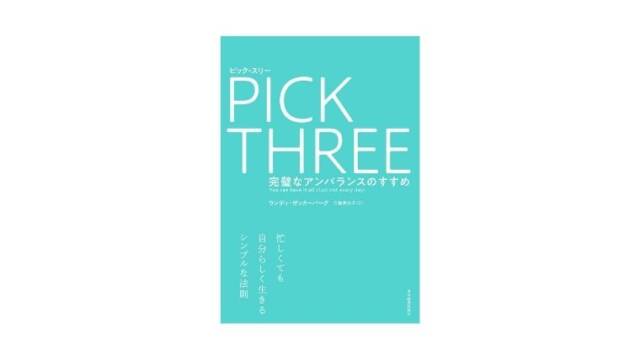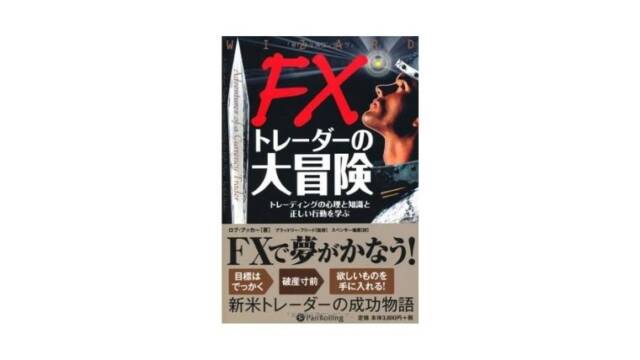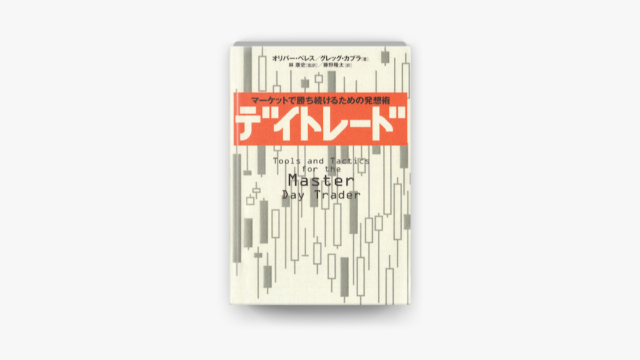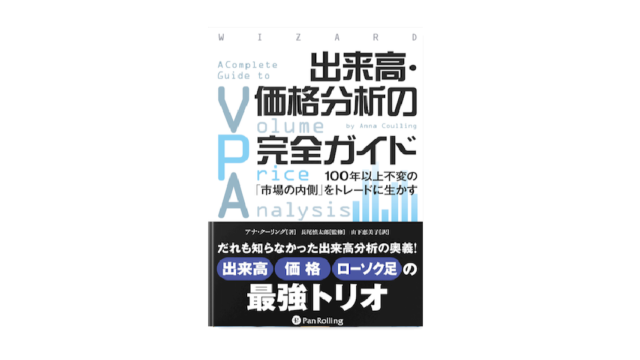投資の勉強をするために、たくさんの本を読んで勉強しています。
『結果を出し続けるために』を読んでいるだけでは記憶になかなか残りにくいため、インプットした知識を整理して、
- 「読んで勉強になったこと」
- 「理解が及ばず、さらに勉強をしなくてはいけないこと」
を感じたままに書き留めています。
とても勉強になりましたので、書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんがご紹介いたします。
目次
『結果を出し続けるために』とは?
| 読みやすさ | |
|---|---|
| 専門性 | |
| 役立ち度 |
- 著者:
- 出版社:日本実業出版社
- 発売日:2011/8/12
- ページ数:216ページ
【目次】
- 第1章:努力を結果に結びつけるために
- 第2章:ツキと運にとらわれずに、最善を選択する
- 第3章:一二〇%の能力を出し切る、プレッシャーとの付き合い方
- 第4章:結果を出し続けるにはミスへの対応が鍵になる
- 第5章 自ら変化を生み出し、流れに乗っていくために
- おわりに
将棋棋士の羽生善治先生の著書になります。
『結果を出し続けるために』では、将棋だけに限った話ではなく、変化が激しい時代の実力の磨き方が学べます。
「結果を出し続けるための3つの秘訣」という羽生先生自身の公演をもとに加筆修正された本です。
『結果を出し続けるために』を読むきっかけ

勝ち続けるためのマインドセットを学ぶために、プロゲーマーの梅原大吾さんの「勝ち続ける意志力」を読みました。

このような最前線で戦い続けてる人の本を色々読みたいと思いました。
1番初めに思いついた勝ち続けている人は、史上初の「永世7冠」を達成した「羽生善治」先生です。
羽生先生の書で「結果を出し続けるために」という本があり、学びたいことにぴったりだと思い、手に取りました。
『結果を出し続けるために』を読んで勉強になったこと

将棋では次の手を読むことをしますが、実際には自分の予想した通りにはなりません。
自分が予想できない中で、何をやっていくのきちんと羅針盤を定めて、どういう方向に進んでいくのかが大事です。
思考を進化・深化させるために大切な3つのこと、「ツキ・プレッシャー・ミスを味方にする法則」が、結果を出し続けるための大きな鍵です。
『結果を出し続けるために』は、この3つの法則を中心におきながら、様々な心理戦略についてまとめられた1冊でした。
第一章:努力を結果に結びつけるために
【第一章の小見出し】
- 対局中の九割は不利な状況を考えている
- 勝負で大切なこと
- 不調も三年続けば実力
- 不調の見分け方
- 技術以上に、わずかな気持ちが大きな差を生む
- うまくいかないときは他力思考
- 速い球は力で打ち返さない
- 誰だって報われない努力はしたくない
- 「もうひと息」の努力が結果につながる
この中でとても勉強になったのは「勝負で大切なこと」「不調の見分け方」です。
「勝負で大切なこと」は、3つあり、
- 恐れないこと:自分にとって必要でないものを見極めたうえで、決断しながら不要なものを捨てていくこと
- 客観的な視点を持つこと:局面を、自分の側、相手の側からではなく、審判のように中立的に見ること
- 相手の立場を考えること:自分にとって1番都合の悪い手を考えること
冷静沈黙にことを進めることが、勝負では大事であることが窺えます。
「不調の見分け方」は、4つあります。
- 結果を見るのではなく、内容だけを見ること:内容が良ければ不調、内容が悪ければ実力不足
- 身の周りで起こっている出来事を見ること:周りと歯車が噛み合っていない、不協和音があると感じているときは、何かが欠けている証拠。
- 自分の視点ではなく、第三者の視点で見たときに、「自分がどう映っているのか」を、他に人に確認してみること:不調のときは、自分で判断している基準すら狂っている場合も多い。
- 人から言われた言葉の感じ方の違いを見ること:「頑張ってください」を言われたときに、どのように受け取るかを感じてみること。うまくいってるとき、「ありがとうございます。」うまくいっていないとき、「そんなことを言われても、頑張っているよ。」
不調なのか、実力不足なのか、気持ちの切り替えが必要なのか、自分について理解することが大事なことがわかります。
第二章:ツキと運にとらわれずに、最善を選択する
【第二章の小見出し】
- ツキや運、流れ、バイオリズムは変化し続ける
- ツキや運に一喜一憂しない
- 次の一手の決断プロセス(直感・読み・大局観)
- 大局観では「終わりの局面」をイメージする
- 最後は玲瓏な状態で主観に頼る
- 見切りこそ決断
- 多くの選択肢は後悔しやすい
- データからの判断と野生の勘を組み合わせる
- 知識を知恵に高めるには自分の頭で考えるしかない
- 羅針盤が効かない状況が感性を磨く
この中でとても勉強になったのは、「次の一手の決断プロセス(直感・読み・大局観)」です。
将棋では決断の連続ですが、直感・読み・大局観を駆使しています。
まず意外なのが、「直感」で80通りの手から、カメラのピントを合わせるように2~3の可能性に絞り込みます。
「どこが1番のポイントなのか、急所なのか」を経験則的な感覚に近いもので、瞬間的に峻別・選別の取捨選択をしていきます。
次の手をシミュレーションをする「読み」に入っていきますが、①その手が良いかどうか②どこで読みを打ち切るかが重要になります。
読みの上達には、自分が選ばなかった選択肢を、可能な限り検証することです。
最後に、具体的な手というよりは、方針や方向性を考えるという「大局観」が大事になります。
大局観の特徴は以下の通りです。
- 直感と同じく、ロジカルな積み重ねの中から育ってくるもの、わかってくるもの。ただし、その因果関係は、直感と違って、証明しづらいもの
- たくさんのケースに出合い、多くの状況を経験していく中で、だんだん培われてくるもの
- 自分がやっていなくても、他の人が過去にやったケースをたくさん見ていくことでも、磨かれていくもの
- その人の本質的な性格、考え方が非常によく反映されるもの
経験を積めば積むほど大局観の精度が上がり、大筋の判断を誤ることが少なくなり、余計な手を読むことが省かれます。
第三章:120%の能力を出し切る、プレッシャーとの付き合い方
【第三章の小見出し】
- 最高のパフォーマンスはリラックス・楽しむ・集中から
- プレッシャーがかかっているときは八合目まで来ている
- プレッシャーがかかるほうが集中力、能力を発揮できる
- プレッシャーへの耐性は、まず自分の性格を知ることから
- 集中するためには、刺激を遮断する時間を作る
- 気分や体調の浮き沈みがあるのが前提だと考える
- 起こった感情には、ワンクッション変換を入れて対処する
- 結果は100%受け止めてから次に進む
- 心の状態は指し手に表われる
- 結果が表に出ないのは、力を蓄積している状態
- 結果よりも大事なのは自分にとっての価値
- 考え方は常に変化、進化する
この中でとても勉強になったのは、「プレッシャーがかかっているときは八合目まで来ている」です。
あともう少しで、ブレイクスルーができる、壁を打ち破ることできる、そういう状態のときにプレッシャーにかかることが多いです。
プレッシャーがかかる状況自体は、結構いいところ(八合目)まで来ている、と思うようにすればいいということです。
勝ちを確認すると羽生先生ですらミスができないから手が震え、逆に勝ちだという確信がないときには手が震えることがないそうです
この考えを持つことで、プレッシャーが能力・集中力を発揮するのには必要だという気構えに繋がります。
第四章:結果を出し続けるには、ミスへの対応が鍵になる
【第四章の小見出し】
- ミスをしない対局は一年に一回くらい
- 大きなミス、盲点に入ったミスはすぐに忘れること
- ミスをしたときの五つの対処法
- 反省はしても後悔はしない
- 不利になってもギャンブルはしない
- ミスがミスを呼ぶ二つの原因
- ミスを減らすには自分のミスの傾向を知る
- 苦手なものはずっとついて回ってくる
- 覚悟を持ってリスクを取る
- 意図的にアクセルを踏み、適切なリスクを取る
- 保守的な選択は10年後に最もリスクが高い
- 無謀ではないリスクの取り方
- 年代ごとの強みを理解する
この中でとても勉強になったのは、「ミスをしたときの五つの対処法」「無謀ではないリスクの取り方」です。
ミスをしたときの五つの対処法は以下の通りです。
- まず、一呼吸おくこと
- 現在に集中すること:過去を振り返るのは、終わった後にやればいい
- 優劣の判断は冷静に行うこと:ミスをしても依然として有利の場合もある
- 能力を発揮する機会だととらえること
- すべてに完璧さを求めないこと。自分の可能性を広げるチャンスだと、とらえること
ミスをしてしまった状況を立て直すことに全力で取り組み、活路を見出します。
しかし、ミスを恐れるばかりで、取るべきリスクを取らないのは、逆に危険だと羽生先生は示しています。
目の前のリスクを何でも取っていくのは無謀ですので、無謀ではないリスクの取り方を知っておく必要があります
無謀ではないリスクの取り方は以下の通りです。
- リスクは小出しで取る:一回一回は小さいリスクをとることを繰り返す
- リスクをとることへの恐怖との付き合い方:「このリスクを取れば、ある程度の確率で失敗する、負けてしまう」と前提、覚悟を持っておく
- リスクを取ること自体の快感には注意する
- 結果だけではなく、「納得できるか」
- 時代や環境に合わせてリスクを取る
内側と外側の両面を見ながら、リスクを取るべきかどうかを決めていくのが良いでしょう。
第五章:自ら変化を生み出し、流れに乗っていくために
【第五章の小見出し】
- コツがわからないものほど面白い
- 真剣に打ち込むことでしか見えない道
- 一人だけで強くなったわけではない
- 流れを見極める
- 人は、普通に続けられることしか続かない
- アイデアは距離を置いたときに生まれる
- 本質は価値にこそある
- 充実感は環境に左右される
- 不確実性を楽しむ
- 選択が道を決める
- 常に時代の先を歩いていた升田幸三先生
- グローバル化しても本質は見失わない
- 一人ひとりの影響力は想像以上に大きい
- 世界は「六次の隔たり」でつながっている
- 変化が激しい時代の実力の磨き方
- 情報や知識は自分で料理してこそ価値がある
- 才能とモチベーション
- 現在進行形の充実感
- 「成功」とは、自分のやりたいことと周囲の期待とが一致すること
- 期待と誤解は紙一重
- 気持ちこそ鍵
この中でとても勉強になったのは、「人は、普通に続けられることしか続かない」です。
自分にとって普通なことでないと、長い年月は続きません。
目標を立てずにまずやってみて、結果的にゴールについていたらいいなという柔軟なやり方が多いそうです。
プロ棋士なら細々と1日のルーティンや研究時間などを定めていそうですが、生活のルーティンは作っておらず、流動的に過ごしてる一面が驚きでした。
『結果を出し続けるために』を読んで今後勉強すべきこと

『結果を出し続けるために』で、一流の方の心理を学ぶことができました。
このような最前線で戦い続けてる人の本を色々読みたいと思いました。
羽生先生の次に思いついた人は、「イチロー」選手です。
大リーグ歴代22位の3089安打、日米通算ではピート・ローズの大リーグ記録4256安打を上回る4367安打を記録するなど、数々の偉業を達成しています。
その偉業の達成とは別に、弛まぬ努力・野球に対する姿勢も注目されており、それに注目した書籍が出版されていますので、読んでみたいと思います。
まとめ
『結果を出し続けるために』を書評・要約のようにまとまっていないかも知れませんがご紹介させていただきました。
投資をしていくためには、まだまだトレーニングが必要ではありますが、少しずつ実践していこうと思います。
より優れた投資家になるために、色々な本を読んでみたいと思います。