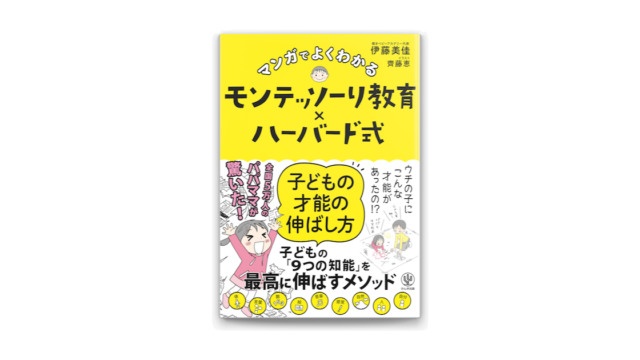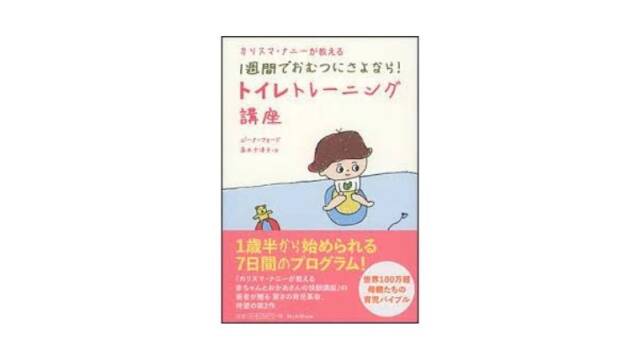母親の産道を通るため、他の哺乳類に比べて未熟な状態で産まれます。
乳幼児期は自分がいる環境に非常に敏感で、自分が安全な状態で生存できるかを本能的に感じ取っています。
そのため、「安心感」で赤ちゃんを満たしてあげる必要があります。
生後0~2か月の視力は、約0.01~0.02と周りが見えないため、母親を感じるには「聴覚・嗅覚・触覚」しかありません。
そのため、「音・匂い・スキンシップ」を与え、安心させてあげる必要があります。
今回は、「音・匂い・スキンシップ」を用いて安心感を与えられるように、まとめさせていただきます。
目次
赤ちゃんを安心感で満たすと何がいいの?

安心感は、赤ちゃんの脳にストレス反応システムが発達を促進させ、これが効果的に機能することでコルチゾールに対する反応など月齢と共に変化します。
新生児 抱き上げるだけでコルチゾール値が上昇する。
3か月 抱き上げてもストレスではないが、医師の診察などはストレスに。
6か月 医師の診察と注射によるコルチゾール反応が減少する。
9か月 信頼できるベビーシッターと2人きりになっても、コルチゾール値がほとんど上昇しない。
13か月 コルチゾール値を上げずに怒ることができる。出典:最高の子育てベスト55 p29
このシステムが働くことで、赤ちゃんの学習・理解などの神経回路が守られ、心血管と免疫システムが正常に機能できます。
人の表情を読む能力が発達のピークは「生後6カ月」であると言われていますので、このストレス反応システムについても関係してきます。
また、安らぎを感じるホルモン「オキシトシン」が脳から分泌され、情緒が安定します。
オキシトシンは「信頼のホルモン」とも呼ばれ、赤ちゃんとの関係性を深めるのにとても大切です。
安心感を与えないとどうなるか?
子どもは真似をするのが得意で、生後1時間で他人の表情の真似をしたりするほどなので、親のストレスに対する反応などもよく観察しています。
生後6ヶ月ほどでも、夫婦ケンカに異変を感じて、血圧・心拍・コルチゾールが上昇します。
赤ちゃんがいる手前で、「罵声を浴びせあう」「暴力をふるう」などの好ましくない反応をすると、赤ちゃんの心はとてもダメージを受けます。
これらの影響を調査した研究で以下のような傾向があるという結果が出ています。
- 両親が暴力的な喧嘩をするのを見て育った子は、感情を読む能力に欠ける傾向があった
- 両親が激しい口論をする姿を見て育った子は、感情を読みすぎる傾向があった
- 長期間、両親の喧嘩を見てきた子は、自分の感情(寂しい、怖いなど)をコントロールする能力に欠ける傾向があった
Development and Psychopathology(2014)「Poverty, household chaos, and interparental aggression predict children’s ability to recognize and modulate negative emotions.
ストレス反応システムが常に反応しているか、逆に全く反応しなくなるなど、生涯にわたって影響を与えてしまいます。
子どもの前でケンカをしてしまったときは、必ず「仲直りした姿」を見せましょう。
赤ちゃんに安心感を与える「音」
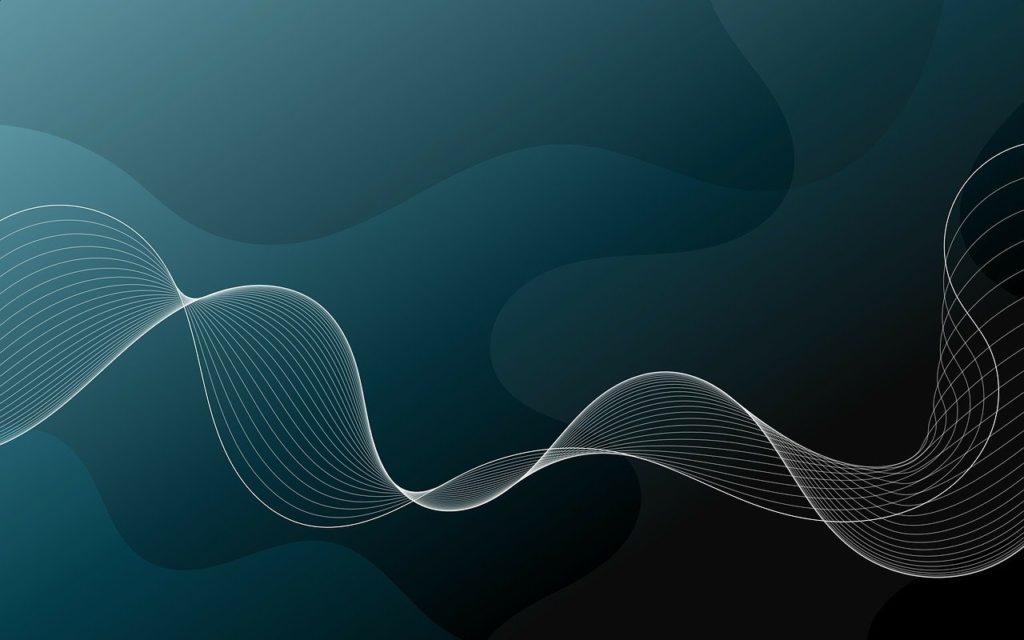
赤ちゃんに安心感を与える音として、以下のものが挙げられます。
- お母さんの心音
- お母さんの声
- マザリーズ(対乳児音声)
- ホワイトノイズ
- クーイングへの反応
胎児の脳は妊娠6ヶ月でできあがり、同時に聴覚もできています。
生後3ヶ月位で体内の記憶は忘れると言われていますが、情緒面に大きな作用があり、胎内で聞こえていた音に安心感を特に感じます。
また、自分が発する声・音に対する周りの反応などを感じることでも安心します。
お母さんの心音
赤ちゃんは、子宮内でお母さんの心音を常に約85dbという大音量で聞いています。
絶え間なく聴いていた赤ちゃんにとっては、その音は「究極の安心音」として心に刻まれています。
そのため、生まれたての赤ちゃんに心音を聞かせると、泣き止んだり・安らかになったり・眠たくなったりします。
心の与える影響だけではなく、身体にも影響を与え、体重増加を促します。
抱っこすることで心音を聴かせることもできますが、CDを使うなどの方法もあります。

お母さんの声
胎児の頃から、体内で反響したお母さんの声が、心音・雑音に混じって子宮の中に届いています。
産まれてからも、一番多く接する音が母親の声です。
この母親の声が、子どもに対して様々な影響を与えることは、多くの研究で明らかになっています。
「CNN」が伝えるところによると、2010年に実施された調査で母親の声でストレスホルモンが減少していくことも明らかにされています。
慶應義塾大学文学・中央大学・首都大学東京の研究グループは、生後2~7日の新生児が母親の語りかけを聞くことで前頭部~側頭部の脳機能結合を強めることを見出しました。
しかし、残念なことに、父親の声に関しては胎児の頃は聞こえていないため、父親の声は安心感という点では全く効果がありません。
効果がないですが、父子の絆の形成のためには大事なことですので、父親も優しく声掛けをしてあげましょう。

マザリーズ(対乳児音声)
マザリーズとは、赤ちゃんをあやすときの自然に出てくるやわらかい声かけのことで、専門的には「対乳児音声=Infant Directed Speech」といいます。
特徴として、「話す声のトーンが高い・抑揚を大きく・ゆっくりしたテンポ・反応を待つように間をとる・同じ言葉/を繰り返す」などあります。
マザリーズは、模倣しやすい特徴であり、乳児は養育者の声や表情から感じられる情動を感知し、 情動調整・情動調律をしていくようになります。【Stern, D. M., Spieker, S., Barnett, R. K., & MacKain, K.(1983)The prosody of maternal speech: Infant age and context related changes. Journal of Child Language, 10, pp.1-15.】
また、マザリーズには相互作用があり、お母さんの情緒調整機能もあるため、産後うつ対策にも良いとされています。
また、大人向けの話し方よりもマザリーズの方が、脳の左半球で注意喚起に関連する反応を示すことが明らかになっており、注意をひきつけるだけではなく、言語の理解を促す効果があるということが報告されています。【Zangl, R., & Mills, D. L.(2007). Increased brain activity to infant-directed speech in 6- and 13-month-old infants. Infancy, 11, pp.31-62.】
お母さんだけはなく、お父さん・祖父母でも効果的ですので、いっぱい話しかけてあげましょう。

ホワイトノイズ
「ホワイトノイズ」は、赤ちゃんがおなかの中にいた際に聞こえていた心臓音、胎内音と似たような音であることがわかっています。
ホワイトノイズとは、全帯域にわたるひとつひとつの周波数をほぼ均等に持ったノイズで、単調で予測可能な退屈な音です。
以下のような音がホワイトノイズの一例として挙げられます。
- テレビの放送終了後に流れるザーというノイズ音
- 口で「シー」と言う音
- 換気扇・扇風機の音
- ビニール袋の擦れる音
- 掃除機
- ドライヤー
- 波の音
- 雨の音
赤ちゃんに与えるホワイトノイズの効果として、「安心・鎮静化」「音のカーテン」が挙げられます。
「胎内音に近い音が新生児の鎮静効果に役立つ」という研究が2013年に「日本生理人類学会誌」で発表されています。
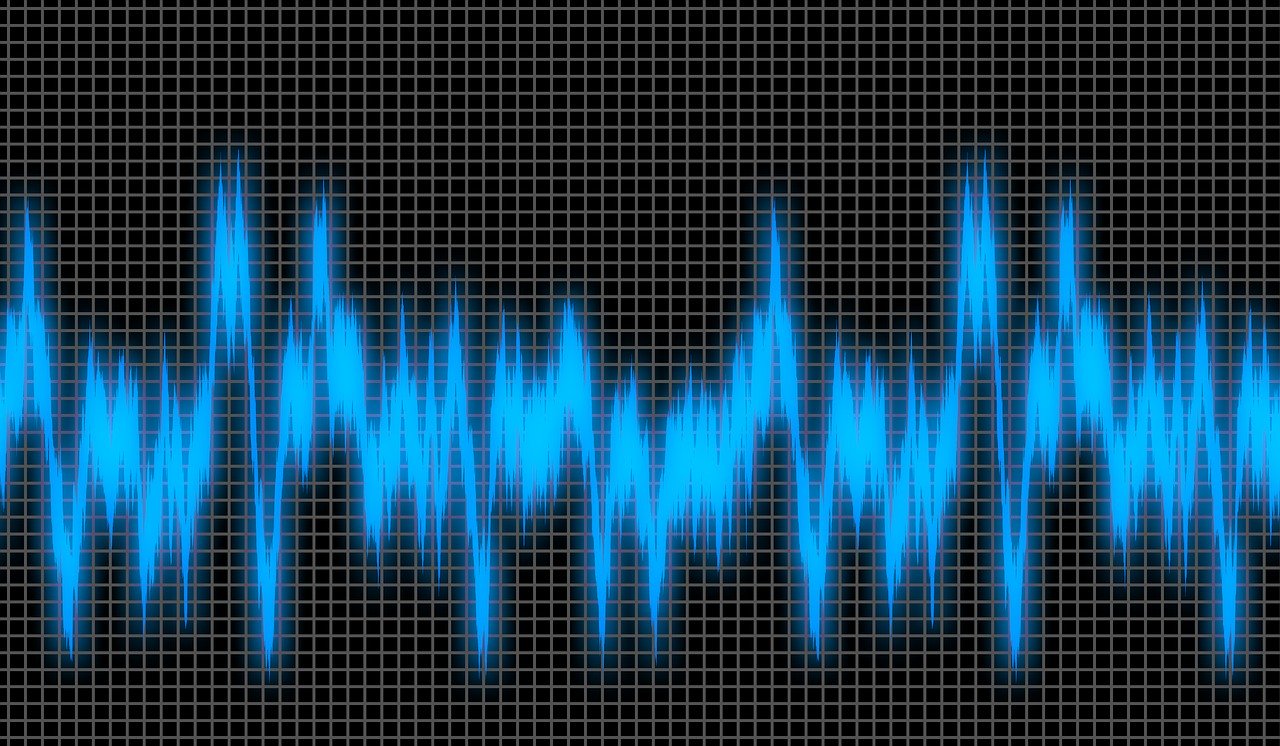
クーイングへの反応
生後1か月ごろになると、母音を中心とした「あー」「うー」などクーイングと呼ばれる声を発するようになります。
クーイング=「cooing」で、ハトの鳴き声に似ているのが由来です。
口や唇を使わずに発せられ、言葉の発達に欠かせないもので、声帯やのどの筋肉が発達に関係してきます。
面白いことに、赤ちゃんの意志とは関係なく勝手に声が出てしまうようで、自分が発した音にびっくりして泣いてしまうこともあります。
赤ちゃんが喉から発せられていることに気付いて、繰り返しクーイングをしたりして、音を楽しんみます。
このクーイングに対して、「オウム返し・優しく話しかける」など反応してあげることが良いことだと分かっています。
- 言語能力・聴覚能力の発達
- 情緒の発達
に良い影響を与えていることが分かっています。

赤ちゃんに安心感を与える「匂い」

赤ちゃんの嗅覚はママとの愛着形成に欠かせないコミュニケーションツールです。
生まれるまでに一番嗅いできた匂いである「母親の匂い」にとても安心感を覚えます。
赤ちゃんは胎児の頃から嗅覚があり、「羊水の匂い」には母親の匂いがあるため、赤ちゃんを安心します。
また、「母乳の匂い」も強い安心感を与えます。
生まれたての赤ちゃんは目がほとんど見えませんが、自分のお母さんの母乳の匂いからおっぱいをかぎ分け、乳首をくわえることができます。
本能的に母乳があることに対しての安心感があります。
赤ちゃんは母親との匂いのやり取りに関してとても重要であるため、匂いの強い「香水・柔軟剤・消臭剤」に要注意です。

赤ちゃんに安心感を与える「スキンシップ」

生後9週の赤ちゃんと親を5分間別々の部屋にいてもらったところ、赤ちゃんの額の温度が1℃近く下がったという研究があります。【小林登「赤ちゃんの心をサーモグラフィで測る―母子分離による顔面皮膚温度の変化と愛着」『周産期医学』第26巻、1号】
「親がそばにいるか」を感じており、親ではない人が同じ部屋にいても額の温度に変化は出なかったのです。
未熟な赤ちゃんが親から離れるということは生死に関わるため、本能的に恐怖を感じます。
スキンシップにより、神経伝達物質の放出が促進され、コルチゾール値を下げることでストレスホルモン値を低下させ、安らぎを感じるホルモン「オキシトシン」が脳から分泌を促す必要があります。
スキンシップにより「情緒安定」「脳の発達」という効果をもたらします。

まとめ
「音・匂い・スキンシップ」を用いて安心感を与えられるように、まとめさせていただきます。
残念ながら、内閣府子ども・子育て白書によると、親子の平均的接触時間は減っており、子どもと触れあい、ゆっくり会話をするといった時間は減ってしまっています。
子どもと触れ合い・関わる時間を増やしてあげることが、子どものため・親のためになりますが、ご自身のペースで育児を出来る範囲で良いものにしていきましょう。