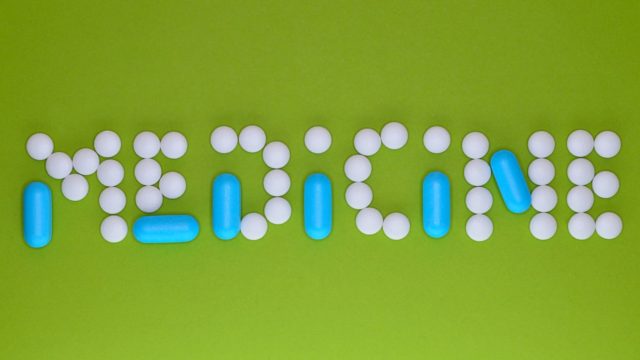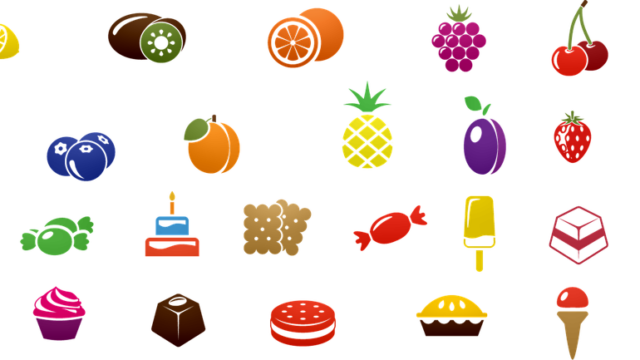妊娠中に摂取すべき栄養素として、
- 葉酸
- 鉄分
- タンパク質
- ビタミンD
などが挙げられると思います。
その中でも今回は、「ビタミンD」についてまとめさせていただきます。
目次
妊娠期・授乳期に摂取すべきおすすめ栄養素について 〜ビタミンD〜

ビタミンDは、脂溶性ビタミンであり、腸管のカルシウムの吸収促進し、血液中のカルシウムとリンの濃度を調整し、骨の石灰化(カルシウム沈着)を起こすことで、骨の成長や再生に関わっています。
たんぱく質と結合して、ビタミンD・ビタミンD( 25(OH)D )・ビタミンD( 1,25(OH)2D)として血液中に存在します。
津川尚子によると、ビタミンDは骨の成長や再生だけでなく、細胞増殖・分化調節作用・免疫調節作用・骨格筋機能・血圧調節作用・心血管系疾患に関係しています(甲状腺・骨代謝疾患診療マニュアル。p7-11。)
ビタミンDは、ビタミンD2からビタミンD7まであり、生理学的に重要なのは、
- ビタミンD2(エルゴカルシフェロール)
- ビタミンD3(コレカルシフェロール)
のみです。
「ビタミンD2」と「ビタミンD3」を比較すると、2つの働きはほとんど同じですが、ビタミンD2は「骨密度を高める」効果が若干高く、ビタミンD3は「免疫力向上」効果が若干高くいです。
骨=カルシウムの間違え
妊婦さんは、カルシウムを多く摂取すると良いと勘違いするかもしれません。
妊娠したからといって、多くカルシウムを摂取する必要はありません。
妊娠中はカルシウムの吸収率が高まることが知られているため、妊娠していない成人女性の摂取量(600~700mg)で十分です。
骨=カルシウムと思われがちですが、ビタミンDがあってはじめてカルシウムが骨に定着します。
ビタミンDの必要摂取量

このことから、2020年に改定された「日本人の食事摂取基準」(厚生労働省)にて、1日に食事から摂取するべきビタミンDは男女ともに8.5μg/日とされています。
過去は以下のような基準でしたが、2020年の改定に伴い、一律で増量されました。
- 妊娠していない成人女性:5.5μg/日
- 妊婦:7.0μg/日
- 授乳婦:8.0μg/日
これの前提には、1日に必要なビタミン量15μgから、食事以外に紫外線から合成する量の目安を10μgを差し引いたと仮定しています。
乳児のみ5µg/日としています。
これは母乳中のビタミン D 濃度は、日本食品標準成分表 2015 年版(七訂)では、従来の測定法により0.3µg/100gとされているためです。
「国民健康・栄養調査」(厚生労働省)で、授乳婦の場合で2.4μg/日も足らないとされており、深刻なビタミンD不足状態です。
ビタミンD不足の予防には、高齢者では少なくとも1日10μg、ビタミンD不足があれば20μg程度は必要だと言われています。(岡崎 亮.日老医誌 2009:46;125-7.)
上限について
上限は1日100μgであるため、上限は全く気にするにする必要がありません。
紫外線による皮膚での産生は調節されており、必要以上のビタミン D は産生されない。したがって、日照によるビタミン D 過剰症は起こりません。
また、ビタミン D は、肝臓及び腎臓において活性化(水酸化)を受けるが、腎臓における水酸化は厳密に調節されており、高カルシウム血症が起こると、それ以上の活性化が抑制されます。
しかし、乳児の場合は、25 µg/日が耐容上限量とされています。
ビタミンDが不足した場合

ビタミンD欠乏によって、妊婦・胎児の骨に深刻な影響を及ぼすだけでなく、早産・喘息のほか、胎児の生涯に渡って病気リスクとの関連が指摘されています。
妊婦の極端なビタミンD欠乏は、高血圧・子癇前症・妊娠性糖尿病のリスクを高めます。
京都大学依藤亨医学研究科講師(発達小児科学)らの研究グループによると、1120人の新生児の頭蓋骨(ずがいこつ)を調べたところ、指で軽く押してみるとピンポン球のようにへこむ状態の「頭蓋ろう」という症状が246人に認められました。(「日本人正常新生児にはビタミンD欠乏症が高頻度に見られ、母乳栄養児で特に改善が遅れる」京都大学依藤 亨 医学研究科講師(発達小児科学)らの研究グループ)
井上大輔によると、癌、心血管イベント、結核、認知症、うつ病、高血圧、メタボリックシンドローム、肥満、2型糖尿病なども関係があります。(甲状腺・骨代謝疾患診療マニュアル。p202-6。)
ビタミンDが不足を解決する方法

ビタミンDが不足する原因は主に2つです。
- 紫外線を浴びる
- 食事による摂取
夏場の場合、紫外線を10~15分浴びることで、必要なビタミンDを合成できますが、冬場の場合、札幌では約4時間ほど外にいる必要があります。
そのため、食事による摂取についても考えなければなりません。
紫外線を浴びる
ビタミンDは、日光を浴びることで紫外線を受け、皮膚でコレステロールから合成されます。
妊娠を機に肌が敏感になり、肌トラブルを気にして過度に日焼け止めなどのUVケアをしてしまったり、外出を控えると、十分な量のビタミンD合成を難しくしている可能性があります。
しっかりと顔と手に紫外線を10~15分浴びると1日に必要な必要なビタミンDを合成できます。

食事による摂取
冬は緯度40度を越える地域(秋田や岩手以北)では日光浴だけではビタミンDが不足するとも言われています。
また、皮膚が弱いなどで日光に極力当たらないほうがいい場合もあります。
そういう場合は、ビタミンDを食べることで摂取する必要があります。
ビタミンDを多く含む食材は、ビタミンD2はキノコ類・ビタミンD3は魚です。
- 干しシイタケ
- きくらげ
- シラス干し
- ベニザケ
- イワシの丸干し
牛のレバー・チーズ・卵黄にも少量ながらビタミンDが含まれています。
しかし、つわりなどで必要量を食べることが不可能な場合がありますので、サプリメントを利用するのも一つの選択肢です。
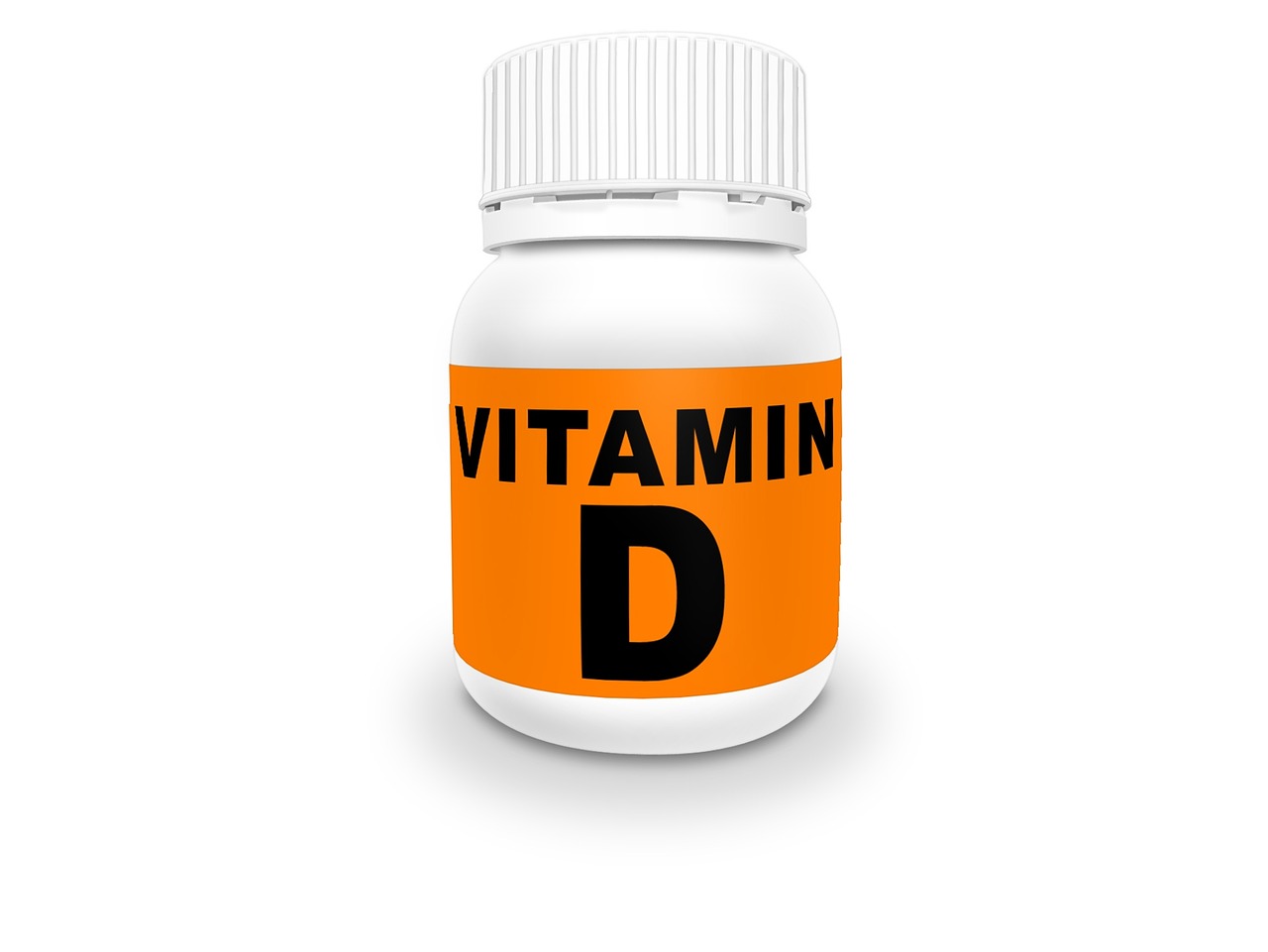
まとめ
妊娠期・授乳期に摂取すべきおすすめ栄養素としてビタミンDをまとめさせていただきました。
ビタミンD以外にも摂取すべき栄養素がたくさんあります。
それらについては以下をご参照ください。